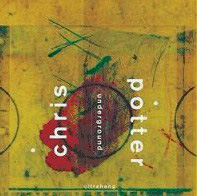
『Chris Potter/Ultrahang』
ArtistShare
Chris Potter(sax)
Adam Rogers(g)
Craig Taborn(fenderrhodes)
Nate Smith(ds)
1. Ultrahang
2. Facing East
3. Rumples
4. It Ain't Me, Babe
5. Time's Arrow
6. Small Wonder
7. Boots
8. Interstellar Signals
クリス・ポッターである。
受験勉強していた高3の息子に「まじかよ!そんなサックス奏者いるのかよ!」とヘラヘラした顔で言われるのは、どうだとばかりにクリス・ポッターのヴィレッジ・ヴァンガード・ライブ盤を聴かせた群馬県太田市金山町の交差点で、「これはな、いまNYで最も実力と人気があるハリー・ポッターというサックスだ!」と勝ち誇ってしまったせいだ。子どもたち4にんみんながサウンドに耳をたてるので、どうもおかしいと思ったが。言い間違えた。クリス・ポッターというんだ。おとうちゃんもう音楽のこと書くのやめたほうがいいよ。最近も言われてるんだよな。
クリス・ポッターとマーク・ターナーがこの10年にNYダウンタウンシーンで中心的地位を確立したサックス奏者であることはすでに述べた。そろそろ出てきたターナーの醍醐味が記録された録音は、昨年わたしが年間ベストと掲げたカート・ローゼンウィンクルのヴィレッジ・ヴァンガード・ライブ盤『レメディ』で、これはArtistShareというレーベルの作品だった。この、ArtistShareで!、クリス・ポッターが新譜を出すというのだから心臓がドキドキする期待をおれは当然持つ。持って当然だろ。
結論を述べると、決めて出てきたなポッター、外角ギリギリ狙いの予期せぬファンク・スライダー、バッター、ニセコロッシ、おれ、バットをつい大きく振ってしまう、空振り!、ストラク・ツー・ノー・ボール!勝負がついたわけではないぞ。そんな、実にタイトに仕上げてきた高水準な盤となった。
1曲目にこのレコーディングの特質が凝縮している。抑制されたファンク感を聴く。複雑な変拍子、全員縦割り譜面設計図付き、だけど身体性で硬直を回避している、ファンク感、を、聴く。カッコイイ。ずったら、ずったら、の、中毒性がある。
(ギターのインを聴いておいらがちとやな予感がしたのは、デヴィット・トーンのECM盤『プレゼンス』ECM1877になったりしてはいないよな!というものだった。そいえば『プレゼンス』も、本作と同じく実力者クレイグ・テイボーンがフェンダーローズで参加しているサックス・カルテット編成なのだよ。アヴァン・シーンの大物サックス奏者ティム・バーンの実質盤だのに!バーンの怪物自主レーベルscrewgun“スクリューガン”とECMの共同プロジェクトだのに!あのコケオドシのプログレ作戦はなかったよね。おれは泣きながらユニオンに売ったよ。
http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin
/day?id=7590&pg=20070728
ううむ。この『Ultrahang』、全体として、「どっか、聴いたことある感」てのを、突き破ったもんがないんだよな。つい、タイコをディジョネットに置換して聴いてみたくなったり、つい、ナシート・ウエイツならこのあたりの叩きはどうだろうと思ってみたりもする。このバックで若きオズビーに吹かせる空想もしてしまう。M−BASEも昇華したかの現代性が狙われているか。なあ、3曲目のファンクはオズビーに替われと言いたくなるだろ。おいおいおい、この3曲目、おいらにはサイコーなベースが聴こえるんだが・・・。
編成としてはベースレスであるけれども、ベースの役割はクレイグ・テイボーンのフェンダーローズが十二分に負っている。テイボーンはじつにいい仕事をこなしており、これがピアノでの参加ではうまくゆかないであろうし、キーボード奏者として適切な身の処しかたでもある。いま、ピアノというのはじつに難しいのではないか。例外的に菊地雅章がモチアンとの行程で現代性を放つようにわたしは観ているが、むしろ菊地の存在ゆえにジャズピアノ生態系は何人も入り込めない、圧倒的存在への畏怖というか、おじけづいた空気に覆われているものか。
ポッターの存在に気付いたのも菊地が参加する『ポール・モチアン・オン・ブロードウェイvol.4』(2006)だったこともある。そこでのポッターは、おいおいおいと呆気にとられるほどに奔放であり、ず太く、サウンドを支配してしまう、モチアンと菊地を相手に、だ、そのソロのありようにわたしはびっくりしたのだ。そこでのポッターをインプロヴァイズドに晒された「裸のポッター」と形容するならば、ヴィレッジ・ヴァンガード・ライブ盤2種『Lift』(2004)と『Follow the Red Line』(2007)は奔放に活躍する「旬のポッター」である。
本作『Ultrahang』は、ポッターのグループ、アンダーグラウンドのスタジオ録音で、これまでのスタジオ録音盤に比べるとはるかに出来はいいのだが、「裸のポッター」「旬のポッター」とは、また違った奏者のように聴こえる。それまでのポッター像を踏まえなければ、実力奏者以上のものをおれは感じなかったかもしれないのだ。ブレッカーなり、オズビーなり、オーネットなりを踏襲したうえで、現代的立場を誇示するかのような実力サックス奏者・・・、ちょうどいい、ポッターはホランドのグループで研鑽を積んでおり、ホランドのグループとこのグループのツアーで忙しいということであれば、なるほど、ホランドの弟子であるような緻密なコンポジションの継承を漂わしていると納得し得る水準と読むことも可能だ。
NYジャズサイトall about jazzにポッターのインタビューがある。ポッターがスティーリー・ダンとも録音していたことや、最近ハンコックとも共演を果たしていることを知る。なんだいポッター。ホランド、モチアン(8曲目はモチアン・リスペクトだろ?)、に、スティーリー・ダン、ハンコック。どの先達の養分も血肉にするヌエのような存在に感じたりもする。おれ、最近になってハンコックの『マン・チャイルド』、むかしはあれだけ耳を閉ざしていたのに、じつにハンコックの見えないカミソリのよなソロと天才的なファンクの効果に感じ入っていたこともあって、その反響を『Ultrahang』に適応させて聴いていたりもする。
そんなカンジで、おれはここでのポッターを「アマルガムのポッター」とする。影響・反響関連が合成された、耳の感性ものさしをいかようにも合わせうる奇妙な力作、という実感だ。1曲目と3曲目のカップリングでCDシングルだったら、おれの耳は飢餓感にのどが渇きまくるぜ。まずはツー・ストライク。次は、どう来る?ポッター。JT
(多田雅範)
*「ArtistShareというレーベル」
http://www.artistshare.com
/home/default.aspx
このCDのうらに“An artistShare fan-funded project”とクレジットがあるが、このレーベルはそのミュージッシャンの支援者の出資によって制作がなされるものだという。ミュージシャンの自主性を活かすような慧眼プロデューサーによるものかと思っていたおいら的には、なーんだ、という気持ちである。でも、現象的には、作品たちのクオリティも含めて、じつに興味深いレーベルだと思う。コンポスト編集長益子さんに教わった。
*「コンポストcom-post」
http://com-post.jp/
現代ジャズという視点を持つ批評サイト。
*クリス・ボッティ
スムース・ジャズの文脈にあると思われるトランペッター。おれはボッティの『イタリア』国内盤新譜背表紙を見て「クリス・ポッターの新譜じゃんか!」と手にしていたすさまじい勘違いから出会い、ボッティの甘く抑制の効いたシビれるようなペットの鳴りに魅了された。おれん中では、マイルスの『死刑台のエレベーター』テーマとの出会いと同じディレクトリーに入っている幸福な体験だ。