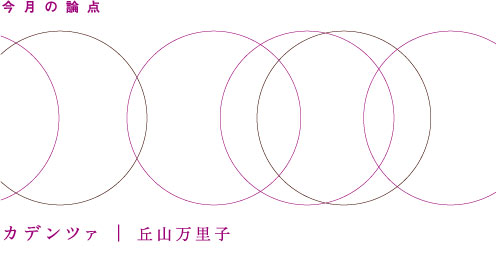
Vol.30 �b ���R�c�q�� (pf) �����|�p��܂ɂ悹��text by Mariko OKAYAMA
���N�A���U�ɔ��\����閈���|�p�܂̉��y����ŁA���N�̓s�A�j�X�g���R�c�q������܂����B�����i�V���j�����Ȃ��Ƃ����B
���Ƃ����ꂪ�����h�q�̃f�r���[50���N���}���ẲX���������ɁA�ł���A��ʂɂ��������R�Ɏv��ꂽ�낤�B�܂Ƃ����̂́A�����������ǂ��m��ꂽ�r�b�O�l�[���ɗ^������̂����ʂ��B
�ł�����̉��R�c�q���́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�m��l���m��I�ȑ��݂ŁA���̒��ł��A�M���I�ȃt�@���ƒf�Ŕے�g�Ƃɂ͂����蕪�����^�C�v�̃s�A�j�X�g�ł���B
���������āA����̎�܂̈Ӗ��͑傫���B

photo by �ъ��큗���R�@�i�s�A�m�F�x�q�V���^�C���j
�u�R�����q�F�������܂�B�˕��w����w���y����ȗ��_�ȉ��y���w��U�B���y�]�_�ƂƂ��āu�����V���v�u���y�̗F�v�ȂǂɎ��M�B���{��w�����w�����u�t�B�����Ɂu驂��������̉z���䂭���́v�i�[��p���j�u�Ăז����̔ޕ��ցv�i�y�Ёj�u���y���̉��F�v�i�Ёj���B
 1.31 '16
1.31 '16
�Ǔ����W
�|�[���E�u���C Paul Bley
![]() �F
�F
#1277�w��F�ljp�X�y�V�����r�b�O�o���h�^���C���E�A�b�g�E�V�h�s�b�g�C���x(�s�b�g�C�����[�x��) �]���R��
#1278�wDavid Gilmore / Energies Of Change�x(Evolutionary Music) ��Օ�
#1279�wWilliam Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989�x(NoBusiness Records) �֓���
#1280�wChris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality�x(Clean Feed) ���c ��
#1281�wGabriel Vicens / Days�x(Inner Circle Music) �}�C�P���E�z�v�L���X
#1282�wChris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality�x (Clean Feed) �u���[�X�E���[�E�M�������^�[
#1283�wNakama�^Before the Storm�x(Nakama Records) �דc���k
![]() �F
�F
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
�������ɂ��郊�A���E�W���Y�@�|�@�j���[���[�N����̃��|�[�g
by �V�X�R�E�u���b�h���[ Cisco Bradley�C���c�� Takeshi Goda, ꎓ��� Akira Saito & �@���ߖ� Rema Hasumi
#10 Contents
�E�g�����X���[���h�E�R�l�N�V���� ���c��
�E�A�ڑ�P�O��F�j���[���[�N�E�V�[���ŐV���C���E���|�[�g�������[�X���
�V�X�R�E�u���b�h���[
�E�j���[���[�N�F�ϗe����u�W���Y�v�̂���
��1��@�`���ƑO�q���Ȃ����@�|�@�A�i�C�X�E�}���B�G���@�@���ߖ�
���̌����镗�i
�uChapter 42 �쓈�N�Y�v�]���R��
�J���T�X�E�V�e�B�̐l�Ɖ��y
#47. �`���b�N�E�փf�B�b�N�X���Ƃ́g�I�[�j�\���W�[�h:�`���[���[�E�p�[�J�[�E�q�X�g���J���E�c�A�[ �qPart 2�r �|���m�q
�y������̒����ǂ���`�F�b�N
#263 �w��F�ljp�X�y�V�����r�b�O�o���h�^���C���E�A�b�g�E�V�h�s�b�g�C���x (Pit Inn Music)
#264 �w�W�����W���E�P�C�W�� ��t�L�� ���c�Ǖv�^���~�i���g�x (Amorfon)
#265 �w�����ƕv���C�W���O�E�T���E�o���h�^NY Groove�x (Ratspack)
#266 �w�j�R���C�E�w�X�E�g���Ifeat. �}�������E�}�Y�[���^���v�\�f�B�`�n���}�[�X�z�C�̈�ہx (Cloud)
#267 �w�|�[���E�u���C�^�I�[�v���A�g�D�E�����x (ECM�^���j�o�[�T���~���[�W�b�N)
�I�X���Ɋw��
Vol.27�uNakama Records�v�c������
�q���E�z���V���N�̊y�ȉ��
���S�wPaul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop�x (Steeple Chase)
![]() �F
�F
#70 (Archive) �|�[���E�u���C (Part 1) �{���L�`
#71 (Archive) �|�[���E�u���C (Part 2) �{���L�`
![]() �F
�F
#871�u�R�W�}�T�i�G=���ܗ���=��삱���� New Year Special Live!!!�v����N�k
#872�u���̂悤�ɂ�������Ȃɂ��̂� Things to Hear - Just As�v������
#873�u�f���B�b�h�E�T���{�[���v�_��G�Y
#874�u�}�[�N�E�W�����A�i�E�W���Y�E�J���e�b�g�v�_��G�Y
#875�u�m�[�}�E�E�B���X�g���E�g���I�v�_��G�Y
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
