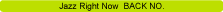Jazz Right Now - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito, 吉田野乃子 Nonoko Yoshida & 蓮見令麻 Rema Hasumi
・音楽を進化させる異邦人 剛田 武
・連載第9回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報 (シスコ・ブラッドリー)
・よしだののこのNY日誌 第7回(最終回) 吉田野乃子
・ライヴ・レポート:吉田野乃子@Stone 蓮見令麻
・インタビュー:ジョシュ・エヴァンス 齊藤聡
アルベール・カミュは、母の死にも自堕落な生活を改めず、殺人の動機を「太陽が眩しかったから」と述べる男を主人公に、人間社会に存在する不条理を描いた小説を『異邦人 L'Etranger』と名付けた。久保田早紀は、別れの哀しみから生まれ変わるためにシルクロードを彷徨う旅人を「異邦人」と歌った。スティングは新しい希望の街ニューヨークにあっても、古臭い英国人の精神を捨てられない自分を皮肉を込めて「異邦人 Alien」と呼んだ。「異邦人」という言葉には、単に別の社会・文化圏から来た見知らぬ異人というだけではなく、宗教的な選民思想(Elitism)とまでは言わなくとも、周りと異なることを自らの誇りとする、確固たる信念や生き様が投影されているに違いない。
元々アメリカは移民の国である。つまり異邦人の寄り合いがいつしか「合衆国」として成り立ってしまったのである。いわば烏合の衆の国家の最大の都市ニューヨークこそ、エトランジェやエイリアンの心をもっとも魅了する街であり、あたかもリンゴの表皮を食い千切り、穴を穿ち中に潜り込む腹ペコ青虫のように、地下深くまで潜入した「異邦人」を受け入れる土壌が培われている。時代が変わっても、常に古い異邦人が新しい異邦人と交歓し、新たな果実を生むことが、ビッグアップルの創造力がいつまでも色褪せない秘密なのであろう。
Jazz Right Nowに登場する異邦人(カッコ内は楽器と出身国):
パク・ハンアルHan-earl Park(g, アイルランド)
ミッコ・イナネン Mikko Innanen(sax, フィンランド)
連載第2回
⇒http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/002.html#02
パスカル・ニゲンケンペル Pascal Niggenkemper(b, ドイツ)
連載第3回
⇒http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/003.html#02
ヨニ・クレッツマー Yoni Kretzmer(sax, イスラエル)
連載第5回
⇒http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/005.html
メッテ・ラスムッセン Mette Rasmussen(sax, デンマーク)
連載第6回
⇒http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/006.html
蓮見令麻 Rema Hasumi(p, 日本)、永井晶子 Shoko Nagai(p, acc, 日本)
連載第8回
⇒http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/008.html
リューダス・モツクーナス Liudas Mockunas(sax, リトアニア)
連載第9回(今号)
7回に亘って連載記事『よしだののこのNY日誌』を執筆していただいたサックス奏者・吉田野乃子さんが、この12月に9年半住んだニューヨークに別れを告げて帰国された。連載は終わるが、彼女が異邦人でなくなるわけではない。ニューヨークであれ北海道であれ、何処に居を構えようとも、他者と異なる自分の表現を求める者は皆「異邦人」なのである。これからも他の異邦人との出会いを通して新たな表現の扉を開いていくことになるだろう。
ちなみに彼女がニューヨークを離れた理由は「太陽が眩しかったから」ではない(と信じたい)。
関連リンク
http://www.jazztokyo.com/live_report/report281.html
http://www.jazztokyo.com/event/event006.html
http://www.jazztokyo.com/live_report/report616.html
剛田 武 Takeshi Goda
1962年千葉県船橋市生まれ。東京大学文学部卒。レコード会社勤務の傍ら、「地下ブロガー」として活動する。80年代東京地下音楽に関する書籍を執筆中。
ブログ「A Challenge To Fate」 http://blog.goo.ne.jp/googoogoo2005_01
ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
translated by 齊藤聡 (Akira Saito)
アンドリュー・バーカー Andrew Barker
過小評価されているドラマーのアンドリュー・バーカー Andrew Barkerは、ゴールド・スパークル・バンド Gold Sparkle Bandの活動によって知られているが、このたび、自身の名を冠した注目すべきデビュー作『Barker Trio』を出した。激しく大胆なテナーサックス奏者マイケル・フォスター Michael Fosterとアヴァン・ロックのベース奏者ティム・ダール Tim Dahlをフィーチャーしており、また、1曲にベース名人のジェームス・イルゲンフリッツ James Ilgenfritzが参加している。1998年にNYに進出して以来、バーカーは多くのエキサイティングな演奏に加わってきた。共演者は、ベース奏者ウィリアム・パーカー William Parker、多楽器奏者ダニエル・カーター Daniel Carter、アルトサックス奏者チャールズ・ウォータース Charles Watersなど多彩だ。バーカーが解き放つ大渦巻には粘り強さのようなものがあり、それは共演者を浮揚させる。ダールが駆動するベースラインは音楽を瀬戸際まで追いやり、また同時に落ち着かせて互いを結び付け、推進力となって次々に音楽を噴射する。フォスターは、ようやくブルックリンで正当な評価を受けるようになってきた。彼は、火傷してしまうほどの熱気を、アンサンブルの無謀さにうまく結び付けている。バーカー・トリオは、1年以上もの間、NYの観客に強烈な印象を与えてきた。このレコードが、願わくは、他国のリスナーの耳に届きますように。
 |
 |
| The Barker Trio, photo by Peter Gannushkin | 『Barker Trio』 |
ウィリアム・フッカーとリューダス・モツクーナス William Hooker and Liudas Mockunas
NYを拠点として活動するドラマーのウィリアム・フッカー William Hookerと、リトアニアのサックス奏者リューダス・モツクーナス Liudas Mockunasとが、印象的で、燃えるようで、また瞑想的でもある盤『Live at Vilnius Jazz Festival』(No Business, 2014)を出した。このアルバムには4曲が収録されていて、最初から最後まで聴きとおすことが愉しいものだ。フッカーは語りかけるような緊張感を保つのが非常に巧く、それを終始見事に披露している。おそらく、最も効果的なフッカーのワザは、ドラムスで二度と同じことをしない点だろう。彼は計算づくでマレットやシンバルを駆使し、拡張し、モツクーナスのサウンドを圧倒せずに包み込み、そして、去っていく。一方、モツクーナスは、燃えだしそうで悲しげな、まるで熾火のような音色を放ち、巧みに素早く寄せては返してゆく。モツクーナスは才能のある若いプレイヤーであり、自分自身のアイデンティティを失うことなくジャズの歴史を取り込んでいる。時にはアルバート・アイラー Albert Aylerの揺らめきや、デイヴィッド S.ウェア David S. Wareの不屈の魂や、ジョン・コルトレーン John Coltraneの大胆な模索を聴き取ることができるだろう。しかし、それはあくまで彼のやり方で提示されるのだ。
 |
 |
 |
| Liudas Mockunas, photo by Vytautas Suslavičius | William Hooker and Liudas Mockunas, photo by Vytautas Suslavičius | 『Live at Vilnius Jazz Festival』, artwork by Neringa Žukauskaitė |
ザ・ゲイト The Gate
チューバ奏者ダン・ペック Dan Peckとパーカッション奏者ブライアン・オズボーン Brian Osborneが率いるザ・ゲイト The Gateによる盤『Stench』(Heat Retention, 2014)も面白い。アヴァン・メタル、ノイズ、フリージャズの要素を絞り出すパフォーマンスである。ふたりのベース奏者トム・ブランカート Tom Blancarteとティム・ダール Tim Dahlは、この10年間、NY即興音楽の最先端を走ってきた。規格外のトランぺッターであるネイト・ウーリー Nate Wooleyは、ここでは、彼の『Seven Storey Mountain』シリーズに似た役割を担っている。ベースふたりが猛スピードで演奏し、ペックとウーリーとが幅広に素晴らしいやり取りを見せ、そして、オズボーンが無定形の荒々しさと肌触りを提示するという、騒乱である。音楽が小さな音にまでメルトダウンしてきても、なお刺激的で駆動力を持っている。『Stench』は、今世紀のはじめのブルックリンにおいて、あまり注目されぬところから胎動した音楽であり、ノイズ〜アヴァン・メタル〜フリージャズの邂逅が結実した素晴らしい代物である。
 |
 |
 |
| The Gate, photo by Steve Singer | The Gate, L to R: Tom Blancarte, Dan Peck and Brian Osborne, photo by Steve Singer | 『Stench』, artwork by Levi Seeldraeyers |
ウィリアム・フッカー・トリオ William Hooker Trio
ライヴ・シーンに目を向けてみよう。テナーサックス奏者ジェームス・ブランドン・ルイス James Brandon Lewisとベース奏者アダム・レーン Adam Laneを擁するウィリアム・フッカー・トリオ William Hooker Trioは、10月3日、東ウィリアムスバーグのFirehouse Spaceにおいて、見事なパフォーマンスを繰り広げた。客演したダンサーのジナー・パーカー Jinah Parkerは、ミュージシャンたちと同様に、素晴らしい即興の踊りを披露した。彼女はミュージシャンたちの前にまろび出て、上半身の動きによる表現が、観客の心をわし掴みにした。トリオのメンバーは、彼女の動きに合わせてソロを取った。なかでもフッカーのドラミングがもっとも良い反応をみせた。ブルックリンには、即興音楽とフリー・フォームのダンスとのミクスチャーの歴史がある。この日のパフォーマンスは、ふたつのアート・フォームが相互作用により凄い効果をあげうることを、改めて示すものだった。
 |
 |
| William Hooker | William Hooker |
ネイト・ウーリー Nate Wooley
10月には、ネイト・ウーリー Nate Wooleyがいくつもの素晴らしいパフォーマンスをみせた。10月10日には、New Revolution Artsにおいて親しみやすいソロ・アコースティックでの演奏を行い、己をさらけ出した。10月20-25日には、Stoneでのレジデンシーとして、ピアニストのマシュー・シップ Matthew Shipp、多楽器奏者ジョー・マクフィー Joe McPhee、ドラマーのジェラルド・クリーヴァー Gerald Cleaverやポール・リットン Paul Lytton、さらにはヴァイオリニストのC・スペンサー・イー C. Spencer Yeh、パーカッション奏者ライアン・ソーヤー Ryan Sawyer、クラリネット奏者ジェレマイア・サイマーマン Jeremiah Cymermanといった若い実験的な面々に至るまで、様々なミュージシャンと共演した。この多彩さこそ、ネイト・ウーリーが当代きっての偉大な幻視者であることを示すものなのである。
 |
| Nate Wooley, photo by Ziga Koritnik |
以上がニューヨーク・シーンの最新動向である。
シスコ・ブラッドリー 2015年10月31日
(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)
シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley
ブルックリンのプラット・インスティテュートで教鞭(文化史)をとる傍ら、2013年にウェブサイト「Jazz Right Now」を立ち上げた。同サイトには、現在までに30以上のアーティストのバイオグラフィー、ディスコグラフィー、200以上のバンドのプロフィール、500以上のライヴのデータベースを備える。ブルックリン・シーンの興隆についての書籍を執筆中。http://jazzrightnow.com/
齊藤 聡(さいとうあきら)
環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong
photos by 吉田野乃子 Nonoko Yoshida, except * by Jesse Wakeman
日が暮れると一気に気温が下がるNY、冬がやってきました。
11月は自分のストーン・レジデンシーがあり、いろいろなプロジェクトで6夜連続のライヴを行いました。無事に終了してほっとしております。見に来ていただいた方々、応援してくださったみなさん、どうもありがとうございました。
私事ですが、11月いっぱいでNYを離れ、実家のある北海道に帰ることにいたしました。18歳で単身渡米してから、たくさんの人に支えられての、約9年半のNY生活、とんでもない(とても良い意味で!)体験をたくさんさせていただきました。お世話になった方々に心から感謝します。
v
今月見た、とっても素敵なライヴをふたつご紹介いたします。
<宇宙で一番好きなバンド>
■11月3日(火)エレクトリック・マサダ@ヴィレッジ・ヴァンガード
John Zorn (sax) Marc Ribot (guitar) Jamie Saft (keyboards) Ikue Mori (electronics) Trevor Dunn (bass) Cyro Baptista (percussion) Kenny Wollesen, Joey Baron (drums)
ジャズライヴハウスの老舗、ヴィレッジ・ヴァンガードに、数年前にジョン・ゾーン一族が(ようやく!)初登場し、ほぼ全公演ソールドアウトになるという快挙をぶち上げてから、ゾーン師匠は、何度かヴァンガードでレジデンシー・ウィークを行っています。
前回の日誌で紹介もいたしましたが、エレクトリック・マサダは、ゾーン師匠の楽曲集『マサダブック』からの曲を演奏するマサダ・プロジェクトのバンドの一つで、その中でも「メンバーが豪華すぎてなかなかライヴができない」という贅沢なバンドです。私は、このバンドが宇宙一大好きで、ヨーロッパまで追っかけに行ったこともあるほどなのですが、帰国前にまた見られて本当に幸せでした。
基本的にはジャズバンドのように、作曲されたテーマを序盤と終盤に演奏するマサダ・プロジェクトですが、エレクトリック・マサダのライヴで注目すべきことのひとつは、ゾーン氏による即興演奏の指揮です。ゾーン氏の有名なゲームピース『コブラ』を、簡易化したようなハンドキュー(身振り手振りで合図を行うこと)を利用し、即興演奏を指示、リード、まとめるのです。例えば、まず指を指された数人が演奏を開始、途中、また違う数人が指名され、ゾーン氏が手を振り下ろしたら、次のグループが演奏開始(最初に演奏していた数名は止める)というのが基本形。演奏中の指示では、手のひらをひっくり返す動作は「今やっている演奏と違うことをやる」、手のひらをゆらゆらと波打たせる動作は「リズムのないノイズ即興」、ビートをカウントする仕草は「速いスウィングで即興」、物を書くような仕草は「今やっている即興を覚えておく(あとで「あれをやれ」という指示がでます)」、人差し指をクイクイ曲げる動作は「この人のやっている演奏を真似る」などなど、いろいろな合図があります。このような指示によって、即興演奏がオーガナイズされ、ゾーン氏がその場で演奏家と共に作曲をしているようになるのです。長年ゾーン氏と一緒に演奏しているこのバンドの人たちは、この複雑な指示の中でも楽しげに、自由自在に、スリリングな演奏を繰り広げ、観客は、矢継ぎ早に展開される即興演奏に、まるで、超人アスリート達によるスポーツの試合を見ているかのような気分にされるのです。まさにゲーム感覚です。この日一番面白かったシーンは、モリ・イクエさんのラップトップ・エレクトロニクスのノイズを「真似しなさい」という指示が出て、他のメンバーが自分の楽器でそれに近い電子音を出そうとしていたところでした。
“超人アスリート”と比喩しましたが、このバンドのメンバーはみなさんまさに超人ミュージシャン。それぞれのソロでもマジックが起こりまくります。マーク・リボー、ジョーイ・バロン両氏の各ソロでは演奏途中で大歓声があがりました。ゾーン師匠も絶好調で、絶叫ノイズから特殊奏法による変な音まで、縦横無尽のソロは圧巻です。ですが、私が一番好きな瞬間は、わけのわからないノイズをめちゃくちゃに繰り出したあと、とても綺麗なメロディーを、遠くまで突き抜けるような音色で師匠が吹く時なのです。ゾーン氏がサックスを吹く機会が年々減っていっているので(作曲やプロデュースの方が多くなっています)また見られてよかったです。「やっぱり師匠はすごい…」と思わされました。
2セット目ではまさかの、なにやら複雑なリズムの新曲披露もあり(恐らくこの豪華メンバーでは、当日リハしかしていないはずです)メンバーのみなさんが若干ドキドキしながら演奏している様子を見てこちらもなんだか緊張しました。
エレクトリック・マサダはやはり、宇宙一かっこいいバンドです。このバンドが生で見られたことは私の音楽人生にとって最大の幸福です。
ドラムのジョーイとエレクトロニクスのイクエさんがいませんが、一番お気に入りの動画を参考にご紹介いたします。
https://www.youtube.com/watch?v=pJkmTdoYQYE
写真はヴァンガード外の看板、これって、いつもこうやって手書きでしたっけ。なんだか良いですよね。
<れまさんのLPリリース記念ライヴ>
学生ビザを取得し、長期でNYにいられるようにするためという、若干不純な動機で通い、なんとか卒業できた、ハーレムにあるNY市立大学シティカレッジ校ですが、そこで、素敵なピアニストのお姉さん、蓮見令麻(はすみれま)さんに出会えたことは幸運でした。在学中はバリバリとビバップを演奏されていたれまさんは、卒業されてからNYの即興シーンのミュージシャンとたくさん共演され、ジャズを越えた、ご自身の言語を確立されています。
近くに住んでいると変に油断(?)してしまい、数ヶ月前にれまさんにお会いした時には実に2,3年振りの再会になってしまったのですが、私のストーンのライヴに来てくださったりと、また最後にNYで交流ができたことを大変嬉しく思っています。そんな、大好きなれまさんのLPリリースライヴに行ってまいりました。
■11月20日(金)UTAZATA@iBeam, Brooklyn Rema Hasumi(piano/voice) Todd Neufeld (guitar) Thomas Morgan (bass) Billy Mintz (drums) Ben Gerstein (trombone) Sergio Krakowski (pandeiro)
即興演奏と楽曲の境目が見えないようなれまさんの音楽は、まるで水が流れるようです。ガツガツとリズムを刻んでいくのではなく、詩を読むように、歌うように、紙の上に筆で滑らかな線を描くように流れるのです。普段、個人的に、禅のスピリットに基づいて演奏されるような、ビートを極力避けるような即興を聞く時「なんだかダラダラしていて飽きてしまうなぁ…」ということもあるのですが、れまさんのこのバンドは、大きく緩やかに流れていくにも関わらず、常に緊張感とスピード感に溢れています。前へ前へと進む、強靭で俊敏なフレーズが、そこかしこにアクセントのようにちりばめられ、それが本流と交ざり、大きな河になり、渦巻いて流れていくようなのです。メンバーそれぞれの情熱的なパフォーマンスはとてもエネルギーがあり、それをまとめあげていくれまさんの楽曲は素晴らしかったです。途中で不意に聞こえてきたれまさんのボーカルにもうっとりしてしまいました。穏やかな優しさの中にも力強い意志と主張が聞こえる、とてもれまさんらしい素敵なライヴでした。今後、れまさんは、NYのライヴレポートもこちらに寄稿してくださるようなので、読者として楽しみにしています。
 |
 |
 |
<最後のご挨拶>
完全帰国にあたり、このNY日誌も今回が最後になります。短い期間ではありましたが、書かせていただき楽しかったです。寄稿にあたりお世話になった剛田武さん、齊藤聡さん、本当にありがとうございました。つたない文章でしたが、NYでの楽しい音楽体験が、少しでもみなさまにお伝えできていれば幸いです。12月からは北海道を拠点に活動をして参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。読んでいただき、本当にどうもありがとうございました!
吉田野乃子@The Stone, NY
2015年11月10日&12日
http://www.jazztokyo.com/live_report/report863.html
蓮見令麻(はすみれま)
福岡県久留米市出身、ニューヨーク在住のピアニスト、ボーカリスト、即興演奏家。http://www.remahasumi.com/japanese/
Interviewed and translated by 齊藤聡 (Akira Saito)
http://www.jazztokyo.com/interview/interview144.html
齊藤 聡(さいとうあきら)
環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。
ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.