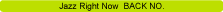Jazz Right Now - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
・トランスワールド・コネクション 剛田 武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報 (シスコ・ブラッドリー)
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 ― アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
前回のコラムでニューヨークを訪れる異邦人について書いたが、当然ながらニューヨークの音楽家が異国を訪れて、現地の音楽シーンで表現活動を行う例も多数ある。
50年代末に勃発したジャズの新しい波に同調する演奏家は、その志の高さに反して、本国アメリカでは経済的バックアップが得られず、不遇な境遇にある場合が多かったが、現代音楽の伝統があり先進的なジャズへの理解があるヨーロッパには、そういったアメリカのミュージシャンを受け入れる土壌があり、マーケットがあった。
オーネット・コールマン、エリック・ドルフィ、アルバート・アイラー、ドン・チェリーなどフリージャズのオリジネーターの多くがその活動の中で何度もヨーロッパを訪れ、現地のミュージシャンとの交流を通して、肥沃な音楽畑を耕した。現地のシーンに与えた影響が多大なものであったことは、例えばエリック・ドルフィの晩年のアルバム『ラスト・デイト』で共演したオランダのミシャ・メンゲルベルグとハン・ベニンクが、1967年にInstant Composers Pool(ICP)を創設し、現在に至るまでヨーロッパ即興音楽の中心的存在として活動することでも明らかだ。また、パートナーのモキ・チェリーの故郷のスウェーデンに移住し、世界中にオーガニック・ミュージックの種を蒔いたドン・チェリーのような存在もいる。
ヨーロッパだけではなく日本を耕したミュージシャンも少なからず存在する。ジョン・ゾーンは90年代に暫く日本に滞在し、ジャズや即興音楽のみならずパンクやノイズや歌謡曲のミュージシャンと交歓し、日本の音楽シーンに大きな影響を与えた。ゾーンは現在もTZADIKレーベルから日本の先鋭的音楽作品をリリースし世界に紹介している。他にも活動の場をNYから日本へ移し、今では日本の地下音楽シーンに欠かせない存在であるサム・ベネットやジム・オルークなども思い浮かぶ。
今号のFIVE by FIVEで紹介したNYのクリス・ピッツイオコスとドイツの演奏家による『Protean Reality』のように、インターネットを通して異国の表現者が出会い素晴らしい作品を生み出す例もある。テクノロジーの進歩で世界が狭くなったと言われるが、そんな時代だからこそ生まれる新たな<トランスワールド・コネクション>に音楽表現の未来があるのは確かである。
関連リンク
FIVE by FIVE #1278『Protean Reality (Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz) / Protean Reality』
剛田 武 Takeshi Goda
1962年千葉県船橋市生まれ。東京大学文学部卒。レコード会社勤務の傍ら、「地下ブロガー」として活動する。80年代東京地下音楽に関する書籍を執筆中。
ブログ「A Challenge To Fate」 http://blog.goo.ne.jp/googoogoo2005_01
ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
translated by 齊藤聡 (Akira Saito)
スウィート・バンディットリー Sweet Banditry
スウィート・バンディットリー Sweet Banditryは、ルイーズ D.E.ジェンセン Louise D.E. Jensenをリーダーとして、ギタリストのブランドン・シーブルック Brandon Seabrook、ベーシストのトム・ブランカート Tom Blancarte、ドラマーのケヴィン・シェイ Kevin Sheaからなるカルテットである。彼らのデビュー盤『Farvefisen Blomstrer』(Marsken)は2014年に出されたのだが、間違いなく、もっと注目されていい作品だった。ここでジェンセンは、詩の引用(ジェンセンの母語であるデンマーク語で)から、激烈で忘れ難いヴォーカルや叫びまでを、また、焼け焦げるようなサックスとフルートのソロを披露する。シーブルックはニューヨークでもっとも過小評価されているギタリストのひとりだが、この煮立った大釜のようなサウンドに、1990年代的とも言える美学とパンクとを加味している。ブランカートとシェイとが寄せては返すダークエネルギー波を創出し、その大騒乱があってこそ、ジェンセンとシーブルックとが浮かび上がって足場を固め、絡み合い、閃光を放つのである。少々へヴィーな音楽ではあるが、ときに優しさや郷愁さえも漂っていて、楽しさが迫りくるとき、メロディーを大波として動かすのである。ジェンセンはエレクトロニクスも使い、それにより広がる情感がリスナーに訴えかける。スウィート・バンディットリーは、騒々しく苛烈なフリージャズとしても、またアヴァン・ロックとしても、魅力あるバンドだ。
ダニエル・レヴィン Daniel Levin
チェロ奏者ダニエル・レヴィンのカルテットが、6枚目(Clean Feedレーベルからは4枚目)となるアルバム『Friction』を出した。またしても、同世代の中で頭一つ抜けた存在であるトランぺッターのネイト・ウーリー Nate Wooleyと、ニューヨーク・シーンの屋台骨たるヴィブラフォン奏者のマット・モラン Matt Moranとをフィーチャーしている作品だ。レヴィンはさらに、ポスト・バップにおいてもアヴァンギャルド・ジャズにおいても影響力のあるスウェーデンのベーシスト、トビョルン・ゼッターバーグTorbjorn Zetterbergを起用した。その結果、8曲にわたり、揺れ動き、ときにミニマリストの探求のようでもあるサウンドが出来上がった。音楽の中心には、反響するような静寂があり、鍛錬されたミュージシャンたちがそこに生命を吹き込んでいる。モランは巧みであり、デュエットの間も相手を威圧することがない(ちょっとでも間違えたらバランスを崩してしまうものだ)。偶然的感覚がアルバム全体を覆っており、それがリスナーを励起する。ウーリーのトランペットは軽く、印象的であり、ミュートをかけて透き通るような美しいソロを取る。ゼッターバーグは、メロディー、ソロ、アンサンブルを通じて底流を創り出し、緊張感を保つ。この魅惑的なグループにあって、レヴィンはこれまでにないほど微妙な演奏を行い、黒や藍色のキャンバスに丹念にサウンドを塗り重ね、ダークフィニッシュに仕上げているのである。このアルバムはミュージシャンたちの長い修練の賜物たる名人芸であり、2015年のベストの1枚だと言うことができるだろう。
 |
 |
| L to R: Daniel Levin, Nate Wooley, Matt Moran and Torbjorn Zetterberg, photo by Joachim Ceulemans (Levin) and Peter Gannushkin (the others) | 『Friction』 |
2015年のベスト・アルバム
1. マタナ・ロバーツ Matana Roberts『Coin Coin - Chapter Three: River Run Thee』 (Constellation)
http://diskunion.net/portal/ct/detail/XATW-00135015
2. ティム・バーン(スネークオイル) Tim Berne’s Snakeoil『You’ve Been Watching Me』 (ECM)
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/007.html#01
3. イングリッド・ラウブロック(アンチ・ハウス) Ingrid Laubrock’s Anti-House 『Roulette of the Cradle』 (Intakt)
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/006.html#02
4. クリス・ピッツイオコス Chris Pitsiokos『Gordion Twine』 (New Atlantis)
http://www.jazztokyo.com/five/five1224.html
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/005.html#02
5. ミシェル・アシラー&アイヴィン・オプスヴィーク Michelle Arcila & Eivind Opsvik『A Thousand Ancestors』(Loyal Label)
6. トマ・フジワラ(ザ・フック・アップ) Tomas Fujiwara & the Hook Up『After All Is Said』(482 Music)
http://www.jazztokyo.com/five/five1203.html
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/003.html#02
7. ダニエル・レヴィン Daniel Levin『Friction』(Clean Feed)
本コラム
8. ベン・スタップ(ザ・ゾジモス) Ben Stapp & the Zozimos『Myrrha’s Red Book, Acts 1 & 2』(Evolver)
9. ミッコ・イナネン、ウィリアム・パーカー、アンドリュー・シリル Mikko Innanen with William Parker & Andrew Cyrille『Song for a New Decade』(TUM)
http://www.jazztokyo.com/five/five1216.html
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/002.html#02
10. シークレット・キーパー Secret Keeper『Emerge』(Intakt)
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/002.html#02
2015年のベスト・ライヴ
1. トーマス・ボーグマン、マックス・ジョンソン、ウィリ・ケラーズ Thomas Borgmann Trio with Max Johnson, Willi Kellers @New York Tenor Saxophone Festival / Ibeam、1月31日
2. チェス・スミス、クレイグ・テイボーン、マット・マネリ Ches Smith/Craig Taborn/Mat Maneri @New Revolution Arts、1月16日
3. ネイト・ウーリー Nate Wooley(ケネス・ガブロ Kenneth Gaburoに捧げたソロ)(For Kenneth Gaburo) @Wild Project、1月19日
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/001.html#02
4. ウィリアム・フッカー、ジェームス・ブランドン・ルイス、アダム・レーン(ゲスト ジナー・パーカー) William Hooker Trio with James Brandon Lewis, Adam Lane, and guest Jinah Parker @Firehouse Space、10月3日
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/009.html#02
5. VAX(パトリック・ブレイナー、リズ・コサック、デヴィン・グレイ) VAX: Patrick Breiner, Liz Kosack, Devin Gray @New Revolution Arts、2月27日
6. タニヤ・カルマノーヴィッチ&マット・マネリ(デュオ) Tanya Kalmanovitch-Mat Maneri Duo @JACK、7月26日
7. トマ・フジワラ(フック・アップ)w/ ジョナサン・フィンレイソン、ブライアン・セトルズ、メアリー・ハルヴァーソン、マイケル・フォルマネク Tomas Fujiwara & the Hook Up with Jonathan Finlayson, Brian Settles, Mary Halvorson, Michael Formanek @Cornelia Street Café、4月18日
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/003.html#02
8. シークレット・キーパー(メアリー・ハルヴァーソン&ステファン・クランプ) Secret Keeper: Mary Halvorson, Stephan Crump @Cornelia Street Café、4月17日
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/003.html#02
9. シェイナ・ダルバーガー(ソロ) Shayna Dulberger Solo @Kings County Saloon、6月3日
10. アンダーマイン・トリオ(クリス・ピッツイオコス、ブランドン・ロペス、タイショーン・ソーリー) Undermine Trio: Chris Pitsiokos, Brandon Lopez, Tyshawn Sorey @JACK、7月20日
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/006.html#02
以上がニューヨーク・シーンの最新動向である。
シスコ・ブラッドリー 2015年12月25日
(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)
シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley
ブルックリンのプラット・インスティテュートで教鞭(文化史)をとる傍ら、2013年にウェブサイト「Jazz Right Now」を立ち上げた。同サイトには、現在までに30以上のアーティストのバイオグラフィー、ディスコグラフィー、200以上のバンドのプロフィール、500以上のライヴのデータベースを備える。ブルックリン・シーンの興隆についての書籍を執筆中。http://jazzrightnow.com/
齊藤 聡(さいとうあきら)
環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 ― アナイス・マヴィエル
アナイス・マヴィエルは、数年前にニューヨーク・アンダーグラウンドそして特にブルックリンの即興シーンに彗星のごとく現れた。彼女はハイチ系のフランス人で、AACMに傾倒し、その伝統を引き継ぐ意志を持つ若手の音楽家のひとりだ。
マヴィエルの主な「楽器」はヴォイスだが、同時に彼女はアフリカの弦楽器ンゴニや、ブラジルのサンバに用いられるスルドという打楽器などの優れた奏者でもある。
アナイス・マヴィエルのライヴ
マヴィエルの演奏を見るのは今回で3度目だ。1度目は、ウィリアム・パーカーのマーチン・ルーサー・キング・プロジェクトでオーケストラの中のヴォーカリストのひとりとして、2度目は65 Fen という小さな箱での即興パフォーマンスで、彼女の演奏を見て感銘を受けたのだけれど、3度目のこのライヴでも彼女は更に圧倒的な演奏を聴かせてくれた。今回のライヴはハイチ料理を出すブルックリンのLa Cayeというレストランで、バーの横に作られた小さなステージにマヴィエル(voice, n'goni, surdo)、レイサン・ハーディー(reeds)、ジョン・マーチソン(gimbri, flute)、そしてAACMのメンバーであるシカゴ在住のサクソフォニスト、アーネスト・カビア・ドーキンス(reeds)が並んだ。
マーチソンの奏でる静かなゲンブリの音色で最初の曲がはじまる。エチオピアのフォーク・ソングらしく、マヴィエルがスルドで叩くリズムに合わせて、あのエチオピア独特のブルージーな音階をハーディーとドーキンスのふたりがサックスで辿っていく。そこにマヴィエルが声を重ねていくのだが、声色も美しければ、その即興における声のコントロールも並外れている。その後も、ハイチやジンバブエのフォーク・ソングなどが演奏されていったのだが、このパフォーマンスには、ただの「ワールド・ミュージック」として片付けることのできないインパクトがあった。それはきっと、メンバー全員が、伝統音楽が滅多に超えることのないライン(特有の音階にとどまる演奏=伝統を守ること)を超えて即興しているからだろうと思う。それに加え、マヴィエルのヴォイスの即興というのは、かなりの割合を非西洋的な音楽的アプローチが占めている。あらゆる種類の民族的音階を自由に行き来しながら、絶妙なさじ加減で彼女の声が「外側」に飛び出す瞬間に、オーディエンスはたまらないスリルを感じることができるのだ。
レイサン・ハーディーとアーネスト・ドーキンスはまったく違うスタイルのサックスを吹くので、その演奏のコントラストも十分に楽しむことができた。また、特筆すべきは楽器編成の面白さだ。まず、ゲンブリという北アフリカの弦楽器でグナワ音楽の重要な役割を担う。それから、マヴィエルの弾くンゴニという楽器は西アフリカのもので、とても柔らかで素敵な音色を持つ上に、見た目もとても美しい。
ブラジルの打楽器スルドに関していえば、この楽器はサンバを演奏する以外に使われることは滅多にないそうだが、マヴィエルの演奏スタイルには非常に良くマッチしている。ンゴニもスルドもそうだが、楽器を演奏しながらあれだけの即興を声でできるヴォーカリストというのはなかなかいないのではないだろうか。
 |
 |
| L to R: Lathan Hardy, Anais Maviel, John Murchison | L to R: Ernest Khabeer Dawkins, Lathan Hardy |
太陽と月
現代のニューヨーク・ジャズシーンにおけるヴォーカリスト達の立ち位置には興味深いものがある。楽器奏者達が素晴らしいテクニックを持って次から次へと新しい音楽を開拓している中で、ヴォイスの音楽における必要性を提示していくためには、楽器奏者と同等の技術以上に、比類のないオリジナリティと即興能力が求められる。そのような環境の中で、スタンダードの演奏やバップの伝統から自身を解放するという試みをそれぞれがしてきた結果、ヴォーカリスト達の中に奥行きのある多様性が生まれてきたのではないかと思う。エラ・フィッツジェラルドやサラ・ヴォーンの様な歌唱の伝統は、ある意味で途切れてしまったかもしれない。それは、フィッツジェラルドやヴォーンを生み出した社会的背景の消失、そして現代社会における音楽のリスナー達の求めるもの、または音楽家達自身の表現手法の変遷、様々なことに帰すると思う。現代のニューヨークにおけるヴォーカリストといえば、エスペランサ・スポルディング、グレッチェン・パーラトやベッカ・スティーヴンスなどがよく知られているかと思うが、彼女達の様なシンガーが太陽であるとすれば、その裏側に月のようにジェン・シュー、ジュディス・バークソン、あるいはアナイス・マヴィエルといったヴォーカリスト達が存在している。前者がよりポップなアプローチを持ったスタイル、よってソング・ライティングを基盤とするのに対し、後者はM-Base、ECM、またはAACMの潮流を受け継ぎ、即興演奏を主体としている。
新たなブルースを求めて
魅力あるヴォーカリストの歌には、ブルースがある。アメリカにおける黒人の歴史と経験に基づいた「ブルース」の理解が一般的にはジャズのリスナー達に広く受け入れられ、またそういった意味でのブルースは、ビリー・ホリデイやアビー・リンカーンをはじめとするいわゆるジャズ・シンガー達の歌を魅力的なものにしてきた。
しかし、ブルース的ロマンチシズムが芸術の基盤からほぼ失われてしまった現代の社会(少なくとも私にはそういう風に見える)においては唄い手達は何を拠り所に表現できるのだろうか?
そのような潜在的な疑問を持った幾人かの勇気あるヴォーカリスト達が、新しい形の音楽を作り始めている。彼女達は、表現の土壌となる広義のブルースを求めて、世界中の音楽を探し廻っている。その中から、自分の内側に存在するパズルの断片とぴったり合うピースを持ち帰り、ニューヨークで新しい音楽を形作るのだ。
ジェン・シューとアナイス・マヴィエル
スティーブ・コールマンとの共演で知られるジェン・シューは長年の間、ニューヨークとインドネシアや韓国などのアジア各国を行き来してきた。アジアではそれぞれの国の伝統音楽家達に教えを受け、共演し、その伝統音楽から得たものをジャズというキャンバスに描きだす。昨年リリースされた『Sounds and Cries of the World』(2015, Pi Recordings)ではトーマス・モーガン、ダン・ワイス、マット・マネリ、アンブローズ・アキンムシーレなどのニューヨーク・シーンを牽引する奏者達と共に素晴らしい演奏をし、ニューヨーク・タイムスの2015年のベスト・アルバムのひとつに選ばれている。彼女についてはまたゆっくり別の機会に書こうと思うが、アナイス・マヴィエルの話をするためには、まずニューヨークにおけるジェン・シューの存在の大きさについて述べておかなければならないと思った。
とにもかくにも、前衛ジャズにおけるヴォーカリストの可能性というものを、ジェン・シューが開拓したことによって、声を使ったフリー・インプロヴィゼーションをするアーティストが、シーンにおいて生き生きとしてきたように思う。
類のない表現と存在感
前置きが長くなったが、その流れを今ものすごいパワーで後押ししているのがアナイス・マヴィエルなのだ。彼女と直接話をした時に聞いたことだけれど、マヴィエルの表現の根本にあるのはシャーマニックな表現者としてのスタンスであり、実際に彼女はジンバブエで儀式音楽を研究したという経歴も持っている。それに加えて、インタヴューで彼女自身も話しているように、クレオール文化からの影響も受けている。マヴィエルのデビュー作『hOULe』(Gold Bolus Recordings, 2015)は、ソロでのヴォイスとスルド、シンギング・ボウルの演奏というシンプルな内容になっており、すべてが即興演奏である。一聴するとこの音楽はやはり、どこか異国の儀式音楽のように聞こえる。多くの場合、儀式音楽を聴く機会があるとすれば、それは集団での演奏、そしてフィールド・レコーディングで録音されたものがほとんどである。このアルバムは、そのようなシャーマニックな音楽をマヴィエルがひとりで演奏しているということ、そして現代のニューヨークのスタジオ録音でプロデュースされているということが非常に面白いと思う。 今回のデビュー作はソロで彼女の持つポテンシャルをしっかりと聞かせてくれたマヴィエルが、これから先どのようなミュージシャン達とどのような共演作を生み出していくのか、とても楽しみである。
インタヴュー
以下はJazz Right Nowでおなじみのシスコ・ブラッドリー氏のアナイス・マヴィエルへのインタヴュー記事だ。ウィリアム・パーカーとの共演、そして社会における芸術の役割に関する考えなど、非常に読み応えのある記事となっている。
シスコ・ブラッドリー:あなたにとってクリエイティヴな音楽との出会いはどのようなものでしたか?
アナイス・マヴィエル:音楽をはじめた頃は、自分自身をうまく表現したりフリーな演奏をしたりするためには長い間の探求が必要になることを感じていました。クリエイティヴな音楽との出会いは、初めはリスナーとしてでした。『Live At The Newport Jazz Festival』(1957, Verve) の「Airmail Special」という曲でのエラ・フィッツジェラルドのパラダイスの様に自由な即興、そしてウィリアム・パーカーの『Double Sunrise Over Neptune』(2008, AUM Fidelity)は毎日取り憑かれたように聞いたものです。
もちろん、自分のライヴでの演奏における超越的感覚との出会いもありました。
音楽学校でジャズの勉強をする中で、次第に息の詰まる様な気持ちになってきた私は、美学についての研究をするようになりました。研究の内容は、「音楽とユートピア」というもので、私の目標は、現代の(「植民地時代以後」とは言い難い)クレオール社会において、クリエイティヴな音楽がどれほど重要で核心的なものであるかを証明することでした。世界との関わりを反映する音楽を創る、という未だに自分でも完全に成し遂げてはいないことを、なんとか明瞭に表現することはできないかと模索しました。
そして幾度かのフリー・インプロヴィゼーションへの内気な試みを経て、私はニコル・ミッチェルと出会ったのです。(私はシカゴに行きAACMに教えを受けたいと考えていました。)ニコルはモンマルトルの私の小さな部屋に来てくれて、二時間ほど一緒に演奏した後に、「あなたにはすでにあなた自身の音があるわ。」と言ってくれました。それは素敵な助言でしたし、ニコルの様な素晴らしい演奏家と音の空間を共有できたことも幸せに思いました。楽器を通した際限のない可能性を探索し続けるようにと彼女は応援してくれました。
ブラッドリー:ニューヨークで共演したアーティストやプロジェクトの中で最も深い影響を受けたものは何ですか?そしてそれはどのような影響でしたか?
マヴィエル:ここに来て気づいたこと重要なことがひとつあります。それは、人間の深い価値を共有し、理解し、祝福し、さらに活力を与えるための「聖なる領域」を守る責任が私達音楽家にはあるということです。このことはあらゆる人々の下で得た気づきですが、その中に詩人で音楽家であるウィリアム・パーカーや、(人種または性的な)マイノリティのためのヒーラー・アーティスト団体、Harriet’s Apothecaryなどがあげられます。
ブラッドリー:ウィリアム・パーカーの作品における「治癒力」のどのような点に最もインスピレーションや超越的感覚を覚えますか?
マヴィエル:ウィリアムはとても神聖な領域で活動しているように感じます。彼は共演するすべての音楽家達に「音色の世界」というリアリティーを見せてくれるのです。ウィリアムの自宅を初めて訪れた時に彼が最初に話してくれたことは、「治癒」についてでした。私はそれを次のように理解しました。私達音楽家は、人間の非常に繊細な部分の事柄と向き合っています。音楽は、いわば人間ひとりひとりがどのような状態にあるか、ということに多大な影響力を及ぼします。そしてその音楽の持つ多大な影響力を、人間の持つ恐れや絶望を治癒し、またバランスを取る方法として使うという責任が私達音楽家にはあります。
後から気づいたことですが、人のために音を創るという芸術的営みにはある種の倫理が付随します。
音の持つパワーは、私達の脳の感情中枢に直接働きかけ、波動を通して身体的な部分にも影響するために、それによって人間は極端に破壊的にも、創造的にもなり得るのです。
ウィリアムとの音楽における共同作業は、音楽家として最も素晴らしい経験となりました。
音楽を通して超越的な経験をするほどに、私は謙虚な気持ちになっていきました。
私という媒体を通して、何かとても重要なことが成し遂げられようとしている。私という存在を超越して為されるその事柄のために、「美」の裏側で自分自身を消すことも厭いません。
ブラッドリー:あなたは、パフォーマーであり、アカデミックでもあります。クリエイティヴな音楽が、どのような形で社会の変革のためのユートピア的な政治活動となり得ると考えますか?
マヴィエル: 素晴らしい芸術とは、社会にとって核心的な役割を持つものです。それ故に私は様々な伝統音楽に興味を持っています。伝統音楽には、集団における儀式的な芸術活動の経験を通して人々の生活を内側から変容させる力のある本質的な力があります。
「ユートピア」という言葉には、いまや退廃してしまった「政治」という言葉の代用にはならずとも、その言葉に疑問を投げかけるだけの破壊的役割があります。ユートピアという言葉を耳にする時、私達はいわゆる「不可能な」夢や希望について思い出します。ジャズとも深い関わりのあるクレオール文化を通して私が学んだことは、芸術とは「不可能」を乗り越えられる限られた方法のひとつであり、「自由」という概念を許さない意識のなかで「自由」の輪郭を描き出していく方法のひとつであるということです。ですから、ユートピア的芸術の系譜は、冷淡なポストモダン的政治活動や美学に問いかけ、働きかけていくべきです。ほんの少しだけ感覚を研ぎすませ、意識を変えるだけで、我々は自由を手にすることができるのですから。
ブラッドリー:音楽を創造する過程の中であなたが経験した「自由」の感覚について教えてもらえますか?
マヴィエル:音楽を演奏する中に自由を見出そうとすると、次第に自分の中にある音楽の欠片達をてなずけることができるようになってきます。その欠片達は思うほどに外の世界とかけはなれてはいないし、荒ぶれてもいないということに気づくのです。自由とは、静寂そのものかもしれない。もしくは、掘り起こすまでもなく、すぐ足元に落ちているかもしれない。自由とは水の様に流れ、私が向こう岸に流れる自由を探すことをやめた途端につかまえることができるものなのかもしれない。毎日の生活において、情熱や信心を捧げる他のどのような活動がそうであるように、音楽は解放のための教師であり、私は学ぶために自分自身をさらけ出す時に「自由」を感じます。そしてそれは、危険なほどに美しく、ひとからひとへと伝わっていくのです。
シスコ・ブラッドリーによるアナイス・マヴィエルへのインタヴューより抜粋
訳:蓮見令麻
Jazz Right Now October 5th, 2015
http://jazzrightnow.com/2015/10/05/artist-feature-vocalist-anais-maviel/
(インタヴューのオリジナル記事へのリンク)
 |
| Anaïs Maviel『hOULe』(Gold Bolus Recordings, 2015) |
artwork by My Lê Chabert
http://www.goldbolus.com/houle.html (Gold Bolus Recordings)
Anaïs Maviel Solo
https://www.youtube.com/watch?v=eDBOh4myNx4
Jen Shyu & Jade Tongue - Sounds and Cries of the World : MOXA
https://www.youtube.com/watch?v=orJ5gu7bvXQ
蓮見令麻(はすみれま)
福岡県久留米市出身、ニューヨーク在住のピアニスト、ボーカリスト、即興演奏家。http://www.remahasumi.com/japanese/
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.