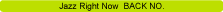Jazz Right Now - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda & 吉田野乃子 Nonoko Yoshida
・ライヴの魅力(剛田武)
・連載第3回: ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報(シスコ・ブラッドリー)
・新連載:よしだののこのNY日誌 (吉田野乃子)
・ウイリアム・パーカー・インタビュー <前編>(シスコ・ブラッドリー)
音楽の魅力は生演奏にある、というのが筆者の持論である。勿論CDやレコード、DVDやビデオなどの録音・録画物は『作品』として重要な意義があることに異論はないし、私自身重症のレコード・コレクターであることは否定しない。それにも関わらず、ライヴ現場で出会うその場限りのパフォーマンスの魔力は「My Life Is Live(我が人生はライヴにあり)」という英文法無視の座右の銘を、筆者に呟かせるのである。とりわけ即興音楽に於いては、一回一回が一期一会、もしくは一か八かの瞬間芸に近い真剣勝負であり、現場に立ち会うことこそ、本当のスリルを肌で体感出来る理想的な鑑賞法だと思っている。
Jazz Right Now第2回で『ニューヨーク、冬の終わりのライヴ日記(http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/002.html#03)』を寄稿いただいた齋藤聡氏とは、氏のブログ記事を通して出会った。筆者がネット動画と音源だけで妄想していたNY即興シーンの現場を実際に経験した氏の文章には、リアルでヴィヴィッドな音楽体験が息づいており、プロ顔負けの素晴らしい写真と併せて、まさに「今ここにあるジャズ(Jazz Right Now)」の活気と興奮が、読者の皆さんにも伝わったに違いない。
第3回の今回は、Jazz Right Now主宰のシスコ・ブラッドリー氏によるふたつの丁寧なライヴ・レポートに加え、ニューヨーク在住のサックス奏者の吉田野乃子さんに日記風のレポートを執筆していただいた。実際にシーンを形成するクリエイターならではの視点や思想は、たいへんユニークで興味深く、生身の音楽表現の鑑賞と理解への大きな助けになるに違いない。吉田さんには今後も連載で寄稿をお願いしているので、楽しみにしていていただきたい。
ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
translated by 剛田武 (Takeshi Goda)
今月最大のイベントは、4月17,18日にコーネリア・ストリート・カフェで開催された2つの重要なレコード発売記念コンサートだった。第1夜に登場したのは、セカンド・アルバム『エマージ Emerge』(Intakt)をリリースしたメアリー・ハルヴァーソン Mary Halvorson(g)とステファン・クランプ Stephan Crump(b)によるデュオ、シークレット・キーパー Secret Keeper。第2夜は、サード・アルバム『アフター・オール・イズ・セッド After All Is Said』(482 Music)をリリースしたトマ・フジワラ&ザ・フック・アップ。メンバーは、リーダーのトマ・フジワラ Tomas Fujiwara(ds)、ジョナサン・フィンレイソン Jonathan Finlayson(tp)、ブライアン・セトゥルズ Brian Settles (ts)、メアリー・ハルヴァーソン(g)、マイケル・フォーマネック Michael Formanek (b)。
シークレット・キーパー Secret Keeper
2012年夏に結成して以来、シークレット・キーパーは目覚ましい進化を遂げてきた。二人はもともと数回のデュオ演奏のために出会い、たまたまそのセッションが録音されることになった。デュオとしての最初の一音を含むこの邂逅の様子は、デビュー・アルバム『スーパー・エイト Super Eight』に収録された。今回の2作目では、完全即興による前作から変わって、アーヴィン・バーリンの「What’ll I Do」に加え、それぞれが4曲ずつ楽曲を提供し、革新的な音楽ヴィジョンを提示すると同時に、両者の卓越した技術をいかんなく発揮している。
コンサートはアルバムのタイトル・ナンバー<Emerge>でスタート。冒頭から息もピッタリに、ギターとベースのサウンドが親密に織り重なりながら、音楽はゆっくりと進行する。ハルヴァーソンのギターは、クランプのベースが描く深淵の真ん中で、暖炉の火のように踊る。時に暗く予兆的に、時に純粋に、忍耐強いエネルギーを持って、二人はお互いのフレーズと音色を紡ぎだす。二人の演奏家の逞しく、しかし正直な音声は、まばらな音風景を高みへと導き、やがてゆっくり衰退していく。
<In Time You Yell>は、全編に亘るシャープなギターと、木霊のように共鳴したり、背景に隠れたりするベースとが、メロディアスな追いかけっこを展開する。<Disproportionate Endings>は、土台を形作るベースの上に、アンビエントなギターがメロウでエッジーなラインを滝のように浴びせる。二人の周りにサウンドの軌道を描き出す<Planets>から、そのまま<A Muddle of Hope>に進行する。クランプの正確なベースが生み出す茂みの中を、ハルヴァーソンがファンタスティックに駆け抜ける。1stセットは、冒頭の激しく鋭い演奏が天に上って絶頂に達すると、突然静寂に回帰する<Bridge Loss Sequence>で幕を閉じる。
2ndセットは<Turns to White Gold>で始まる。エネルギーを溜め込んだ辛抱強いインタープレイで始まり、突如炎のように燃え上がるこの曲は、両ミュージシャンの実力が最大限に発揮された、とりわけ印象的なナンバーである。1stアルバム収録の即興曲<Mirrors>から<What’ll I Do>に続き、お互いに美しく共鳴し補完し合いながら、浮遊感のあるデュエットを聴かせる。
<Nakata>は観客の現前に、激しく振動する地震のようなサウンドを閃かせる。再び1stアルバムからの<Toothsea>では、一転して瞑想するようにお互いを探り合い、来るべき騒乱のクライマックスに備える。アルバムのハイライトでもあるラスト・ナンバー<Erie>は、流れ落ちる滝のような音像と、深く切れ味のある弓弾きベースでスタートする。物憂いダークな共鳴は、演奏を堪能した観客を、夜の通りへ送り出すのに相応しい終曲だった。相互信頼が、二人のミュージシャンを、激しく鮮やかなスタイルの遥かな高みへ導く。『エマージ』はこのユニットに新たな方向性を与え、デュオとしての大きな飛躍を明らかにした。
Stephan Crump - Mary Halvorson "In Time You Yell" @ Cornelia Street Cafe 4-17-15
https://www.youtube.com/watch?v=fgg8kK5eKUA&feature=youtu.be
Stephan Crump - Mary Halvorson "Erie" @ Cornelia Street Cafe 4-17-15
https://www.youtube.com/watch?v=xJMDWKtBYmE&feature=youtu.be
Mary Halvorson Official Site
http://www.maryhalvorson.com/
Stephan Crump Official Site
http://stephancrump.com/
トマ・フジワラ&ザ・フック・アップ Tomas Fujiwara & The Hook-Up
『アフター・オール・イズ・セッド』は、現代最高のドラマーのひとりであり、近年印象的な作品を次々リリースしているトマ・フジワラが、第一級の演奏家を迎えて発表した、大胆な声明である。『アクションスピーク Actionspeak 』(2010)と『ジ・エアー・イズ・ディファレント The Air Is Different』(2012)に続く、トマ・フジワラ&ザ・フック・アップのサード・アルバムは、バンド・メンバーの強みを最大限に活かして、関連するテーマ---記憶と人間関係---の探求を、7つの興味深い楽曲で描き出した。ジョナサン・フィンレイソン(tp)は、自己のアイデアを鮮烈且つ正確に表現する新鮮なスタイルをもたらした。メアリー・ハルヴァーソンのクインテットとセプテットのメンバーでもあるフィンレイソンは、ハルヴァーソンと育んだ深い美的感覚を共有しており、トランペットとギターの豊かなコミュニケーションがアルバム全体を貫いている。ブライン・セトゥルズはトランペット奏者の完璧なカウンター(迎撃者)である。このテナーサックス奏者は他のメンバーの間を流れる水のように温かいトーンで、バンドに必要な結束性を与える。前作からの最もエキサイティングなバンドの変化は、達人ベーシスト、マイケル・フォーマネックをラインナップに加えたことだろう。彼はバンドに比類のないエネルギーと強固なサウンドをもたらし、アンサンブルを新たな高みへ押し上げた。
コーネリア・ストリート・カフェでのコンサートは、フジワラが捻くれた口調で“可能な結末”と呼ぶ<Lastly>で始まった。エネルギーが流れ出し、リーダーのフジワラの特徴的な演奏スタイルと作曲技能を提示する。ドラムとベースの安定した動きを核にして、ギターが音楽のキャンバスまたは創造的張力を閃光で切り裂き、ホーンが深い青、緑、紫色のサウンドスケープの上に黄色い線を交互に弾く。セトゥルズがくっきりした嘆くようなフルートを吹き始め、演奏を豊かな感情の発露へと導く。新たな始まりの終わりである。
続く<Boaster’s Roast(ほら吹きのロースト)>では、曲名に相応しく、バンドは自信満々に演奏する。ホーンが順番に前奏を奏でたあと、ハルヴァーソンの脈動するリズムに乗せて、ギター=ベース=ドラムのインタープレイが進行する。そしてベースとドラムが先導する複雑なパッセージに戻り、トランペット、ギター、テナーが足を踏みしめて先頭を競い合う。新作中で最も印象的な曲のひとつである。
1stセットのラスト・ナンバー<When>では、ハルヴァーソンがカート・コバーン(ニルヴァーナ)風のフレーズを弾いて、観客の中に混じる元X世代たちの全身に喜びのさざ波を起こす。しかし彼女はすぐに持ち前のねじれたフレーズを連発し、テーマへ戻る。バンド全員のエネルギッシュなアンサンブルに続き、トランペット・ソロに突入。フィンレイソンは空間を完璧に活かして、才能豊かに選んだ音列を強調し、水晶のように透明な音色で、ソロの最高の瞬間を吹き切った。
2ndアルバムからの「Lineage」で始まった2ndセットは、「The Hook Up」と「Folly Cove」で楽しげな時を過ごし、傑作の「The Comb」でエンディングを迎える。5人それぞれの異なる音の集積体から、曲想が次第に形を現し、トランペットとベースの確信的なデュオ演奏へと進む。他の奏者たちが交じり合う沸騰点からテナーサックスが上昇を始め、トランペットとギターも追随しそれぞれ頂点を極める。楽曲の底辺を支えるベースの上で、素晴らしいシンバルワークが要所を締める。フジワラが我々に見せる記憶への探求の中でも、この曲は最も感動的かつ挑発的である。この曲の背景となったストーリーについては、アルバムの長文ライナーに記されており、嘆きと希望が絶妙にミックスされたこの曲に光を与えている。
どちらのレコードも素晴らしく編成されており、シビアな観客の耳に訴えかける。この週末のコーネリア・ストリート・カフェでのライヴ・パフォーマンスは、たいへん意義深いお披露目だった。

photo by Cisco Bradley
Tomas Fujiwara Official Site
http://tomasfujiwara.com/
【関連記事】
Jazz Right Now #02 トマ・フジワラ・インタビュー
http://www.jazztokyo.com/column/jazzrightnow/002.html#04
Five by Five #1203
『Tomas Fujiwara & The Hook Up/After All Is Said』剛田武 & 多田雅範
http://www.jazztokyo.com/five/five1203.html
パスカル・ニゲンケンペル Pascal Niggenkemper
今月のもう一枚の注目すべきレコードは、ドイツ生まれ、ブルックリン在住のベーシスト、パスカル・ニゲンケンペル Pascal Niggenkemperのソロ・アルバムである。リーダー(Vision 7)、コラボレーション(PascAli)、そしてサイドマン(ハリス・アイゼンシュタットのゴールデン・ステーツ、ネイト・ウーリー=デイヴ・レンピス・カルテット)のいずれに於いても才能を現してきた。『ルック・ウィズ・ザイン・イアーズ Look with Thine Ears』 (Clean Feed)は彼の初めてのソロ・アルバムであり、ベースの音響的可能性を拡大する試みである。しかしそこに留まりはしない。ニゲンケンペルは鋭い音楽センスを持つ熟練したプレイヤーであり、あらゆるベース奏法テクニックを駆使して深遠なサウンドスケープを創造し、ベテラン・リスナーをも驚かすのである。常に多層的で、複雑で、角張って、鋭利なこのアルバムは、演奏に使われる素材の幅広さだけでも、リスナーに対する挑戦といえる。各曲が全く新しい方向を持ち、ガラガラしたメタリックな摩擦音の芳醇な弓弾きから、一つの楽器から出ているとは信じ難いほど逞しく凶暴なロック・リフまで、無限の幅を持つ。このレコードは、革新的ベースの次世代の展望に興味を持つ人すべてにアピールするだろう。
 |
 |
| Pascal Niggenkemper photo by Peter Gannushkin | 『Look with Thine Ears』 |
Pascal Niggenkemper - Be This Perpetual ? Be This Perpetual
https://www.youtube.com/watch?v=2dFWHbWyc2A
Pascal Niggenkemper Official Site
http://www.pascalniggenkemper.com/home.html
シスコ・ブラッドリー 2015年4月30日
(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)
photos provided by吉田野乃子 Nonoko Yoshida
Jazz Tokyoをご愛読のみなさま、初めまして。ニューヨークでサックスを吹いております、吉田野乃子と申します。
2006年に単身渡米してから、こちらの前衛音楽シーンに入り込んで、現場のミュージシャンから学び、活動して参りました。
私が体験した面白いイベントなどを紹介していけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
<The Stoneと大友良英さんのレジデンシー>
マンハッタン、ロウアーイーストサイドにある、ジョン・ゾーンの経営するThe Stoneというライヴハウスは、客席と同じ高さのステージと、椅子があるだけで、飲み物などの販売はなし、入場料は100%ミュージシャンにバックされる、前衛音楽を演奏、堪能するには最高の場所です。ドアのところで入場料を集めるのは、このシーンに関わっているミュージシャンや音楽関係者で、すべてボランティアです。私もここで2008年から働いていて、出演者のセットアップを手伝ったり、リハを見たり、話をすることで、いろいろなことを学んできました。ボランティアのクルーは現在15人程いて、一人が月2、3回働けば良いので、みんな、自分の見たいライヴの日にサインアップしたりしています。店の家賃や経費は基本的に、かつては月に一度、今は不定期に行われているゾーン氏と仲間の即興ライヴでの入場料と、店で販売しているCDの売り上げでまかなわれています。(足りない分はゾーン氏のポケットマネーから出ているはずです。いやはや頭が上がりません)
The Stoneは元々、ゾーン氏から任命されたキュレーターが2週間〜1ヶ月ブッキングをするシステムで、キュレーターによって毎月違ったシーンの出演者が楽しめました。現代クラシック、フリージャズ、インプロビゼーション、エレクトロニクス、インディーロックやパンク寄り‥‥共通しているのは、どの出演者も前衛的、創造的であるということでした。
2013年4月からは、一人のミュージシャンが1週間、毎晩演奏をするという、レジデンシーシステムに変わりました。ヴィレッジ・ヴァンガードやブルーノートといった、ジャズのライヴハウスなどでは、一つのバンドが数日連続で演奏するということがよく行われていますが、前衛シーンのアーティスト達にはなかなかそのような機会がない、ということでの、ゾーン氏の計らいです。ただ、上記のようなジャズのライヴハウスとの違いは、出演者は毎晩、違うバンド、違うプロジェクトで出演することを求められるということです。
2015年4月の第3週は、大友良英さんのレジデンシーが行われました。大友さんのターンテーブルとSachiko Mさんのエレクトロニクスによる、緊張感のある微音系の美しいノイズのデュオを皮切りに、毎晩、様々なミュージシャンとのコラボレーションが繰り広げられました。最終日、4月19日(日)のファーストセットは、私がサックスを吹いているカルテット、『ペットボトル人間』と大友さんの共演でした。バンドのオリジナル曲を私たちがノンストップで演奏し、大友さんには、好きな時に好きなように即興をしていただくことになり、大友さんのギターにインスパイアされ、いつもの私たちの曲が何十倍もパワーアップしました。「もし途中で『これは良い!』という展開になったら、元々の曲の構成はどんどん無視して行こう」ということにし、曲中の即興の部分を引き延ばしたり、エンディングをわざと削って次の曲へなだれ込んだりと、縦横無尽に駆け回りました。最終日のセカンドセットは、大友さんの貫禄のソロギターで締めくくられ、素晴らしい一週間を見せていただきました。
大友さんご自身のブログでも、レジデンシーの様子をご覧いただけます。
大友良英JAMJAM日記
http://otomoyoshihide.com/date/2015/4/?cat=9
 |
 |
| Pet Bottle Ningen + Otomo Yoshihide David Scanlon, Otomo Yoshihide (guitars) Nonoko Yoshida (sax) David Miller (drums) Chuck Bettis (electronics) |
|
<即興シーンの先輩、友人達の活躍>
今月も、他にも面白いライヴをたくさん見ましたが、即興系のイベントを二つピックアップします。
4月20日(月)
Briggan Krauss’ H-Alpha @ Roulette, Brooklyn
Briggan Krauss (alto saxophone), Ikue Mori (laptop), Jim Black (drums and percussion)
Special Guest: Brandon Seabrok (guitar), Kato Hideki (bass)
シーンの重鎮ミュージシャンによるトリオH-Alphaに、ベーシストのKato Hideki氏、ギタリストのBrandon Seabrok氏が参加。凄腕インプロバイザーが5人も集まると、多様なシーンに富んだ長編映画をみているような、壮大なインプロが行われます。サックスのBrigganはよく、“不自由にすること”をボキャブラリーにしているように感じます。わざと吹きにくそうな体勢、くわえ方、運指で演奏をしたり、ベルにタオルのようなものを詰めて曇った音を出したりなど、故意にサックスの開放的な音を制限するのですが、そうすることで、他の楽器の音質と相性良くブレンドされているように聞こえます。複数名による即興を聴く時、「あれ、この音は誰が出しているんだろう?」と思う瞬間がとても面白いのです。
参考音源 Briggan Krauss’ H-Alpha
https://www.youtube.com/watch?v=fYmOURkOH8s
4月22日(水)
Henry Kaiser/Weasel Walter Large Ensemble @ JACK, Brooklyn
Henry Kaiser (guitar), Weasel Walter (drums)
Alan Licht (guitar), Tim Dahl (bass), Brandon Lopez (bass), Jim Sauter (saxophone), Chris Pitsiokos (saxophone), Matt Nelson (saxophone), Michael Foster (saxophone), Peter Evans (trumpet), Dan Peck (tuba), Steve Swell (trombone)
恐らく一夜限りのアンサンブル。出演者は揃いも揃って、マッチョなパワー全開のインプロが持ち味の、前衛音楽シーンの“悪い奴ら”ばかりです。これはとんでもない爆音ライヴになること間違いなしと、誰もが思って会場に向かったはずです。ステージ上に電子時計をセットし、ドラムのWeaselが書き出したスコアに沿って即興が行われます。スコアには(本当はネタバレしちゃいけないので見てはいけなかったそうなのですが)時間と(何分何秒から何分何秒まで)誰が(ソロだったりデュオだったりもっと大勢だったり)何をするか(自由にソロ、ロングトーン、八分音符、静か目、爆音など)といった指示が書かれています。指揮者が合図するわけでもなく、こちらからは時計もスコアも見えないため、変化が一瞬にして、突発的に起こり、ものすごいスピードで曲が展開して行くのです。1時間ちょうどの曲が、休憩を挟んで2度演奏され、音の洪水で、やたらとハイな状態になったり、逆にぐったり疲労したり、精神に異常をきたしたオーディエンスも少なくなかったように思われます。さすが極悪インプロ集団でした。(笑)
 |
 |
1987年生まれ。北海道岩見沢市出身。10歳からサックスを始め、高校時代、小樽在住のサックス奏者、奥野義典氏に師事。2006年夏、単身ニューヨークに渡る。NY市立大学音楽科卒業。前衛音楽家John Zornとの出会いにより、完全即興や実験音楽の世界に惹かれる。マルチリードプレイヤー、Ned Rothenbergに師事。NYで結成した6人組のバンド" SSSS (Super Seaweed Sex Scandal)"で、2010年5月、ドイツ、メールス音楽祭に出演。2週間のヨーロッパツアーを行う。2009年からNYで活動している前衛ノイズジャズロックバンド"Pet Bottle Ningen (ペットボトル人間)"でJohn Zorn主宰のTzadikレーベルより2枚のアルバムをリリース。4度の日本ツアーを行う。2014年4月、ベーシスト、Ron Andersonの前衛プログレバンド"PAK"のメンバーとして、ドラマー、吉田達也氏と日本ツアーを行う。
William Parker Interview Part 1
ウィリアム・パーカー William Parker (bass)
1952年米国ニューヨーク市ブロンクス生まれ。71年に演奏活動を始め、当時の「ロフト・ジャズ」の支え手として活躍。80年から91年までセシル・テイラー・ユニット、またサックス奏者デヴィッド・S・ウェア・カルテット、90年代に入ってからはマシュー・シップのグループでも演奏。ペーター・コヴァルトやペーター・ブロッツマンを始めとするヨーロッパの即興演奏家との共演も多い。リーダーとして、コンポーザーとして、後進の育成者として自在な力を発揮している。96年からニューヨーク市で毎年開催される即興音楽を中心としたダンスやヴィジュアル・アートも含めた総合的なイベント「ヴィジョン・フェスティバル」の主催メンバーの一人。前衛詩人であり、アフリカ民族楽器も演奏するが、ブラック・ジャズのスピリットを伝えるベース音の重厚さが、黒い霊樹のような存在感を放つ唯一無二のベーシストである。最近作に『Essence of Ellington』(Centering Records, 2012)、『Live in Wrolove』(Forune, 2013)、『Wood Flute Songs: Anthology - Live 2006-2012』(AUM Fidelity)。
interviewed byシスコ・ブラッドリー (Cisco Bradley)
on Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/
translated by 剛田武 (Takeshi Goda)
癒しの力としての音楽〜ウィリアム・パーカーの音楽哲学 <前編>
Music as a Healing Force: The Musical Philosophy of William Parker : Part 1
2014年11月17日、私は伝説的ベース奏者ウィリアム・パーカーのローワー・イースト・サイドのアパートを訪れて、彼の音楽哲学についてインタビューをした。前月にブルックリンで開催された彼のギグでインタビューの打診をしたとき、私は自分がライターで、特に「登場したばかりの若手アーティスト」に注目していると自己紹介した。彼は苦笑いしながらも私の申し出を快諾してくれた。その苦笑いは今もそのままだが。。。
冗談はさておき、パーカーは現在60代前半にして、生々しいエネルギーと新鮮な好奇心を保って創造活動を続けている。1970年代にセシル・テイラー・ユニットをはじめとするパイオニア的なグループのメンバーとして活躍したパーカーは、90年代に活況を呈したNYダウンタウン・シーンにインスピレーションを与えた音楽家のひとりとして大きな注目を集めた。それから25年間のあいだ、彼は信じられないほど多数のレコーディングに参加し、次世代アーティストに多大な影響を与え続けてきた。
私がアパートに到着した時、パーカーはデューク・エリントンのライヴ・ビデオを観ていた。彼が座っている古いソファの後ろの壁には、たくさんの楽器---いくつかは彼自身のお手製---が飾ってあった。最近リリースされたフランク・ロウ・カルテットのレコード『OUT LOUD』(Triple Point Records, 2014)が暖炉の棚の真ん中に飾ってあった。そのレコードは、パーカーの最初期の演奏を収めた貴重なレコーディングのひとつである。奥の部屋のクローゼットには、彼の参加したレコードのコレクションが詰まっていて、気前よく見せてくれた(その多くは私も所有しているものだった)。世間話(歴史の話や前日に結審した黒人青年射殺事件のダレン・ウィルソンの評決のことなど)に続いて、音楽の話題に移ると、私はできるだけ口を挟まず、パーカーの語るに任せた。
Cisco Bradley(以下CB):あなたの音楽哲学について話していただけますか?
William Parker(以下WP):話したいことはたくさんあります。
もし私が詩人であれば、私の役目は、言葉を集めて正しく並び替えて、他人が読んだときに、魔法のように読者の運命を変えてしまうことでしょう。
もしくは画家なら、特定の色やイメージをカンバスに描いて、それを見たときに、何かの魔法のように見た人の人生を変えてしまう。
音楽家なら、サウンド(音)をトーン(楽音)に変化させて、人々がその音楽、これらの楽音、それらの音列を聴いたときに、やはり聴き手の人生を変容させるでしょう。
芸術家はそんな変幻の混乱の真っただ中にいますが、自分の表現の力を強く信じているので、やり続けるのです。というより、やらずにいられないのです。自分自身のやり方で、世界のバランスを変化させつつ、自らのバランスを保っているのです。
もし音楽を作るのをやめたら、言葉を集めるのをやめたら、絵を描くのをやめたら、世界が軌道から外れて行くのを見ることになるでしょう。もしまだ軌道通りに動いているとして、ですけどね。
つまり、私は世界が内破するのを防ぐのが芸術の役割だと思っているのです。だから何があろうと続けなければならない。勝ち目があろうがなかろうが、続けることが本当に重要なのです。
CB:音楽を始めたときから、常にそう感じてきたのでしょうか。それとも何かきっかけがあったのですか?
WP:本当に私に大きな影響を与えた出来事がいくつかあります。
段階を追えば、最初は「我々はなぜここにいるのか?」、次に「私はなぜここにいるのか?」、そして「私は何をしようとしているのか?」という疑問の変化です。
子供が成長する時期は、ただロープに従う(周りの言うことを信じる)だけです。私の家には本物のクリスマス・ツリーはありませんでした。毎年クリスマスになると箱にしまってある銀のクリスマス・ツリーを出して、親戚が持っている緑のツリーと一緒に飾りました。母はハヌッキーヤー(ユダヤ教の八枝の燭台)を窓際に置いて、それに灯りを燈しました。金曜日には魚料理を食べました。母が金曜日には魚を食べる、と決めていたからです。そんなとき、子供は置かれた環境にただ従うだけです。
ご存知かもしれませんが、私が育ったのはダウンタウンの公団住宅でした。環境としては、詩的な生活とは程遠いように思われるでしょうが、一方で詩的世界の入り口でもあったのです。ブロンクスには空があり、いつも空を意識していました。木々の間からは日の光が差していました。そして、空き瓶を集め出す頃には、誰かに教えてもらうことなく、子供たちはこうしたことを知っていました。
通りの向かい側でウェブスター・ハウスという公団住宅が建設中で、男たちが働いていました。子供たちはそこへ行って待ちます。昼休みに男たちがランチを食べに出かけた後に残された空き瓶を集めて店に持っていけば、2セントか5セントもらえました。子供には恰好の小銭稼ぎでした。
そんなコンクリートに囲まれた生活(後に私はコンクリート・マウンテンと名付けました)、その中には「光」がありました。毎週末田舎の別荘に行くなんてことはあり得ませんでした。でも私は光があることに気付いていました。光は、どこに居ようと誰にでも届くことを知っていました。幸せだって、振り向いて肩越しに見ればそこにあることが判るでしょう。それに気付く人と気づかない人がいるのが不思議でなりません。
人はみんな異なるバックグラウンドで育ちます。最近よくインタビューで話すのですが、私の父は、仕事から家へ帰ってくると、さっき私がビデオを観ていたデューク・エリントンのレコードをかけました。『ライヴ・アット・ニューポート』なんかのレコードを聴きながら、家族みんなで踊ったものです。毎週土曜日は音楽の日でした。土曜日は父の仕事が休みだったので、音楽を聴く日だったのです。父が好きなベン・ウェブスター、ウィリス・“ゲイターテイル”・ジャクソン、コールマン・ホーキンスなどのレコードを聴きました。ジョニー・ホッジスも好きでした。
ラジオも聴きました。といってもチャビー・チェッカーの<ザ・ツイスト>とかその手のヒット曲はあまり好きではありませんでした。でも朝の4時になるとジャズ番組が始まりました。家族で早朝にジャズを聴く。そうやって私たちはジャズが好きになったのです。最近の親はヒップホップを聴きます。ずいぶん前からそれが彼らの音楽であり、もうジャズを聴くことはありません。でも私の両親はジャズを聴き、近所にもジャズを聴く人がいたのです。
もちろんどこでも安全だったわけではありません。通りの向こうのパターソン団地には、イカれた連中がいて危ないので、近づかないよう言われていました。でもそれさえ守っていれば、一日中外で遊ぶことが出来ました。今日では、親が子供たちを自動車でサッカーやバスケットボールに送り迎えし、コーチがいてすべて組織化されています。私が子供の頃にはそんなことはありませんでした。リトルリーグに所属したこともありません。ただ一日中外へ出て、公園や通りでいろんなゲームやあらゆる種類のスポーツをしました。素晴らしい思い出です。
でも私にとっての一番の関心事は音楽でした。その当時、1962年私は10歳、1964年には12歳、その頃、レコードがモノラルからステレオに変わったのです。1トラックしかないモノラルよりも、新しい2トラックのステレオが主流になったので、モノラル・レコードは99セントで買えたのです。
土曜日に家族でハーンズ・デパートへ行きました。父は私たち子どもに5ドルくれて、父向けのレコードと自分が欲しいレコードを買うよう言いました。父の好みを知っていたので、デューク・エリントンの新譜『ファー・イースト・スイート』や『ソウル・コール』などを買ってきました。そうやってレコード売場を探しているうちに、私たちはアトランティック・レコードを知ったのです。オーネット・コールマンやジョン・コルトレーン。ジャケットは絵画なので、見てもどんなサウンドかわからなかったのですが、買い集めるようになり、ライナーノーツを読んだりジャケットを眺めたりしました。そうやってゆっくりと物事は輝き始めたのです。
一方学校では博物館に行きました。65年に中学校で、博物館見学の授業があったのです。動物園など野外の施設にも行きました。そのおかげで、私は教育の重要性が本当に判ってきました。
高校時代にジョン・デューイに出会い、情報を与えてからそれを隠す、パブロフ型条件づけ理論について学びました。正しく反応すればお茶を一杯もらえます。出来なければしょっぱい塩水を飲まされます。学校の考えは、情報を隠して正しい答えをを与えることなのです。学校は、生徒が自分自身であることに目覚め、自分が本当になりたいものを知るための助けにはなりません。だから私はその頃教育についてのエッセイを書いたのです。
*訳注:ジョン・デューイ(John Dewey, 1859年10月20日 - 1952年6月1日) アメリカ合衆国の哲学者、教育哲学者、社会思想家。学習を能動的なものと規定し、自ら問題を発見し解決していく能力を身につけていくことに本質をもとめる「問題解決学習法」を提唱した。なお原文ではThomas Dewey(40,50年代ニューヨーク州知事)となっているが、明らかに間違い。
その頃、私はジョン・コルトレーンの『至上の愛』やアルバート・アイラーなどを聴き始め、なぜ音楽が演奏されるのか、ということを考え始めました。なぜ音楽が演奏されるのだろうか?その答えは、音楽が癒しの力(healing force)だからです。癒すために演奏されるのです。一旦その考えに行きつくと、それが私の音楽をやる理由になりました。私は音楽に目覚めたのです。「ああ、僕は音楽がやりたい」と言うことを許されたのです。
同じ頃に、ジョン・コルトレーンについての本を読んで、精神世界について学びはじめました。コルトレーンは仏教に傾倒していました。だから、私はバガヴァッド・ギーター(ヒンドゥー教の聖典とされる宗教叙事詩。インドの2大叙事詩の1つ)を読みました。そして目が開かれたのです。私にはエホバの証人の叔母さんがいました。そのエリヴィラ叔母さんが家に来ると、魔法のように、みんないなくなってしまいました。というのは、叔母さんの仕事は、会う人みんなをエホバの証人に勧誘することだったからです。彼女は『失われた楽園への誘い』という黄色い本を持ってやってきました。正直者の私は「バスケに行かなきゃならない」などと嘘をつけなかったのです。だから私は彼女の思惑通りに、聖書の個人レッスンを受けることになりました。でも、どういう訳か、私は学ぶことを全部フィルターにかけることが出来たのです。すべてを文字通り受け取ることはなく、逆にすべてを投げ捨てることもありませんでした。
例えば、聖書の書かれた時代には、人は何千年も生きた、と言われたとしましょう。すると、耳から入った物事は、どんなことであろうと、栄養物だけ吸収して出てくるのです。つまり人間が1000歳まで生きられる?と聞いても、私にはどうでもいいことでした。興味を惹かれなかったのです。与えられた情報に何か自分の助けになることがあれば、それだけを取り入れるのです。
私が叔母さんとの個人授業を終えた後に本当の勉強が始まったのです。すべてが育っていきました。高校時代にたくさんの出来事が起こりました。新約聖書を学び始め、その本当の意味を理解できた、と本当に強い確信を抱いたのです。
そんなある日、ブロンクスのクレアモント・パークにいたとき、不思議なことが起こったのです。大雨の中で、私の身体は濡れもしなかったのです。つまり、あたり一面大雨が降っているのに、奇妙なことに、私の立っているところだけ雨が降っていなかったのです。私は、それこそ自分が正しい道にいることの徴(しるし)だと確信しました。
この話を人にすることはほとんどありませんが、あなたにはお話します。なぜなら本当に起こったことだからです。乗物に乗っていたわけではなく、本当に私の周りに雨が降っていなかったのです。虹のような何かがあって、雨に濡れないように守ってくれたのです。
このようにして、私は音楽をやりたいという気持ちへの確証を得たのです。学校には飽き飽きしていて。。。
CB:その頃あなたは高校生だったのですか?
WP:はい、そうです。私がすることすべてが必然で、私が出会った人すべてが、会うべくして会ったのです。学校には何人もの教師がいました。英語の担当は、スロットキン先生でした。当時先生が出した課題を、私は高校を卒業して20年経っても実践していました。彼の課題とは、美徳を定義し、正義を定義し、真実を定義し、愛を定義しなさい、ということでした。
他の生徒はみんな教室を走り回って遊んでいました。なぜならスロットキン先生は、口には出しませんでしたが、誰も落第させられないという考えを持っていて、全員を合格させるとわかっていたからです。だから他の生徒は、勉強なんかやる必要がない、と言いました。しかし、私はといえば、先生のお蔭で本当に人生が変わったのです。プラトンを読み始め、そしてソクラテスを、『プラトンの対話』を通して学んだのです。
プラトンの著作に『イオン』という対話篇があります。それは超自然を授かることが出来るか、美徳とは何かについて、そして神からの授かりもの(恩恵)についての物語でした。
詩人のイオンが、詩人コンテストから戻ったとき、ちょうどソクラテスや仲間はバーベキューを食べて座っていました。イオンは仲間に加わり、煙草を吸いながら言いました「自分は世界最高のホメロス暗唱家だ」と。「普段は身長5フィートだけど、ホメロスを暗唱すれば10フィートになれる」。そこでソクラテスは、君がそんなにすごいなら、他の詩人はどうですか?と尋ねて、他の詩人の名前を挙げました。イオスは「いいえ、他の詩人を暗唱するのは余りうまくありません」。ソクラテスは、「ほほう、そうですか、でもホメロスをうまくできて、他の詩人はできないのはどういう訳ですかね?」と言いました。そういったやりとりが対話篇に書かれているのです。
ソクラテスは話し続け、例として運動力学と磁石の輪について説明します。磁力が輪を通して出てくるように、人から出てくる力について。つまり、イオンはホメロスにだけ磁石のようにくっつき、それ以外の人にはつかないのです。それは彼が学んで得たものではなく、超自然的に神から授かった授かりものなのです。
別の例を出しましょう。ロサンゼルス・レイカーズに雇われてシャキール・オニールにフリースローのやり方を教えた郵便局員の話です。彼は一日中手紙を配達していたので、全くミスをせずフリースローをすることが出来たのです。ドリブルはできません。コートを走り回ることもできません。ただフリースローだけは完全にうまくできるのです。
ある人が尋ねました。「あなたはフリースローを練習したのですか?」。郵便配達は答えます。「いいえ、練習したことはありません。ボールをください(投げる動作)、ボールをください(投げる動作)、ボールをください(投げる動作)」「ええっ、どうやるんですか?」「神からの授かりものです」
神の恩恵なのです。彼らは話を続けます。「では、他の誰かがそのやり方を学べますか?」。彼は答えます。「はい、どうやるかを学ぶことは出来ます。でもそれは神からの授かりものではありません」。判りますか?そうやって私には、授かりもの(天賦の才能)と本当の発見が判り始めたんです。。。
自分なりの音楽美学を身に着けるためには、人生の生徒として、自分が授かった神の恩恵を見つけなければならないのです。自分自身がおのずから持っているものを理解して、それ以外のものに専心すればいい。いったんそれを見つけたら、おのずと創造のドアが開くでしょう。次から次へと。
その頃、私は映画を学んでいました。フランス映画です。フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダール、ロベール・ブレッソン、クロード・シャブロル、そしてスウェーデン映画のイングマール・ベルイマン。それからインディペンデント映画に進み、私にとってとても重要な書物に出会いました。ジョン・メカスの『メカスの映画日記―ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959‐1971』です。それは私が後に『サウンド・ジャーナル』(2004)という著作集を出版するアイデアの元になりました。さらに著作集『フー・オウンズ・ミュージック?』(2007)も出版しました。
*訳注:ジョナス・メカス(Jonas Mekas、リトアニア語ではヨナス・メカス、1922年12月23日〜)は、リトアニアの映画監督、作家、キュレーター。ビルジャイ近郊セメニシュケイ出。「アメリカ実験映画のゴッドファーザー」と呼ばれる。
それから私はスタン・ブラッケージという映像作家に惚れ込みました。彼は同じことを彼のやり方で語っていました。ケネス・パッチェンも同じことを彼なりの方法で話していました。そのように私が選んだ人はみんな、同じ感情を掻き立ててくれたのです。自分自身の声(ヴォイス)を見つけて、内側に取り入れ、身体の中から音楽として放出するということは、彼らが映画を編集するときの状態と同じです。あまり考えることなく、トランス状態に入るのです。セシル・テイラーは、演奏するときトランス状態になると話しています。
*訳注:スタン・ブラッケージStan Brakhage(1933〜2003)。アメリカ生まれ、映像作家。1950年代からN.Y.で創作活動を始め、1960年代以降アメリカの実験映画を代表する作家に。代表作に『DOG STARMAN』など。
*訳注:ケネス・パッチェン Kenneth Patchen (1911年12月13日〜1972年1月8日) アメリカの詩人・小説家。美術や音楽を取り入れた実験的な作風で知られ、サンフランシスコ・ルネッサンスとビート世代に多大な影響を及ぼした。
そうやって学んだり経験したりしたことを整理して、魔法がどのように働くのかを理解しはじめました。しかし同時に、魔法に近づき過ぎたくはありませんでした。近づいて、魔法を把握し自分の物にしようとは思いません。だって、魔法を所有してはならないから。形にしたくもありません。なぜなら恐れているから。私はそれを自分にとって神秘的なままにしておきたいのです。所有したくない、いつもそうなんです。つまり、すべての答えを手にいれてしまうと、何かをやるやり方、やる方法、やるべきことが決められてしまう。そして私は見出しました。。。
これが私が見出した最も大切なレッスンです。もし私が何かをやる時の秘訣(フォーミュラ)を考え出して、あなたにそれを教えたとしましょう。するとあなたは秘訣を試してみるでしょう。で、次に起こることはこうです。あなたは私の家のドアをノックしてこう言うでしょう。「ウィリアム、何でこんな秘訣を教えたんだ。全然うまくいかないよ」。私は言います。「うまくいかないですって?じゃあ私がやってみましょう」。私が試すと、完璧に上手く行きます。私にはなぜそれが上手く行かなかったのか判りました。あなたは私ではないからです。
誰もが自分自身の秘訣を持っています。そして私が思うに、秘訣には、秘訣のための原料が必要です。しかし、どんなに投入しようとも、どれだけ取り除こうと、何個のX要因を秘訣に加えようと、結局あなた次第なのです。
なぜなら、私たちは皆、自分自身の音楽DNA(遺伝子)を持っているからです。私の音楽DNAはあなたには役立たないし、あなたのは私には役に立ちません。だから、誰でも自分の秘訣を見出せれば成功することが出来ると思うのです。自分自身であるための、自分だけのやり方を見出したなら。しかしあなたはそれを捕まえて所有することはできません。それを手に入れて、すべてを学んだ、と言うことはできません。何故なら、秘訣は常に変化するからです。コンスタントに変化しています。そういうことを理解したうえで、私はベース奏者として、人生の舞台に上がろうと決心したのです。
高校の最終学年の時に始めました。ベースを手に入れて弾きはじめ、いろんな人々から学んで、練習練習また練習して、多少満足に演奏できるようになりました。それからは現場で訓練あるのみでした。
CB:それは1971年頃のことですか?
WP:はい、70、1年です。私が最初のレコードを制作したのは74年ですから。私がブロンクスからヴィレッジのダウンタウンに移って演奏し始めたのは72、3年頃だと思います。
ここでもまた、私はいつも会うべき人たちに巡り合いました。1973年にアンドリュー・ヒルと、次にビリー・ヒギンズと出会い、知己を得ました。ビリー・ヒギンズとは少なくとも週に二回は彼の自宅で演奏しました。外へ出て街中のいろんな店でデュオで演奏しました。クリフォード・ジョーダンやクリス・アンダーソンやウィルバー・ウェアに会いました。ラシッド・アリとはボワリー通りにあるヒリーズで演奏しました。CBGBと名前を変える前は、そこはジャズ・クラブだったのです。確か毎週月曜日に出演していたはずです。
ラシッドはとてもオープンな人で、すぐに私を受け入れてくれました。「おいで。ここへきてバンドで演奏しなよ」と言って。1975年にドン・チェリーに会いました。一週間ファイヴ・スポットで一緒に演奏しました。1974年にはセシル・テイラーと出会い、73年、いや74年にカーネギー・ホールに出演しました。つまり、一つの出会いが次の出会いへ導いたのです。
それから、私はどのように自分自身の音楽を身につけているべきかを学びました。もしマイルス・デイヴィスのような大物ミュージシャンに雇われたなら、「僕はマイルス・デイヴィスと一緒にやってるんだ」と慢心して、マイルス・デイヴィスの音楽のやり方しか知ろうとしなかったでしょう。ドン・チェリーと一緒にやることはなかっただろうし、ビル・ディクソンと一緒にはやらなかったでしょう。ロスコー・ミッチェルやミルフォード・グレイヴス、ラシッド・アリやビーヴァー・ハリスと一緒にプレイすることもなかったでしょうね。
私が一緒に活動した人たちはみんな異なる哲学を持っていました。私はいろんな人たちの音楽のやり方を経験出来て幸運でした。だから私は胸を張って、なんだって可能だと言えるのです。多くの、とてもたくさんの可能性があるのです。すべてを記録しなくても可能です。すべてを正しく記録しても可能です。自分自身の記録を創り出しても可能です。可能性は無限大なのです。
それはすべて私が自分のやりたいことを秘訣(フォーミュラ)化する役に立ちました。私がやりたいこととは、音楽を演奏することでした。どうやればいいか、正確には判りません。だから、旅をして人に会うのです。
謎の塊のような花崗岩のブロックから形を彫り出すようなものです。そして何が役に立つのか見つけるのです。そして見つけた方法で演奏すれば月曜日はいい音がするのです。でも、火曜日に同じ方法で演奏をしてもうまくいきません。つまり、瞬間は瞬間でしかないということです!食べ物を熱いうちに食べるのと同じです。今食べなければダメ。残り物はフォーミュラが変わってしまいます。在り方が変わってしまい、文字通り醒めてしまうのです。
だから瞬間瞬間に演奏出来なければなりません。私の生徒たちにいつも言うのは、「瞬間に演奏する」ことを学ばなければならないということです。学んだことを演奏するのでもなく、やりたいと思っていたことを演奏するのでもないのです。瞬間に聴いたものを、まさにその瞬間に演奏する。ほんのちょっと前にはなかった曲、まさに今現れた演奏。それはとても難しいことです。なぜなら何かを学ぶととても嬉しくなって「やった!僕は何かを学んだぞ、だから学んだものを演奏したい」となるからです。
しかし、やるべきことは、学んで習得したことを、すぐに忘れることが出来るようになることです。飲み込んで吸収したらすぐに別のところへ行くのです。「私はこれをやる方法を学んだ。これをやれば、これが起こることを知っている」ということに固執しないこと。なぜならあれ(別のこと)をやった時にはこれ(知っていること)は起こらないのですから。全く次元の異なるシャーマン(祈祷師)の世界に入らない限り。そうだとしても、心すべきはシャーマンはミュージシャンではないということです。シャーマンは癒すために音を使います。もしあなたが、シャーマンのように、特定のことを行うために、ガラガラを鳴らしたり、フルートを吹いたり、特定のドラムビートを叩いたとします。するとこういう考えに至るでしょう。あれを演奏したり、それを演奏したり、何かを演奏するといつも、違うことが起こる、ということが判るのです。
しかし、それは聴きたいと思っている身体の特定の器官に効果を及ぼします。なぜなら、器官が患っているときは、そこへ血液を流したいと思います。血液は癒しの栄養素だから。それは音楽でも同じです。
あなたはだんだんわかってきます。音楽を演奏した時には、今か5分後かはわかりませんが、最終的には何かが出来上がるということが。いつも違ってはいますが、起こるべきところで何かが起こるということ、それが秘訣(フォーミュラ)なのです。
こう演奏すれば(音を真似る)ボップ、バップ、バボップ、ボップ、ボップ、ブーン、みんなハッピーになります。アート・ブレイキーだろうと誰だろうと。そのメロディーを演奏すれば、みんながジャンプします。部屋中ダンス大会です。例えば昨晩そんな風な演奏をしたとしましょう。もちろん結果は毎回異なります。でも秘訣は同じです。このリズムを弾けば、これが起こります。あのリズムを弾けば、あれが起こります。そのような特定のことをするための事象の語彙、カタログのようなものを持ち始めたのです。
先日のソロ・コンサートのときにお話ししたかもしれませんが、最終的に私が辿り着いたのは、ベースを、それまでと異なり、光の束として見るようになったことです。それぞれの弦が光の束で、弓で創られるハーモニーは、プリズムへ光を送るようなものです。弓がプリズムで、弦が光です。弓で弾くと光が見えます。その色の中に暗示が、魔術の始まりがあるのです。
私は常にそう信じています。それはミルフォード・グレイヴスの家へ通い始めるまでは判りませんでした。ミルフォード・グレイヴスは60,70,80,90年代を代表する革新的ドラマーです。今でも演奏し続けています。そして鍼灸師であり、ハーブセラピストでもあります。そして、ここ10年余りは心臓の調査をしています。彼がやっているのは、電子聴診器をあなたの心臓に当てて、鼓動を録音することです。でも単なる(音を真似る)ドキン、ドキン、ドキン、ドキンではありません。彼が長時間鼓動を録音する理由は、ドキンドキンだけはなく、他に多くのことが進行しているからです。まあ経験しなければ判らないでしょうが。。。
彼が私の鼓動を録音した後に彼の家へ再び行きました。彼は言いました。「ウィリアム、再生しようじゃないか」。そして彼は私に音を聴かせました。それは私のベース演奏のような音でした。私は言いました。「これは私の鼓動ではありません。私がベースを弾く音です」。彼は言いました。「いや、これは君の心臓の鼓動だよ」。私は驚いて「ええーっ、本当ですか?ベースと心臓は繋がっているんですか?」
聴いてみないとわかりません。経験しなければ知らないままでしょう。そこで私はそれについて考え始めました。クロマチック・チューナーを肝臓の上に置いて調べてみよう。自分の肝臓の音程が何なのか、心臓の音程が何なのか?この内臓器官の音程は?
つまり、もしその音程で演奏すれば、肝臓を刺激することになります。聴覚を刺激します。その音程に近いほど、刺激を与えるのです。
ミルフォードたちはそれを心臓にやっているのです。心臓の鼓動に電気を流し、心臓の不整脈を治そうとしているのです。私はいつも考えています。私が音楽を演奏し始めた時、私の主音はDでした。だいたいDかDフラット。驚くなかれ、その通りだったのです。私は言いました「わあ、感じます!」。そこで調べてみたら、私の心臓の鼓動はDフラットだったのです。
CB:大変興味深い。
WP:Dで話すのです。
そのあとで、私はこのことについてもっと知りたいと思ったでしょうか?いいえ違います。
地下鉄で偶然出会った誰かに、「あれっ」と肩を叩かれ、「あなたはウィリアム・パーカーですか?」と聞かれました。「ハイそうです」。「なんと、あなたは15年前、いや20年前に私の学校に来ましたね。観客は5人しかいませんでしたが、あなたの音楽は私の人生を変えました」と言われたんです。
もし隣の車両に乗ったなら、その人に会うことはなかったでしょう。そしたら自分の音楽が人々に与える効果を知る由もなかったでしょう。
私がデヴィッド・S・ウェアと共演している時に会った人はこう言いました。「私は癌を患っていました。でもあなたのレコードを毎日聴いていたら、癌が良くなりました。治療の助けになったのです」。
そうやって私たちの音楽が人々の生命力の元になることを知りました。私たちはこの仕事を続けて音楽を演奏し続けていきます。でも、「もし誰かが私たちの音楽で本当に癒されたなら、お知らせください」などと宣伝することはありません。時にはそういう証明書があるのもいいのですが、殊更にそれを求めたくはありません。少なくとも現時点では。でも人々にポジティヴな影響を与えることは確信しています。だからこそ音楽をプレイし続けなければならないのです。自分がやるべきことをやる。それを人に教えること。そしてまた、人は自らの声を、自らの主音を見つけるべきだと思います。音楽や詩が身体の何処に共鳴するかを知るべきです。それを見つけましょう。
一旦それを見つけたら、自分自身を見つけられるし、自己啓蒙のように自分で自分に教えて、物事の本質を知ることが出来ます。
CB:瞬間に存在することについて話してくれますか?
WP:もちろん。
CB:あなたがキャリアを通して行ってきた様々なプロジェクトをそういった面で捉えているのですか?
WP:私が子供の頃の話になります。中学校の芸術の授業でミケランジェロ、そしてレオナルド・ダヴィンチについて学びました。また、マルチな才能の持ち主ヘンリー・マーサーについて。ご存知のように彼らは彫刻家であり、発明家であり、画家であり、素描もできました。
*訳注:ヘンリー・マーサー Henry Chapman Mercer (1856年6月24日 - 1930年3月9日) アメリカ、ペンシルベニア生まれ。ハーバード大学で古典学を学び、考古学を修めた。しかし40年後なぜかタイル、焼き物の生産を手がけ、成功する。その資金で地域の生活用品を収集展示する為のマーサー博物館を開設した。
私はミュージシャンになる前、物書きでした。劇の脚本を書き、詩を書いていました。だから私にとって音楽を書くのは自然なことでした。初めてベースを手に入れたとき、私の頭に自然に現れた音楽は24/7(7分の24拍子?)でした。私はそれを書き留めました。
私はそれを求めたのか?いいえ。それを探したのか?いいえ。つまり起るべくして起ったのです。また、私はひとつの音楽だけに興味を持ったのか?いいえ。私が最初に聴いた音楽は映画のサウンドトラックでした。子供の頃、サントラ盤を沢山買いました。1962年に『アラビアのロレンス』が上映された時に、モーリス・ジャール(曲を口ずさむ)を気に入り、オリジナル・サントラ盤を買いました。映画を観るより前にサントラ盤を買うこともありました。そうやってモーリス・ジャールが手掛けた『ドクトル・ジバゴ』、そしてジョン・バリーやジェリー・ゴールドスミス、エルマー・バーンスタインやクインシー・ジョーンズ、そしてラロ・シフリンが音楽を担当したジェームス・ボンド映画。だから、サウンドトラックと音楽を作曲することが結びついて興味を持っていたのです。
2012年にやったデューク・エリントンのプロジェクト『エッセンス・オブ・エリントン』も同じです。「なぜ『エッセンス・オブ・エリントン』をやるのか?」と問われたら、エリントンを私に教えて訓練してくれた父のためです、と答えます。エリントンを聴かせてくれた一年後に父がトランペットをくれました。「このトランペットを吹きなさい」と。弟にはアルト・サキソフォンを与えました。
何年も経ってみて、父が私と弟をエリントン・オーケストラに入れようとしていたことに気がつきました。そのために音楽のレッスンなどすべてを受けさせたのです。彼の夢は私たちをエリントン・オーケストラでプレイさせることだったのです。父は亡くなりました。父は私の演奏を聴くことはありませんでした。だから私は『エッセンス・オブ・エリントン』を制作したのです。
やりたければ即興以外のこともやることができました。子供の頃、ものを書くことが好きでした。本当に本を書きたいと思っていました。そして今、私は本を出版しています。これもまた、自分に出来ることをしているだけなのです。
私は、メロディーを聴いたらそれから逃げてはいけない、という考えを持っています。感染するようなリズムを聴いたら、それから逃げてはいけません。その点が最近多い即興演奏家との違いでしょう。彼らはけっしてメロディーを演奏しない。けっして繰り返すリズムを演奏しない。常にすべてが破綻している(音を真似る)。そんなサウンドは、そういう演奏をすること自体が目的であるだけで、それ以外に大きな意志はありません。それとは違って、私のやり方は、どんなメロディーもモチーフもやりっぱなしにするな、というものです。
1982年に渡欧し、FMPでヨーロッパのインプロヴァイザーと即興演奏を始めました。私は何事からも逃げませんでした。ブルースがプレイしたくなったら、ブルースを演奏しました。
デレク・ベイリーと共演したとき、彼は言いました。「ああ、いいですね。気に入りました。なぜなら、共演した中で、あなたは自分自身であることを恐れない唯一の演奏家だから。他の人はみんな、私のように演奏しようとします。共演するなら、その人らしい演奏をして欲しいのです」
音楽は共通言語です。ブルースはひとつのやり方です。ベイリーは、現在の即興演奏スタイルになる前、ナイトクラブでいつもスタンダードばかり演奏していた、と話してくれました。そしてそれがとても楽しかったと言いました。もちろん、私が演奏するのは違うブルースです。ゴリゴリのブルース・ファンが私の演奏するブルースを聴いたら、「ああ、アヴァンギャルド過ぎる。君の演奏はブルースじゃない」と言うでしょう。でも私にとってはブルースなのです。私は何をやるのも恐れません。
これらすべての経験が、ひとつのことへ導き、別のものから別のものへ繋がりました。私にとってとても実り多い経験でした。
私が美学を論じようとする理由のひとつはこうです。私たちがすることの裏には理由がありますが、自分がすることの理由を証明する必要は全くありません。
インドに行ったら、ミュージシャンは違う音楽を演奏しています。「何故このラーガを演奏するのですか?」と彼に尋ねたら、こう言われるでしょう。「ただこのラーガを演奏しているだけです。私がこのラーガを演奏する資格があるということを証明する必要はありません。そして、あなたはここに来て私にそれを質問する権利はありません」
つまり、言いたいのは、音楽は誰のものでもない、ということです。誰にでも広く開かれています。世界の何処にいても、どんなスケールでも使用できます。自分自身のスケールを作れます。どんなリズムでも使用できます。自分自身のリズムを作れます。なぜなら音楽は誰のものでもないからです。つまり音楽を好きなようにできるということです。
誰が音楽を所有していますか?誰でもありません。音楽は売り物ではないのです。
(209号の<後編>へ続く)
William Parker Official Site
http://www.musicofwilliamparker.com/
ウィリアム・パーカーは土取利行の招きで来日し、7月20日郡上八幡音楽祭で土取、エヴァン・パーカーと共演する。それに先立つ7月17日は京都で、また7月21日には東京でも公演を行う。
詳細は:http://gmf2015.wix.com/free
シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley
ブルックリンのプラット・インスティテュートで教鞭(文化史)をとる傍ら、2013年にウェブサイト「Jazz Right Now」を立ち上げた。同サイトには、現在までに30以上のアーティストのバイオグラフィー、ディスコグラフィー、200以上のバンドのプロフィール、500以上のライヴのデータベースを備える。ブルックリン・シーンの興隆についての書籍を執筆中。http://jazzrightnow.com/
剛田 武 Takeshi Goda
1962年千葉県船橋市生まれ。東京大学文学部卒。レコード会社勤務。
ブログ「A Challenge To Fate」 http://blog.goo.ne.jp/googoogoo2005_01
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.