
あおいろの空に神さまが来て願いをひとつ叶えるなら、ぼくらのいのちは消えてしまうのだろう。
世界の終わり(バンド名)の「虹色の戦争」が爆音でかかり続ける5月22日の真夜中に。座間裕子さんがカフェズミでかけて来場者みんなをとりこにした(耳の人生の軌跡を少しだけずらした、と言い換えてもいい)フィールドレコーディングを構成したりする現代音楽系の作曲家マイケル・ピサロにしても、福島恵一さんがブログで眼差すディストピア・アンビエントなる音のありようにしても、世界の終わりが歌う世界観にしても、ぼくの中ではひとつの地平に重なって見えている。前方120度で聴いていた耳が、360度全方位に、地平線の向こうまで耳の手が伸びて聴きはじめるような、もう昨日の耳には戻れない、でもそれを伝える言葉の手立てが見つからない、見つからなくていいのだ、そこにはひとはいないし、ひとはいらないところ音、誰が聴くために?、さあ、ぼくはきのうのぼくをおいてけぼりにしてゆこう。
▼
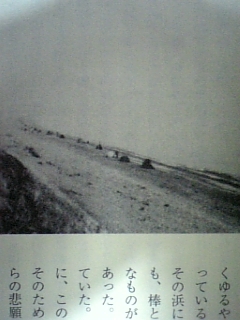
ロウストフトの南を三、四マイルにわたって、海岸線は長くゆるやかな弧を描く。草の生えた砂丘や低い崖の上方を通っている歩行者用の小径からは細(さざ)れ石の平浜が見下ろせるが、その浜に沿って、夜となく昼となく、一年中いつなんどきでも、棒と縄と帆布と防水布で思い思いに拵(こしら)えたテントのようなものがずらりと並んでいるのを、おりふし眼にすることがあった。それらは長い列を作って、ほぼ等間隔で海端に続いていた。あたかもどこかの流浪の民の最後の生き残りがここに、この地の果てにたどり着いて、これまでの窮乏も流浪もそのためにあったと思わせてくれるような、はるかな過去からの悲願であった奇蹟のおこるのを待ちわびているがごとき光景だった。・・・
W.G.ゼーバルト『土星の環』鈴木仁子訳(白水社)■
▼
プーさんは6月の第一週のヴィレッジ・ヴァンガードPAUL MOTIAN TRIO 2000 + TWO(Loren Stillman-sax, Masabumi Kikuchi-p,Ben Street-b, Thomas Morgan-b Paul Motian-ds)であばれまくるそうだ。録音してくれよ、ステファン・ウインター。
▼
来たる6月6日(日)に、吉祥寺カフェズミ sound cafe dzumi■で、福島恵一さんの音盤レクチャー「<耳の枠はずし>―不定形の聴取に向けて■」の第5回「複数のことば・ ECMカフェ in Sound Cafe dzumi」があります。
日時 6月6日(日) 15:00〜18:00
第5回 複数のことば・ ECMカフェ in Sound Cafe dzumi
ECMレーベル全作品をレヴューした「ECM Catalog」の出版に聴き手/書き手として参加した原田正夫氏(月光茶房)と多田雅範氏(元ECMファンクラブ)をゲストに迎え、各々持ち寄ったECM音源を聴きながら、都市空間におけるカフェの本来の機能である複数のことばの響きあいを実践し、聴き手の側から「聴くこと」の公共性の構築を目指す。音盤:Jon Balke,Joe Maneri,Alfred Harth,,,
なぜECMがテーマに選ばれたのか。これはおそらく、ECMほど多様でありつつもなにか統一したイメージがあり、それはジャズやフォーク、クラシック、ときにロックなど、ジャンルというかフィールドで培われてきた価値体系からの距離感によるものでもあるようだし、端的にプロデューサーのマンフレット・アイヒャーの存在感でもあるわけだけど、一方で盤に対する評価、リスナーの反応もじつに様々で、そこが対話に値するところでしょう。
当日は、わたしが選んだふたつのECMベスト20リスト、ひとつはECMファンとしてのベスト20、もうひとつはジャズファンとしてのベスト20、これを公開します。今はその前段階のECMベスト100をリストアップしている週末であります。え?なぜそんなことをするのかって?決まってるじゃないですか、福島さん、原田さんのベスト20を見たいからです。
あと。このCDを聴かせた(プレゼントした)、家庭教師してた生徒、と、親戚の子ども、と、その後ふたりとも精神科医になった、という、いずれも彼らに愛聴されていた密やかなECM盤があるので、その1曲をアナログで、定評あるズミのオーディオで、かける予定です。国立大学の医学部進学率100%のECM。ご来場をお待ちしております。・・・そんなのありかよ。

<track 057>
スガンバーティ:ナポリのセレナーデ / 井上頼豊 from 『チェロ・コンサート』 (株式会社音楽センター) 2006
チェロ:井上頼豊、ピアノ:村上弦一郎 1988.11.4 第一生命ホール
音楽をするよろこび。チェロのケースの取っ手に手をかけて玄関に立ち外をまなざしてい老人の写真をCDジャケのうらに見てから、このひとのチェロを聴かなくてはと思った。ある意味ジャケ買い。買ったときから、この演奏は始まっていたような気もする。ほかに聴きたいCDもあったのだけど、このCDを聴きはじめてからどうもほかのCDを聴く気にならない日々が続く。
カザルスの「鳥の歌」が最初と最後に収められていて。晩年のいろんなコンサートでの録音を並べた、このチェリストの生涯がコンサート・プログラムになったような、丁寧なCDパッケージや文字フォント、演奏者自身の語るような曲目解説、なにかほんとうに特別なコンサートに招かれたように聴き入った。プロコフィエフのソナタがハイライトになっていて、ラフマニノフのヴォカリーズ、外山雄三のこもりうた(これは五木の子守唄がそのまま構成されている)、カザルスの鳥の歌で終わる架空のコンサート。五木の子守唄と鳥の歌が奏でられたのは90年4月26日、カザルスの生地であるスペインのヴェンドレルでのリサイタル。この場所での拍手を演奏者がどのように感じたかも伝わってくる。
調べてみると井上頼豊(■)さんはチャイコフスキー音楽コンクールの審査員を務めたかたで、シベリア抑留の体験があるという。96年に83さいで逝去。ひとりのチェリストの人生をつらぬくような得難いCDに、不意に出会ったのだ。

<track 058>
July Mountain for field recording & percussion / Michael Pisaro, Greg Stuart (engraved glass p05) 2010
なになに、いきなり限定50の英国現代音楽レーベルCDを。なにげにジャケがうるわしいではないか。フィールド・レコーディング20テープとパーカッションをコンポジション構成した作品と、言われれば、その言われた理解が体験を妨げる。
ざわざわと。そりゃあ、平和台の駅前に雨が降り、木のざわめき、子どもと3人乗り自転車の放つ種々のサウンド、その遠近、運動、を受信するおれの耳だってフィールド・レコーディングになるわけだが、素材として、そこには明確な審美や嗜好、思考、趣向が祈るように介在してコンポーザーは録音作業をするのだろうと思う。
erstwhileレーベルの座間裕子さんと10年ぶりに会う。彼女の声を聴くとロヴァ耳の対談■当時にタイムスリップするわけだけど、いや、ミシェル・ドネダが屋外に出てからのおいらの耳の嗜好は、お寺の梵鐘とか坊さんの声明と木のはぜるサウンドとか、自然界の素材そのものではないけどそのざわめきやゆらぎに接していたいほうに来てしまってるんだよー、即興音響系のCDとか聴いてないしー、と話すと、それはもうマイケル・ピサロがやってることと同じアプローチだという。そんなわけで、吉祥寺カフェズミで、そのマイケル・ピサロを聴いてみたのであります。
これはもうサウンドのドラックでしょ。ノイズ好きの若い女性も、現代ジャズリスナーの男性も、美術家も、レコーディングエンジニアも、ズミに来ていたお客さんが皆して耳の人生の軌道の踏み外したような顔をしているではないか。ズミの店主もイタリアン・アンビエント・ノイズのGuiancarlo Toniutti盤■を持ち出してきて、すごいことになっている。
フィールド・レコーディングも、ノイズも、アンビエントも、その区分けはおいらにはようわからんけど、こういう音楽はもう最強でしょう。マイケル・ピサロについては座間さんのブログhttp://d.hatena.ne.jp/yukoz/20100401/p1に語っていただくとして、いやもう、単純に気持ちいい。武蔵小金井から府中にかけてひろがる見晴らしのいい住宅地の上空にセスナが飛んでいたり、鳥のさえずり、日差しの音までが聴こえてくる。もう、このマイケル・ピサロさんは京都に連れて行ったら、鴨川の土手に座ってせせらぎの音、お寺の鐘の音、大文字焼きの音、小料理屋の音、全部フィールド・レコーディングしてしまうんじゃない?
ヘッドホンで聴くとまたいい。語弊はあるけど、なんとも音楽的だ。ピアノの音はポップでさえある。もっと人のいないアンビエントなサウンドも世の中にはあるが、このえもいわれぬ高揚、これはマイケル・ピサロの類まれなる作家性だと思う。

<track 059>
I Remember You / Lee Konitz New Quartet from 『Live At The Village Vanguard』 (Enja) 2010
リー・コニッツ、1927年10月13日生まれ、82さい。27年生まれというと、スタン・ゲッツ2月2日、ジョー・マネリ2月9日生まれだったぞ。すごいよな、この同い年生まれのサックス奏者。生き残ってるのはコニッツだけか。
ジイさんのサックス奏者はすごいからなー。ロイドが38年生まれ、ショーターは33年生まれ、コニッツの3にんで、オールドマンサックス三重奏団を結成させたい。スポンサーは似た名前の証券会社。・・・30年生まれのロリンズはもう吹けてない、ので入れない。・・・39年生まれのプーさんをピアノにして、31年生まれのモチアンが叩く。・・・ベースは36年生まれのピーコックをスタンダーズからはがして持ってくる。名案だなー。・・・ああ、はやく富豪になって真の芸術のパトロンになりたい。
さて、コニッツが初めて自分のグループが持てて嬉しー!と豪語しているらしいニュー・カルテットのヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ盤が出た。ドイツのフローリアン・ウェーバー(ピアノ)のトリオに箔付けお相手してもらってるだけではないのか?このピアニストはポール・ブレイやリッチー・バイラークに師事した新進である。
若きオリンピック強化選手3にんと、かつての、50年前の世界記録と金メダルを取ったジイさんが、並んでマット運動しているんだけど、よろめくジイさんの倒立するタイミングにかつての栄光が見えるような気がする、という演奏だ。1曲目のラテン・グルーブが始まるまでのイントロ、3曲目、6曲目、が、松葉杖をつきながらも光るものを聴かせている。ピアノ・トリオは、タイトで申し分ない演奏を進める、という以上のものはない。何かあるんじゃねーかと、おれはこのCDを6回も聴いてしまったが。
コニッツについていえば、82年パリ生まれ両親米国人のDan Tepfer (p) と、64年イリノイ生まれのMatt Wilson (ds) というNYで活躍する若手とのトリオ、これもまたヴィレッジ・ヴァンガードでの収録だ。1時間を超える演奏がネットで無料で聴ける!>「Lee Konitz, Dan Tepfer, Matt Wilson In Concert」■
こっちのほうが、じつにリスクを背負ったすばらしい演奏ではないか。コニッツ、別人だろ、いなないてるだろ。こっちをCD化しろ。

<track 060>
Birdsong / Paul Motian from 『Lost In A Dream』 (ECM 2128) 2010
Chris Potter tenor saxophone, Jason Moran piano, Paul Motian drums
モチアンの新譜!クリス・ポッターとのトリオ!ときいただけでアドレナリンが駆け巡る。ポッターの才能に気付かされたのはモチアンとのセッション録音において、だったし。・・・ジェイソン・モラン?それピアニスト?なぜプーさんではないのだ?・・・あ!そいえばジョー・ヘンリーの1曲目のピアニストだ。モランって、有名なの?とわたしのジャズブレーン、トップハムハット卿にうかがうと「もはや大御所クラスかも。ロイドのグループでもECMに登場してますよ」とのこと。ふうーん。
このECM盤は、ポール・モチアン作品集である。じりじりと音楽の骨格だけをしゃぶるのがよろし。ポッターに、もっとそこではじけろ!とか、モランに、そこのフレーズを引っ張ってくれ!、とか、聴いてはいけない。能のようにジリジリと詰めてくるポッターとモランの息を殺した旋律を聴け。これはもう、アイヒャーがディスカッションを重ねて作り上げたサウンドだな、と、思いきや、な、なんと、これはヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ収録なのである。
もっとスリリングで野放図な背水の陣のような演奏を聴きたかったが、これはこれで。ECMファンには6曲目がいつまでも耳にくりかえされる出来なのです。

<track 061>
Prelude: Light No Lamp / Joe Henry from 『Blood from Stars』 (Anti-) 2009
Jason Moran piano
ジョー・ヘンリーは『Scar』(2001)と『Tiny Voices』(2003)の2枚だけでいいです。もう、あの声、この声シビレるだろと誇示する歌いかたが鼻についてやだ。いつもいつも、こうもこうも、なにさま。でも、がまんして聴くおれ。マガジンで年間ベストに選出されてるし。冒頭のピアノ・ソロのトラックが異様によく聴こえた。それがジェイソン・モランだったとは、編集CDRに入れてからクレジットを見て気付く。編集CDR用のいいトラックだ。たぶん、まだわたしはジェイソン・モランを理解してはいないと思う。


<track 062>
Lady of the Lake / Rainbow from 『バビロンの城門 Long Live Rock 'n' Roll』 (Polydor) 1978
米国時間5月16日、「ヘヴィメタル界の北島三郎」と言われていたのは死亡記事で知りましたが、ロニー・ジェイムス・ディオが逝去。
レインボーの黄金期、78年1月27日の札幌中島スポーツセンター公演。将棋倒しになって女子高生がひとり踏み殺された事件に、高校1年のおれ、いた。津波に押されるようにステージに向かってゆくのがコンサートの儀式だったのか田舎者の悪ノリだったのか、絶対後者に違いなく、何人もが床に倒れている中を、足を踏ん張って立って倒れないようにするのがせいいっぱいで、もみくちゃに翻弄される圧力と怒声と酸欠で172センチあっても息をするのが困難で、おそらく、床に倒れたひとは、次々に腹や顔面や首などを、同時に踏まれまくっていたのだ。演奏は一時中断されたが、仕切り直しをするように再開した。
ロニー・ジェイムス・ディオ、リッチー・ブラックモア、コージー・パウエル。ベースは誰だったか忘れた。なんかこの事件以降、ハード・ロックには飽きたな。
もちろん、レインボーの最高傑作は『Rising 虹を翔る覇者』であり、とりわけLPのB面に収められた「Stargazer」「A Light In Black」は、このジャンルの最高傑作であることは論を俟たない。
17日の朝に、後部座席シートから04年に作った編集CDRがなぜか出てきて、6年ぶりに「レディ・オブ・ザ・レイク」を聴いて涙していたのだが、ちょうどそのときにロニーが天に召されたのだ。吐くほど繰り返して聴いて熱中した、中世様式美を備えた・・・、と、書いてて、ほんとか?と突っ込みを入れているが、コージー・パウエルの気分は酔いどれ千鳥足で痛快に叩きながらも、切ない旋律と間奏にハマる隠れ名曲だ。ロニーがおいらに聴かせてくれたのだろうと思う。合掌。
編集CDR『マーチング マーチ』
01. “frame” ? “cycle” ? “space” / 志水児王 SHIMIZU Jio
02. Happy Days / 大塚愛
03. Claude Debussy : Golliwogg’s Cakewalk / Zoltan Kocsis ゾルタン・コチシェ 1996
04. オンリーロンリーグローリー (album version) / Bump Of Chicken バンプ・オブ・チキン
05. Magneto And Titanium Man / Paul McCartney Wings ポール・マッカートニー
06. マーチング・マーチ / ハルカリ
07. MIDBAR / John Zorn Masada マサダ
08. Suite Espanola ? No.3 Malaguena/Arr:Narciso Yepes / Narciso Yepes ナルシソ・イエペス
09. 歌劇『トスカ』より「歌に生き、恋に生き」
10. Amor I Love You / Marisa Monte マイーザ・モンチ
11. Tea For Two / Bud Powell Trio バド・パウエル
12. Lady Of The Lake / Richie Blackmore Rainbow レインボー ★
13. フェザー feather / オダニミサコ・タタ Odani Misako ta-ta (小谷美紗子+玉田豊夢+二宮友和+田渕ひさ子+池田貴史)
14. Caroline Says / Marc Almond Marc And The Mambas マーク・アーモンド
15. ひとり ぼくはしなない / 詩:岡真史 作曲:高橋悠治 うた:中山千夏
16. 刻印の彫刻 / David Toop & Max Eastley デヴィッド・トゥープ
曲順、曲のクオリティ、選曲のロジック、三拍子揃った、それにしてもいい編集CDRだ。次々とNHKホールのステージに登場して音楽が奏でられる光景を思い描きながら。

<track 063>
Be Flat & Stay Flat / Jacob Anderskov from 『Agnostic Revelations』 (ILK(http://www.ilkmusic.com/)) 2010 ディスクユニオンで国内盤化■
Chris Speed(sax, cl), Jacob Anderskov(p), Michael Formanek(b), Gerald Cleaver(ds)
Agnostic Revelations 不可知論者の黙示録?、なんのこっちゃ。
おまえはサックス奏者クリス・スピードをどう思う、と、ニューヨークに住むジャズの神さまから問われる。パチョーラやジム・ブラック、イエー・ノーしか聴いてなかったけど。ややもすれば棒読み状態になる、独特なトーンでサウンドに彩りを加えるサックス奏者で、おいらの中では評価は頭打ちになっています、と、言ってみた。すると、わたしのジャズブレーン、トップハムハット卿は「ほんとうにそうでしょうか?」と謎かけのように最新作を机の上に出すのであった。げげげ、戦闘機械アニメBGMのパチモンのような、変なジャケ。こんなセンスのないジャケに・・・クリス・スピードは入っているのであった・・・。時代遅れのシンセ音とか打ち込みドラムンベースでごまかしていそうなジャケじゃないか。
ふむふむ。いつものクリス・スピードのトーンだ。ピアノ、ヤコブ・アンデルシュコフ、が、手堅く、・・・、手堅いどころではないな、このジャズ・ピアノ受難の時代に・・・、コンポジションの手の込み具合とその必然、自然な創造・・・、それに相応しいスピードのサウンドに含みを持たせるトーンのありよう・・・、クリーヴァーの知的かつスポーティーな叩きの繰り出し具合・・・・、おお、ベースもなにげにアグレッシヴに上下してるし・・・、なにか演奏の次元が違うのかな彼らは・・・。
気付いた!クリス・スピードのトーンこそが凶悪な武器だったのだ。マイケル・フォーマネクは、ティム・バーンとかで弾いてたベースだけど、こんなに上手かったっけ?リズムとトーンの変化、4者が入れ子状態になって、ひとときも弛まない(音自体はゆったりと変化しているだけに聴こえるかもしれんが)コンポジションをベースにしたインプロヴィゼーションの妙で見事に構成されているのだ。これは今年いちばんの名盤だ。
なにげに、ガルバレク、ジャレット、ヘイデン、モチアンが、今の彼らの力量で、この構成を再現してもらえないだろうか、と、思いつく。手触りは異なるが、この音楽はECMミュージシャンが開拓した領域にあるように思う。そして、ここでのスピード、アンデルシュコフ、フォーマネク、クリーヴァーはその自覚はあるし、演奏力もある。現代ジャズ・ファン、ECMファンはこの盤を聴かなければなりません。
お・・・。国内盤化されてるのか!さすが人民の味方だ。おれと同じことを感じている若者がおる。ディスクユニオンお茶の水ジャズ館の吉良さんという方のコメントが載っていた。
「NYからクリス・スピードとジェラルド・クリーヴァーを迎えた本作。この辺りの奏者が苦手な方にこそ聴いて頂きたい、イマジネーション溢れる現在進行形ジャズ! テンポ・ルバートを最大限に活かし、ソロの空間や自由度を飛躍的に高める手法は、ここ数年ポール・モチアンが開拓した領域。この奏法を最も積極的に取り入れているのがデンマークの若手で、例えばヤコブ・ブロなんかもモロにその部類。偏見なしに接すれば、そのサウンドの官能的で詩的な美しさと、ジャズの本質たるインプロヴィゼーションの可能性や美学が、新たなヴィジョンとして眼前に拡がるのが体験できるはず。本当に素晴らしい!」
おお、そうか。ピアニスト、ヤコブ・アンデルシュコフもギタリスト、ヤコブ・ブロもデンマークなのだ。ヤコブ・ブロ盤は

<track 064>
Bob Whites / Poolplayers from 『Way Below The Surface』 (songlines) 2008
Arve Henriksen (trumpet, vocals, electronics); Benoit Delbecq (piano, bass station) Lars Juul (drums, electronics), Steve Arguelles (Usine, delays, Sherman filter)
ふえええん。泣き出していいのか。08年に、フランスの天才鍵盤奏者ブノワ・デルベックは朋友スティーヴ・アルグエルと、ノルウェーのアルヴェ・ヘンリクセン(!)を迎えてこんなグループを結成していたのか。アルグエルはタイコは叩かず、ラース・ジュール■に打楽器の表記。
デルベックのトレードマークである痙攣プリペアード・ピアノ音は、ひとつの世界観なのだった。ブノワ・デルベックが90年代に率いていたリサイクラーズは当時のフランス・シーンの重要なユニットで、メンバーは朋友アルグエルに、ギターがノエル・アクショテでした。・・・な、なんと、アクショテは今年デイヴィッド・グラブスと来日して大友良英、秋山徹次、安田芙充央とリュック・フェラーリ作品を演奏したのですか(■、これは観たかった・・・。
04年にデルベックは、なんとサックス奏者マーク・ターナーとのユニットで『Phonetics』を出していて■、「天才は天才を認識するものだ」と騒いだおいらだったが、今度はヘンリクセンを迎え入れていたとは恐れ入った。アイヒャーECMはデルベックをスカウトして、はやくデルベックを世界標準化するように。でもなあ、ECMにはこういうエレクトロな表現を素で録るクールな視点が無いからなー。ぜーんぶアイヒャー・ワールドのドラマチック・ロマンチックに仕立ててしまうんだ。・・・それでもいい!アイヒャーに告ぐ、デルベックの単独名義作品を制作せよ。
で、この、プールプレイヤーズ。遊泳演奏団、なるほど泳いでいると認識することは理解の補助に。やはりジャズからの距離はある。というより、ジャズで聴いたら聴こえないタイプの音楽だ。痙攣する打楽器のようにプリペアドなピアノ音で構築してゆく時間軸で対話する官能である。ヘンリクセンのくぐもった尺八を体現するかのような窒息しそうなトランペットもたまらない。・・・かといって、これがジャズではないのかといえば、やはりジャズの一形態であるだろうし、・・・だいたいジャズ、ジャズと何回も書いてては、それぞれ異なるトーンや意味合いであるように、それじゃあ文意が伝わらないだろ、こうやって聴こえているのに伝えられない、・・・切ない片思いのようである。
ぐんまの山とともに泣く10ねんまえのきよちゃん。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
