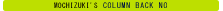|
|||
|---|---|---|---|
 |
|||
Chapter9.加古隆 |
撮影:望月由美 |
||
 |
|||
加古隆がニュー・カルテットを結成し全国縦断コンサートを行うというニュースが入ってきた。最近は映像とのコラボレーションやソロ・コンサートが多かった加古がグループを率いて活動するのは久しぶりのことで注目を浴びている。
加古隆は70年代から今日まで「TOK」と「SABU-KAKO」など幾つかの例外をのぞいては、自分の作曲とピアノの演奏一筋に歩んできた人である。1947年1月大阪の生まれで小学生の時にベートーヴェンの第5を盤が擦り切れるほど聴いてクラシックを知り、中学の時にストラヴィンスキーを通じて現代音楽にとりつかれる。ところが高校一年のときに先輩に誘われアート・ブレイキーの来日コンサートの生を聴きジャズに熱狂する。東京藝術大学、同大学院を経て1971年7月パリ国立音楽院に進み、オリヴィエ・メシアンに学んだことは良く知られていることであるが、私が加古隆を知ったのは豊住芳三郎とのデュオ『パッセージ』(1976年、TRIO)や富樫とのデュオ『ヴァレンシア』(1980年、TRIO)からである。1981年、日本に拠点を移してからの加古隆をピットインでソロや高木元輝や吉野弘志、村上ポンタ等々とのセッションで聴いていた。
そして1986年7月の昼下がり、某新聞の取材で加古さんのオフィスをお訪ねして興味深いお話を伺い、更にヨーロッパで収録してきたという未発表の音源を聴かせていただいた。丁度、前年に発表した『ポエジー』(SONY)に収録されたグリーン・スリーブスの変奏曲がニッカ・ウイスキーのCFに使われ大ヒットしていた頃である。2時間ほどの間、加古さんは物静かに、しかし情熱的にいかに音楽を大事にしているかを話してくれた。加古さんのお話は野口久光さんのことから始まった。ついこの間、野口先生がここに見えたの、野口先生も絵が好きだし僕も絵が好きでしょ。野口先生は来てもジャズの話なんかしないんですよ、ミュージカルの話ばかりで。当時、加古隆はオリジナルしか演奏しなかったそうだが、あるとき野口先生から、誰でも知っている曲を一曲でも弾くと印象に残るからグリーン・スリーブスなんか弾いてみたら、とアドヴァイスを頂いて弾いたらヒットしたのだというお話。美術に造詣の深い加古隆はその後もクレーや北斎などの絵画を触媒に次々と作品を創っている。因みに加古さんのお部屋にはグランド・ピアノの周りに何枚かの絵画のほかにLPレコードが沢山立てかけてあった。一番手前にビル・エヴァンスの『ポートレイト・イン・ジャズ』が飾られていたのが印象に残っている。日本に帰ってきたら知り合いのミュージシャンも少ないし、次第にソロが多くなったという。ソロが自分のピアニスティックな面とか体現したいものがストレートに出てくるし、だから面白いんだと云う。しかしグループでやることも好きだし大事にしたいとも語ってくれた。
加古隆のグループの原点TOK(Takashi Kako、Oliver Johnson、Kent Carter)についても話を伺った。TOKを知らないと僕のトリオの原型は分からないのだという。つまりTOKでは完全なフリーではなく、フリーでありながら4ビートと結びついているような微妙な関係の上に成り立っているのだという。だから、そうすると、フリーも4ッツもどちらも出来る人でないといけないという。そして一時期フリーもフォービートも出来る相手としてベースの吉野弘志と二人でデュオを始めた。吉野弘志も藝大出身である。 しかし加古はもともと三角形が好きなので、吉野弘志とのデュオからトリオにしたくなり古沢良治郎、日野元彦、村上ポンタ等々のドラムを入れて様々な三角形、つまりトリオを試みたという。因みに吉野弘志、村上ポンタとのアルバム『スクロール』(SONY)はSJ誌の1988年度日本ジャズ賞を受賞している。
話を戻してジャズと現代音楽との往き来についても話を伺った。加古さんは作曲家を目指して藝大に入ったものの一、二年の頃は中退してミュージシャンになろうと思うくらいジャズに熱中し、同じ藝大仲間の森山威男等と日々セッションを重ねていたという。しかし、大学の3年の頃、自分から一切ジャズを切ったという。現代音楽の作曲家になるにはフォービートに明け暮れていたのでは絶対両立しないと考えに考えたあげくの決断だったという。丁度この時期(1966年)ジョン・コルトレーンが初来日。知ってはいたが敢えて、聴きには行かなかったというがこの時の心境は大層辛かったに違いない。
次に何故パリ国立音楽院を選んだのかを伺った。藝大では三善晃が好きで三善晃に師事、三善晃の勧めとメシアンが好きだったことから1971年にフランスに渡り、直接メシアンに自分の作曲したしたものを見せてメシアンのクラスに入ったという。しかし、気がついたらヨーロッパでもいつの間にか又ジャズに戻ってしまっていたという。今度は4ビートではなく、フリーのミュージシャンと知合う。当時住んでいたパリの加古のアパートの近くにアンソニー・ブラクストン(reeds)も住んでいて、遊びに行ったらアンソニーから日本人のタイコだよってSABU(豊住芳三郎)を紹介されたのだという、「SABU-KAKO」の誕生である。ヨーロッパ時代に交流のあったミュージシャンを聞くと、ノア・ハワード(as)、スティーヴ・レイシー(ss)、アルバート・マンゲルスドルフ(tb)、ケント・カーター(b)等々フリー系のミュージシャンが大半を占めていた。丁度このころキースのトリオのコンサートもヨーロッパで初体験したという。「その頃のキースは凄かったんですよ、一部は完全なフリー、二部はモードもの、最近のキースとは違うの、フリーのキースは凄かったなあ、インパクトあったなぁ」と語ってくれた。因みにこのころのフリーを演奏するキースの映像はDVD『キース・ジャレット/アート・オブ・インプロヴィゼーション』(VideoArtsMusic)で見ることが出来る。
話の途中で、一年ほど前(1985年)にミュンヘンで録音してきたというテープを聴かせていただいた。2週間かけて、ある個人の方がホールを借りて録ってくれたという音はそれまで加古に抱いていたイメージを完全に覆すほど激しいフリー・インプロヴィゼーションで10数分の間釘付けになってしまった。ピシッと背筋の立ったタッチはまるで氷の彫刻の製作過程を見ているようで、初め鋭く削られた彫像が少しずつ溶けて徐々に滑らかで美しい光を放ってくる、そんなシャープさと穏やかさが同居しているような素晴らしい作品で、今あらためてインタヴュー・テープに入っていた音を聞き直しても新鮮である。しかしこの過激で美しい音源は加古隆のディスコグラフィーには未だに載っていない、いま思えば幻のテープであった。
最後に作曲家としての作業がインプロヴィゼーションにどのように作用し栄養となっているのかを伺った。ええ、大いに栄養になっていますよ、むしろそれが僕の個性になっています。例えば、作曲家の訓練を受けているということは、音を構築するとか、その一つのスタイルを見極めて行く作業とかを殆ど無意識の中でやってしまうから、演奏と作曲の訓練とは深い関連があるし、それが即興で弾いている時も、とにかく僕のスタイルになっているんですという。
今回、加古隆が久しぶりに編成したカルテットは加古のピアノに、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロというストリングスで構成されている。9月に発売されたアルバム『QUARTET』(AVEX)と同じ編成で、アコースティックで美しい音の世界を実現できるアンサンブルを求めて辿り着いたユニットだという。加古はこのグループでこの11月から札幌、東京、名古屋、大阪とコンサートを計画している。
10月31日の日曜日、たまたま見たTV番組に加古さんがゲストとして出演されていたが、加古さんの醸し出す雰囲気、物静かな佇まいは以前と全く変わっていないように見えた。
トレードマークともいえる帽子の下にいつも穏やかな眼差しを漂わせる加古さんだが、純粋に音と向き合う姿勢はカルテットという形式で新たな風景を描いてくれるのではないか、カルテットは11月12日の札幌から始動する。(2010年11月)
* 関連リンク:
http://www.jazztokyo.com/interview/v44/v44.html
望月由美:FM番組の企画・構成・DJと並行し1988年までスイングジャーナル誌、ジャズ・ワールド誌などにレギュラー執筆。 フォトグラファー、音楽プロデューサー。自己のレーベル「Yumi's Alley」主宰。『渋谷 毅/エッセンシャル・エリントン』でSJ誌のジャズ・ディスク大賞<日本ジャズ賞>受賞。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.