# 1229
�w�I�����^Solo Duo Trio�x
text by Hideaki Kondo
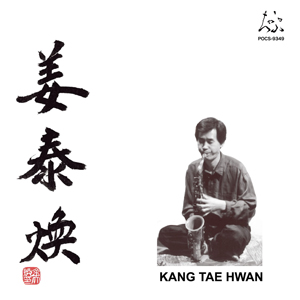
| ����Ղ���Ճ��R�[�h�^���j�o�[�T���E�~���[�W�b�N POJE-9002�iLP�Q���g�^250������j �艿4,800�~�i�ō��j |
Side A
01. Kang+Ned+OtomoTrio
�@�I�����ias�j&Ned Rothenberg�ib-cl�j&Otomo Yoshihide�iturntables�j
�@1994�N8��30�� ���R�s�y�p�[�����h�ɂĘ^��
Side B
01. Kang Solo I
�@�I�����ias�j
�@1994�N9��1�� �R�����h�z�s Cafe Amores�^��
02. Ned Solo I�i�����\�j
�@Ned Rothenberg�ib-cl�j
�@1994�N9��1�� �R�����h�z�s Cafe Amores�^��
Side C
01. Kang+Otomo Duo I
�@�I�����ias�j&Otomo Yoshihide�iturntables�j
�@1994�N8��30�� ���R�s�y�p�[�����h�ɂĘ^��
02. Kang+Ned Duo I
�@�I�����ias�j&Ned Rothenberg�ib-cl�j
�@1994�N9��1�� �R�����h�z�s Cafe Amores�^��
Side D
01. Ned Solo II�i�����\�j
�@Ned Rothenberg�ias�j
�@1994�N9��1�� �R�����h�z�s Cafe Amores�^��
02. Kang+Ned Duo II�i�����\�j
�@�I�����ias�j&Ned Rothenberg�ias�j
�@1994�N9��1�� �R�����h�z�s Cafe Amores�^��
���������E�̕����Փ˂Ƃ��̒����̈��Ƃ��āA�d�v�Ș^���̂ЂƂ�
1994�N�A���R�y�p�[�����h�ƁA�R���h�{�J�t�F�E�A�����X�ɂ����郉�C���^���B���Ƃ��Ƃb�c�Ń����[�X����Ă������������A����̂Q���g�k�o���ɂ������ĂR�Ȃ��lj����^���ꂽ�i�A���A�b�c���^�ȂP�Ȃ������j�B�I�����𒆐S�ɑI�Ȃ��ꂽ�b�c�ɔ�ׂ�ƁA�I�����^�l�b�h�E���[�[���o�[�O�^��F�ljp�̂R�҂ɂ������ł���_����������Ă���B
�p�����ÎE����R�������̑������؍����������A1990�N�̖��厩�R�}�����ɂ���āA�}���ɖ��剻���i�B����Ɍĉ����邩�̂悤�ɁA���{�̈ꕔ�W���Y���f�B�A���I���������グ�͂��߁A����������b�c�̃����[�X���������A������Ƃ����I�����u�[���ƂȂ����B�؍��ݖ�̌|�p���y�ɂ�����ŏ��̕����Փ˓_�������̂ł͂Ȃ��낤���B�I��90�N�㏉���̎��_�ŁA�������^�̎��X�ȌJ��Ԃ��Ƃ��̕ω��Ƃ����T�b�N�X�Ƒt�̃X�^�C�����m�����Ă����B���{�̓s�߉A���ɋ߂��\����^�[�Q�b�g�m�[�g�ɔ����K�ŃA�v���[�`���鉹�^�𑽗p���Ȃ���A��������X�ɌJ��Ԃ��A���y�̒��ɓ���B���̉��y�X�^�C���́A�؍��̃V���[�}�����y�Ƌ��ʂ���i*CD�w���҂ւ̛ދV�xvicg-60391�ȂǎQ�Ɓj�B
�@�{�k�o�^�������A�j���[���[�N�𒆐S�Ƃ����������y���������Ă����B�ǓI�ƌ�����ɗ�������ł����t���[�W���Y�^�C���v�����B�[�[�V�����ɍēx�����͂�^�����̂́A�i����͓e���p�Ƃ��āj�j���[���[�N�������B�{�^���ŁA�j���[���[�N�Ŋ��Ă������[�[���o�[�O���I���琂���B�}���`�t�H�j�b�N�Ȃǂ̓�������t�@��\���ɗp����I�ƃ��[�[���o�[�O�����A���̎g�p�������Ⴄ�B���̐H���Ⴂ�́A�����̑����V�[���̏k�}���B�����̒��҂ɂƂ��āA�I�̑t�ł�t�H������ǐՂ������Ɉӎ��Ɏc��͕̂\�����낤�B���̓_���ꌾ�Ő�������ɁA���́u�����v�Ƃ������t���g�������Ȃ�B�����ɁA���ɛI�����Ɠ����̃j���[���[�N�V�[���������Ă����Ƃ���́u�����v�̈Ӗ��̍���������Ă���B�l�Ԃ̔F�m�I�X�����炵�āA���Ƀt�H������ǂ����͔����������B�������A���t�Ƃ̓t�H��������ړI�Ƃ��ĉ��t�Ɍ������Ă��邩�B�����̉��t�Ƃ͂���������̂ł͂Ȃ��낤���A�u�����̒�����o�Ă�����̂��������t�������v�ƁB���̏u�Ԃɍł��ӂ��킵�������鎖�B�����Ɂu�����v�ł���K�R������̂ł���A����͕ʂ̉��y�V�[���ŕ\�������u��艹�y�I�Ɂv��u�̂��悤�Ɂv�Ɠ��`�ł͂Ȃ����B���̎��_�ŁA�u�����v�Ƃ������t�̃V�j�t�B�G�́A���Ɂu�����ʼn��t���鎖�v���痣���B�X�ɂ��ꂪ���t�u�\���v�̂����ł͂Ȃ��A���͈̔͂�傫�������ĉ��t�u�s�ׁv�̂����ɁA�Ƃ��������ɓ˓�����_�ɂ����āA���A�W�A�̓��Ȍ^���y�ɋ��ʂ�����I���o�������オ��i���������Ҍ��́A���A�W�A�̌|�p���y�����m���y�ƏՓ˂���x�ɉ��x���ċN���鎖�ɂȂ�j�B���̈Ӗ��ɂ����鑦�����ɂ����āA�؍������͑������x���ɒB�������y��L���Ă���B�����āA�I�������o�ꂵ���B�؍��ɂ�����ŏ��̂ЂƂ肪�A�{���˔������l���ł��������͍K�^�������B�Ƒt��{�̂Ƃ���I�����̘^���Ƃ��Đ�Ƀ����[�X���ꂽ��i(mobys-0011)�����荢��ł�������������A�{��͓������I�����̑�\��ƌ���Ă����悤�ɋL������B�l�I�Ȑ��E�g���b�N�́A�k�o�P�̂a�ʁ�Kang Solo �T���B���̉��t�Ɋ܂܂��O�ρA���ρA�����Ă��̈Ӗ��̏�ł̈����A������x����R���e�L�X�g�������ł���A80�N��ȍ~�̉��Ă̑������y�V�[���Ɍ����Ă������̂�������̂ł͂Ȃ����낤���B���A�W�A�̍ݖ�̌|�p���y�j�ɂ����āA���邢�͑��������E�̕����Փ˂Ƃ��̒����̈��Ƃ��āA�d�v�Ș^���̂ЂƂƎv���B�i�ߓ��G�H�j
�ߓ��G�H Hideaki Kondo
�M�^�[�^���i�t�ҁA���y�f�B���N�^�[�A�^���G���W�j�A�A�r�V���b�v���R�[�Y��ɁA�������y�A���T���u���uExperimental improvisers�f association of Japan�v���[�_�[�B��ȍ�i�Ƃ���CD�w�A�W�[���x�iPSF Records, PSFD-210�j�A�ߓ����ɏ��Ёw���y�̌����x�i�A���e�X�p�u���b�V���O�j���s�\��B
 1.31 '16
1.31 '16
�Ǔ����W
�|�[���E�u���C Paul Bley
![]() �F
�F
#1277�w��F�ljp�X�y�V�����r�b�O�o���h�^���C���E�A�b�g�E�V�h�s�b�g�C���x(�s�b�g�C�����[�x��) �]���R��
#1278�wDavid Gilmore / Energies Of Change�x(Evolutionary Music) ��Օ�
#1279�wWilliam Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989�x(NoBusiness Records) �֓���
#1280�wChris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality�x(Clean Feed) ���c ��
#1281�wGabriel Vicens / Days�x(Inner Circle Music) �}�C�P���E�z�v�L���X
#1282�wChris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality�x (Clean Feed) �u���[�X�E���[�E�M�������^�[
#1283�wNakama�^Before the Storm�x(Nakama Records) �דc���k
![]() �F
�F
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
�������ɂ��郊�A���E�W���Y�@�|�@�j���[���[�N����̃��|�[�g
by �V�X�R�E�u���b�h���[ Cisco Bradley�C���c�� Takeshi Goda, ꎓ��� Akira Saito & �@���ߖ� Rema Hasumi
#10 Contents
�E�g�����X���[���h�E�R�l�N�V���� ���c��
�E�A�ڑ�P�O��F�j���[���[�N�E�V�[���ŐV���C���E���|�[�g�������[�X���
�V�X�R�E�u���b�h���[
�E�j���[���[�N�F�ϗe����u�W���Y�v�̂���
��1��@�`���ƑO�q���Ȃ����@�|�@�A�i�C�X�E�}���B�G���@�@���ߖ�
���̌����镗�i
�uChapter 42 �쓈�N�Y�v�]���R��
�J���T�X�E�V�e�B�̐l�Ɖ��y
#47. �`���b�N�E�փf�B�b�N�X���Ƃ́g�I�[�j�\���W�[�h:�`���[���[�E�p�[�J�[�E�q�X�g���J���E�c�A�[ �qPart 2�r �|���m�q
�y������̒����ǂ���`�F�b�N
#263 �w��F�ljp�X�y�V�����r�b�O�o���h�^���C���E�A�b�g�E�V�h�s�b�g�C���x (Pit Inn Music)
#264 �w�W�����W���E�P�C�W�� ��t�L�� ���c�Ǖv�^���~�i���g�x (Amorfon)
#265 �w�����ƕv���C�W���O�E�T���E�o���h�^NY Groove�x (Ratspack)
#266 �w�j�R���C�E�w�X�E�g���Ifeat. �}�������E�}�Y�[���^���v�\�f�B�`�n���}�[�X�z�C�̈�ہx (Cloud)
#267 �w�|�[���E�u���C�^�I�[�v���A�g�D�E�����x (ECM�^���j�o�[�T���~���[�W�b�N)
�I�X���Ɋw��
Vol.27�uNakama Records�v�c������
�q���E�z���V���N�̊y�ȉ��
���S�wPaul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop�x (Steeple Chase)
![]() �F
�F
#70 (Archive) �|�[���E�u���C (Part 1) �{���L�`
#71 (Archive) �|�[���E�u���C (Part 2) �{���L�`
![]() �F
�F
#871�u�R�W�}�T�i�G=���ܗ���=��삱���� New Year Special Live!!!�v����N�k
#872�u���̂悤�ɂ�������Ȃɂ��̂� Things to Hear - Just As�v������
#873�u�f���B�b�h�E�T���{�[���v�_��G�Y
#874�u�}�[�N�E�W�����A�i�E�W���Y�E�J���e�b�g�v�_��G�Y
#875�u�m�[�}�E�E�B���X�g���E�g���I�v�_��G�Y
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.