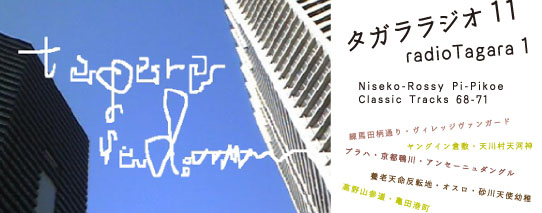
噛むんとフニャンフニャンだのトイレの神さまだの渡り廊下走り隊だの連日有線やTV画面で視聴せざるをえないわたしの労働環境の早期改善を。わが国のジャズ・ファンはこのところ、マーク・ラパポートのマガジン連載「じゃずじゃ」を失い、次いで杉田宏樹と大村幸則のスイング・ジャーナル誌の輸入盤紹介ページを失ったことになる。CDジャーナル誌のオールジャンルをオープンに並べた中でのジャズ国内盤の並び具合および輸入盤紹介、MJ(無線と実験)誌のCDレビュー、ディスク・ユニオンの新宿店と御茶ノ水店の新譜棚、ミュージックバードのジャズチャンネル、という残されたアンテナでなんとかジャズ・ファンをやってゆかなければならない。
→おいおい、JazzTokyoはどうなったんじゃい(編集部)!
「思い詰めは5秒にある」
お年頃になった子どもたちに「レンアイごととは、思い詰めにこそ価値があるんだ」とだしぬけに説教をたれても、ピンときてくれないのはなぜだ。「いいか、芸術というものも、思い詰めるところから始まるのではないか?・・・」と、完全勝利を確信したかのような投げかけに対しても、「いみわかんなーい!」「おとーちゃん、オフサーイド!!!」と、声をあげられるだけ相手にされていることに安堵していていいのか、おれ。・・・オフサイド?
マンフレッド・アイヒャーのインタビューで、沈黙の重要性、ひいては沈黙を理解するためには孤独が必要だとまで言ってのけていたことにわたしは注視する。ECMレーベルのCDには、すべからく冒頭に5秒間の沈黙が用意されている。この5秒間の沈黙体験がECMの重要なメッセージでもある。
→ところで、我が国では、Manfred Eicherはオフィシャルには「マンフレート・アイヒャー」と現地発音に限りなく近い表記をしている。貴殿は何故に、「マンフレッド」を採用しているのだろうか?「マンフレッド・ショーフ」「マンフレッド・マン」に準拠?
さて、1100枚にもなるECMレーベルの全貌を知ることができる『ECMカタログ』(河出書房新社)が、いよいよ7月13日に発売されることになった。廃盤も含めての完全レビュー、データ掲載は世界初である。
わたしは「読者に助言する、ECMの迷宮に手を伸ばしてはならない――。■http://homepage3.nifty.com/musicircus/ecm/ecm_guide.htm」という立場であるから、このカタログが攻略本の機能を果たしてしまう事態も危惧するところ、ECMがそんなカタログ1冊で俯瞰されてなるものか、おれだってまだ何にもわかっちゃいないんだ、まだまだ謎だらけなんだぞECM、とも言いたい。関連ディスク、ガルバレクのトラッド盤、エレベーターの男ではディス・ヒートの作品が関連作、ラスク3、デヴィッド・バーンのMusic for The Knee Plays、などなど、ECMミュージシャンの重要な他レーベル参加作の樹海がひろがっているのである。欠番捜索もしなければならない。
ともあれ、すべては『ECMカタログ』からはじまる。全国のECMファンは使用版、永久保存用、別荘など緊急避難場所用で頭がいっぱいかもしれないが、所属する自治体の図書館にリクエスト・カードを出すことも忘れてはならない。
こないだ座間裕子さんが来日した折に知った現代音楽作曲家マイケル・ピサロさんが、英国WIRE誌6月号の特集記事になっている。
福島恵一さんのユリシーズ誌創刊号(昨年末に発売されている)のディスクレビューの1枚目がマイケル・ピサロの作品であった。
インカスの再来と言われている英国の即興/現代音楽レーベルAnother Timbre。ここの主宰者は他レーベルのレコメンド作品をサイトに掲げてもいるという実に見上げたスピリットの持ち主であるけれども、そこでもマイケル・ピサロ作品は言及されていた。
わたしも本コラムで扱った文章を英訳(
■http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20100529)してもらえた契機から、海外のレコード会社とも通りが良くなったこともあるけど、上記3つの動向の一致は、やはり記しておきたい。

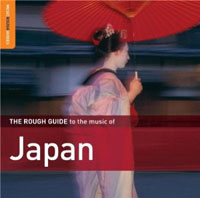
<track 068>
東京節(添田さつき作詞・原曲マーチングスルージョージア・アメリカ民謡) / あがた森魚 from 『タルホロジー』 (ブリッジ EGDS-26) 2007
東京節(パイノパイノパイ)を知ってはいるけど、どのヴァージョンで耳にしていたのだろう?
『ラフ・ガイド・トゥ・ザ・ミュージック・オブ・ジャパン 第2弾』(■http://www.respect-record.co.jp/discs/res141.html)、イギリス人音楽ジャーナリストのポール・フィッシャーが日本の音楽を紹介するコンピレーションのすばらしさだ。第1弾(■http://www.respect-record.co.jp/discs/res28.html)はベストセラーになり、収録アーティストは海外公演も行なった、という。このイギリス人によってコンパイルされる日本によって日本を知る、他者によって見出される構造という知見はここでも適用される。
笠置シズ子の「東京ブギウギ」にカッコいいと、何年かかってこの感興に至ったのか!と、耳を新しくしていたけど、あがた森魚がカバーした「東京節」、久保田麻琴のプロデュースによるブラジルのリズム・アレンジ、演奏の良さと相俟って、まさにアナーキー・イン・トーキョーに聴こえる。この動かしがたい、精神がパンクでジャズである演奏の完成度。時代を超越した人間国宝ヴォーカリストあがた森魚による「東京節」、細野晴臣と鈴木慶一もヴォーカルをとっている、日本音楽史の最強ヴァージョンだろう。
あがた森魚のアルバム『タルホロジー』の冒頭に収録されていたのをすっかり忘れていた。多くのセルフカバー曲を聴いて、「初出のオリジナルのほうがいいなあ」と、相変わらずの偏狭な耳であまり聴いていなかったのだ。大変すいませんでした。


<track 069>
同じ月を見てた(作詞・作曲:松本素生) / GOING UNDER GROUND (Victor Entertainment) 2004
You tube ■http://www.youtube.com/watch?v=BIoFW39qI0Abr />
とてもJポップとは思えない喚起力を持つジャケにも一票。
クラシックのコンサートに通いはじめてから、これは前原幹事長に「おれは50さいになってからECMニューシリ−ズに取り組む」と宣誓した準備運動もしくは助走と言ってもいいのであるが、なにせJポップがほとんど聴けなくなってしまったのだ。なんなの、この現象。ミスチルとミシェルドネダ、とか、アジカンとポールモチアン、とか、ふつーに聴けてたのに。ミスチルもアジカンも、曲をとばすくらいになってしまった。いま聴けるのはラドウィンプスと世界の終わりだけだね。たぶん、Jポップという呼称は、ミスチルが「旅立ちの唄」で、きみが大好きだった歌が街に流れる、のはミスチルのヒット曲だ、と、自ら定位した07年10月に時効を迎えたのだ。小沢健二の復活ツアーも、そこからの現象だ。だからミスチル桜井がラドウィンプスの「有心論」をカバーするなんてのは、宿命的な後退戦、もしくは徳永英明にしか思えない。
ゴーイングアンダーグラウンドはデビューから聴いていたバンドだけど。このPVを視聴するたびにおいらは泣いてしまうなあ。演奏のスピード感と、挿入される列車からの高速風景の効果。たかだかハッピーエンドのクリシェにまみれたレンアイばなし、Jポップは愛だの恋だのしか歌わないのはどうして?と15ねんまえの8さいの娘にきかれたおやじであるけれども、日常の一瞬に永遠を見つめずに何の人生なのか。
このPVに対して、以前、これはミスチルの「くるみ」をベースに小沢健二の「ぼくらが旅に出る理由」のスピリットをアダプトしたものではないだろうかと問いかけたことがある。これに対して制作者から丁寧なメールをいただき、参照関係は無いことが確認された。このPVの男性はバンドのベーシスト石原聡で、女性は俳優の平良千春(たいらちはる・1977〜)、じつにいい演技と写真だ、多分においらの過剰な感情移入によるものだけど「アレックスフォンシュリッペンバッハを観に行くのだー」などなど恋愛の危機を何度もおれも乗り越えたものだ。
JポップのPVのツートップがこれとミスチルの「くるみ」(Dailymotion ■http://www.dailymotion.com/video/x2s43t_mrchildren_music)で、「くるみ」の中でMr.ADULTSという架空バンドが登場するが、「同じ月を見てた」のベーシストの20年後がこのベーシストなんだな。ベーシストは生活のために楽器をすてて八百屋になっていたのだな。おんなはみんなあんなもんだ。いい話じゃないか。


<track 070>
Palhaco / Egberto Gismonti from 『Alma』 (Odeon EMI) 1987
ECMクラシックトラックス第2弾(第1弾はtrack 065のOceanus)は、ジスモンチの名曲「パリャーソ」のピアノ・ソロ・ヴァージョン。
87年にブラジルのオデオンEMIからリリースされたジスモンチの『Alma』。六本木WAVEで見つけて、まだLPでしか入手できなくて、全国のECMファンに聴かせたくて、スイングジャーナル誌に「こんな美しいものはないので、カセットに録音してあげますから連絡ください」とECMファンクラブとしてお知らせを出したことがある。著作権もなにもあったもんじゃない。音楽愛だ。日本各地の6・7人から連絡があって、わたしは結婚したばかりのよしみちゃんがLPレコードの中にあった楽譜をコピーしてそれをパッケージにして送っていたかわいい姿に人生の頂点を感じていたのだった。
91年(たしか)に来日したときは、長野県松本市でピアノ公演とギター公演があった。招聘はタッド・ガーフィンクルさんだった。今でもそのポスター持っている。松本行きのバスに乗って、おいらはウォークマンで、まだCD化されていなかった廃盤『解体的交感』(阿部薫・高柳昌行デュオ)、当時は10まんえんぐらいした、のテープを爆音で聴きながら、(ジスモンチも解体的交感も、この世のものとは思えない美しさなのに、それを理解しない世界は不当だ!)と孤独なリスナーであった30さい、当時の無理解なリスナーは消えてしまった、今のリスナーならこの美しさを自然に受け入れるだろうと思う。
この作品はその後ジスモンチが数トラック加えて、自己のレーベルCarmoで再リリースした。ECMのサイトを通じて購入できます。リマスタリングされたのか、音がシャープになっています。わたしは音が柔らかい旧盤のほうが好みですが。6月6日のECMカフェで、終了後のお客さまお見送りのBGMにこっそりとこのトラックをかけました。

<track 071>
January / Ornete Coleman from 『Who's Crazy』 1979
Ornette Coleman (as,vln,tp)
David Izenzon (b)
Charles Moffett (ds)
練馬区の図書館から何度も借りてはオーネットのヴァイオリンに戦慄を覚える1曲。ヴァイオリン、トランペット、アルトと持ち替え、不穏はなはだしいトリオ演奏になっている。そして何とも音楽的!4分23秒。
ブルーノート盤『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン』65年ライブ録音、は、SJ金賞も取った古典扱いになっているけれど、この絶頂トリオが翌年に映画のサウンドトラックとして制作した『Who's Crazy』スタジオ録音のほうが不穏度、ヒリヒリ度ともに勝っている。というか、前者はちっとも良くないだろ!ちょいとジャズ史を書き直してくださいませぬか。
この録音は79年になってフランスのIRIレーベルから発表された。フリーダム・レーベルから再リリースされたのは83年か。94年に徳間ジャパンから国内盤CDになっている。青木和富さんがライナーで書いている「アイゼンゾンはゲイリー・ピーコックと並ぶ60年代フリージャズエイジが生んだ素晴らしいベーシストである」に相応しい演奏だ。
青木さんはアイゼンゾンの消息を伝えている。「アイゼンゾンは、オーネットがニューヨークにのぼり『ファイブ・スポット』に出演、話題をにぎわした頃、それに感動してその場で直接オーネットに共演を申し込み、共演者になってしまったという経歴の持ち主。その後、子供が小児マヒになり、そのためにアイゼンゾンは、音楽活動を半ば断念し、子供の看護のための専門知識を得るために大学に入り直すという人間であった。70年代半ばになって、一時再びオーネットと共演、他のアーティストと共演もしているが、だが翌年この好漢は、あっけなく他界してしまった。自宅近くの路上で、自動車泥棒を追っかけていたところ、急に心臓発作を起こして、という話だったが、いかにもアイゼンゾンらしい最後ではなかったろうか。」
アイゼンゾンはECMでポール・モチアン・トリオ『Dance』(ECM 1108)1977年録音、を残しています。あれま!このトリオのライブ音源がどこぞにあるという・・・■http://inconstantsol.blogspot.com/2008/12/paul-motian-trio-live-in-bremen-139.html、これは手に入らないものだろうか・・・。
→アイゼンソンはカール・ベルガーの主宰するCMS(Creative Music Studio)とも深く係わっていて、今年の春からスタートしたCMSの予約者
限定のアーカイヴのCD化第1弾でソロが公表されます。これはJazzTokyoのHot Line/International でお知らせした通り:
● Now CMSがCD予約購買者を募集
NYウッドストックのCMS(Creative Music Studio=カール・ベルガー主宰)が輝ける70年代〜80年代の録音アーカイヴ (約400時間)のCD化にあたり、予約購買者の募集を開始した。Planet Arts レーベルを通じてリリースされるアーカイヴのCD購入は予約者に限り頒布される。「CMSアーカイヴ・セレクション・シリーズ」としてリリースされるCDには通常3つの異なるセッション(アーチストまたはユニット)から厳選されたトラックが収録されている。セレクションにあたってはミュージシャン(物故者の場合はその関係者)と合議が尽くされ、慎重なディジタル化作業が行われるので年間リリース予定は2枚に留まっている。今春リリース予定の第1巻は、(1)デイヴィッド・アイゼンソンbのソロとイングリッド・セルッツォ、カール・ベルガーとのトリオ、(2)オリヴァー・レイクとCMSオーケストラ、(3)フォディ・スサ・ムソとマンディンゴ・グリオ・ソサエティ(ハミッド・ドレイクとアダム・ルドルフをフィーチャー)。編集部註:Dr.ベルガーからは約束のサンプル盤がまだ送られて来ない。予約数に満たなかったのか、予想をはるかにオーバーしてしまったのか。(編集部)
Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
