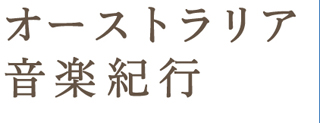|
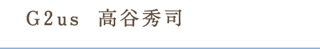 |
Vol9 | |
 |
|
昨年、オーストラリアの国の要請で、シドニーの郊外Kirraweeというところで、数多くの講演とパフォーマンスを展開した。
公立の中高一貫のハイスクール、Kirrawee High Schoolが中心であった。
日本でいう視聴覚講義、芸術鑑賞のアクターとしてエンターテインメントを展開した。開催に際しては、NBCA(Nihon Brain Center Australia)の方々にお世話になった。
タイトルは「日本文化の真髄を伝える」であり、その内容は、第3回で詳述した。
その縁あって、オーストラリアの若い方々(20歳前後)と日本で、話す機会が多い。・・・日本に憧れて、滞在や留学をしている人も多い。
皆さん、音楽にかかわる方々である。音大を出たばかりの人や、ギター・クラフト(ギターを製作する学校)を出て、ギターのリペアーやギター作りをしている人、ミュージッシャン志望で、勉強中の人といろいろだが、音楽が好きで、音を楽しむことを知っている人たちだ。
ある程度、音を極めた人といってもいいかもしれない。
「やっぱ、ジミ・ヘンドリクスいいですね。スケールが違いますよ。」という言葉に出くわして驚くことがある。10代の人たちから出てくる言葉とはとても思えない。(時代が古いという意味で)隔世の感があるという意味で。
ジミ・ヘンドリクスとは、1960年代後半に活躍したギタリストである。勿論、私は、不出生のギタリストとして尊敬している。カテゴリィーとしては、立派なJAZZだ。
彼を、どのくらい知っているのか聞いてみた。
「ジミ・ヘン(ジミ・ヘンドリクスを略して)のどこが好きなの?」
「ギターも歌も全てが、好きです。」
かなりいい線いっている。
「他に好きなミュージッシャンは?」
「マイルス・デイヴィス、ジャニス ジョプリン、BBキング、第一期ジェフ・ベック・グループ、ウエス モンゴメリー・・・・」
出てくる。出てくる。私の青春だ。
「最近の音楽は、聞かないの?」
「えっ・・聞くことは聞くけど、なんかちょっと頼り無くて・・・」
「トランスとかは?」
「面白みにかけますね。やっぱ、ジミ・へンしかないっすよ。最も新しい音じゃないですか。」
19歳のオーストラリアの少年の瞳がきらりと輝いた。
生まれる前に活躍していたミュージッシャンに、この上ない賛辞を送る少年に乾杯・・・。
ジミ・ヘンドリクスとは、知る人ぞ知る、電気楽器(ギター)に、最初に魂を吹き込んだ人。存在するだけで意味のある人。存在そのものが偉大であった人。
エレキギターを演奏することを生業とするほとんどの人に多大な影響を与えた。音楽へのアプローチそのものが奇想天外であり、創造的であった。そして深遠であった。
あの危険なブライアン・ジョーンズ(ローリング・ストーンズの元メンバーで変死を遂げた)にモンタレー・ジャズ・フェスティバルで、「もっとも危険な匂いを放つ男」と言わせた男。それが、ジミ・ヘンである。
他の、オーストラリアの若者も、異口同音に、ジミ・ヘンを褒め称える。40年も45年も前の音楽が、ミュージッシャンが、これほどまでに若人の心を捉えて離さないのはなぜなのだろう?
彼らの心の中に何の違和感もなく、入っていき、受け止められている。なぜなんだ・・・。
ロックやJAZZという音楽自体が、本質的に変質を成し遂げられないのか。
数限りない模倣を繰り返してきた結果、自己矛盾を起こし、自己崩壊に至ったのか?その結果、最も原始的な本質のみが崇拝されることになったのか。
確かに、ここ10年、一部の識者から、JAZZやロックの創造性の限界が叫ばれて久しい。
リズムにしても、メロディーにしても、コード進行にしても、あるいは奏法にしても、行き着くところまで行き着いた感はある。
では、これからのロックに行き場はないのか?どこにも行くあてはないのか。本当にそうなのか?そんなことはない。
今まで、ロックは、流行ると言う事に重きを置きすぎた感がある。とくに音楽ビジネスにおいては、流行るということを受容課題に置きすぎた感がある。ビジネスである以上仕方がないといえばそれまでなのだけれども。
流行るために用いられる手練手管が、手段ではなく、音楽制作の目的そのものにすり替ってしまったという問題がある。
この愚を繰り返すことによって、ますます音楽創造ということから無縁になってしまうという、皮肉な悲喜劇(・・・)を生み出してしまった。
このことは、悲劇であると同時に、喜劇でもある、なぜなら、音楽を創る側は本心では、新しい音楽を生み出すことを求めていたのだから。
では、これからどうすればいいのか。この暗闇を切り開く活路はあるのか? ある。
音楽家が本来持っている内面的な必然性に耳を傾けてみることである。それも。本気になって耳を傾けてみることである。
誰しも音楽家である以上こういう表現をしたい、あるいはこういう表現をせねばならないという、表現者、音楽家としてのやむにやまれぬ内なる叫びに正直になることである。
私は、もう一度、純粋な音楽創造の原点、内なる叫び、命の輝きにしたがってみます。
あのオーストラリアの少年のきらりと輝いた瞳にかけてみたい・・・。
 |
 |
|---|
高谷秀司(たかたに・ひでし)
1956年、大坂生まれ。音楽家、ギタリスト。幅広いジャンルで活躍。人間国宝・山本邦山師らとのユニット「大吟醸」、ギター・デュオ「G2us」でコンサート、CDリリース。最新作は童謡をテーマにしたCD『ふるさと』。2010年6月から約1ヶ月間、オーストラリアから招かれ楽旅した。
www.takatani.com
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.