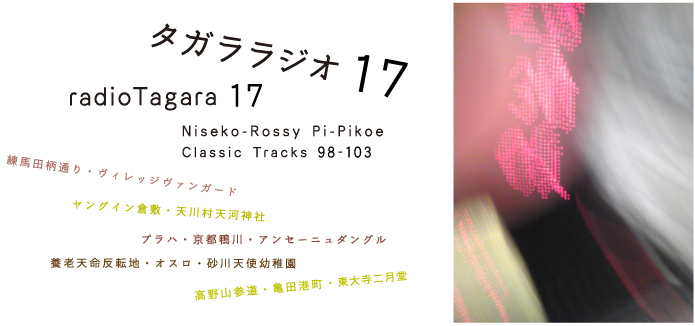
プーさんから元気だというメールが入る。10月15日に、ようやく家に帰ることが許されたのだそうだ。「手術が成功したらしくこの世に戻ってきたが」なんてフレーズがあると、そんなにひどかったのか!さすがに音楽の神さまはそれは許さないだろ!
9月27日に、治療費をケアする目的のコンサートが開かれていた。>Jazz Tokyoライブレポート
「入院直前まで録り続けていたソロがCD25枚分あって、病院で聴いているうちにまたアイディアがわいてきたのであと3・40時間録音して、それらをCD20枚くらいに圧縮しようと思っている。Manfredが欲しいと言っているソロ二、三枚はそこには含まれてこない。そのあと、Thomas Morgan(bass)、RJ Miller(drums)、Todd Neufeld(guitar)、Chris Speed(tenor sax)との録音を考えているが、ただその時オレに聴こえてくるサウンドにそぐわなければ、入れ替えはあり得る。」(菊地雅章)
おおお。元気そうだ!これらの音源が聴けると思うとおいらもおちおち五十肩だの言ってはいられない。「プーさん、モーガン、モチアンのトリオによるECM録音を聴かせてもらったけど、あれは素晴らしいぜ!ことに後半4トラックに到達している感覚は、ジャズだのクラシックだの言う世俗の感覚には止まっていられないもの、これのリリースをもたついているアイヒャーはオカシイ!」とメールしたら、「アレをリリースするのに極力反対していたのはオレだ!」との返信・・・。おおっとー、ニセコロッシとプーさんの耳の見解が分かれましたー!思わず練馬の夜空に向かって場内アナウンスをしたくなるような展開だ。
6月のポール・モチアン・トリオ2000+Two、ヴィレッジ・ヴァンガード公演、コニッツやヘイデンやナベサダが観に来ていた、というから、その3にんとの共演もぜひ聴いてみたい!え?クリス・スピードとの共演も考えているんですか!・・・なんてやりとりをしていた以来、4ヶ月ぶりの世界のキクチの健在をまずは祝福したい。
アイヒャーの耳のハートを射抜いたプーさんが自宅で録ったというピアノ・ソロ、これはまだ聴いていない。リリースされていないので当然だが。アイヒャーの手にかかっていないという点でも、調理前のレア肉ではないけれど、すごいものが録られているのではないか、聴いても、一瞬何かわからないような、どう評価していいかわからないような(そもそもすぐに評価が浮かぶものはろくなものではない)、そういう出来事こそが世界の風景を揺らすことができるわけだが、そんな予感がする。3年も寝かせてんじゃねーよ、ECM。
そのさらに先のピアノ表現に当然プーは向かっている。
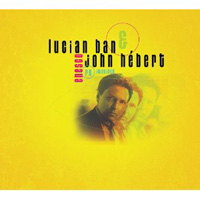
<track 098>
Aria et scherzino / Lucian Ban & John Herbert from 『Enesco Re-Imaged』 (Sunnyside) 2010
助けてほしい。響きの海による、世界の創造だ。と、書き始めるのは1曲目だ。
ルシアン・バン、69年生まれ、ニュー・ヨークで活動しているルーマニア出身のピアニスト。ジョン・ハーバートはニューオリンズ生まれルイジアナ州のベーシスト(ケイジャンなのでフランス的な名前綴りになっているそうだ)。
ルーマニア出身のバンが同じルーマニア出身の作曲家ジョルジェ・エネスクを素材にしたという盤のようだ。1曲目の「アリア」の美しさに、文字通り耽溺する。まるでジョー・マネリが若返って微分音旋律を辿るような、これはマラビーなのか!至福の6分16秒だ。これは誰にも譲れない(何言ってんだ!)、これから年末にかけてニセコロッシに会うひとはすべからく聴かされることだろう。いま、この曲を編集CDRに入れてみた。続いてポール・モチアン・トリオ2000のライブ第3弾の1曲目、菊地雅章のソロからのバラッドにつなげている。
Ralph Alessi - trumpet; Tony Malaby - tenor sax; Lucian Ban - piano; Albrecht Maurer - violin; Matt Maneri - viola; John Hebert - bass; Gerald Cleaver -drums; Badal Roy - tablas, percussion.
recorded live at 2009 George Enesco International Festival, Bucharest, Romania on September 20, 2009.
このCDは7月10日四谷いーぐるでの益子博之「新譜特集:2010年ニューヨークダウンタウンシーン上半期」を聴いて、最後に選曲されたトラックで存在を知ったのだった。これだけコアなミュージシャンたち、
タガララジオ12のおしまいに記述ずみ、の遭遇は面白いにしても、CD全体としては、タブラのバダル・ロイが叩きながらジャズっぽくエネスクを素材に試行をしています、それ以上ではない、かな。
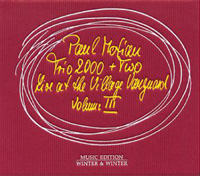
<track 099>
And So to Sleep Again (Joe Marsala / Sunny Skylar) / Paul Motian Trio 2000 + Two from 『Live At The Village Vanguard Vol. III 』 (Winter & Winter) 2010
ディスク・レビューに書き加えると。
1曲目はパティ・ペイジが51年にヒット(ビルボード4位)させたこの曲なんだそうです。
パーソネルも書き忘れていました。現代ジャズを牽引するクインテットです。
ポール・モチアン Paul Motian (ds)
クリス・ポッター Chris Potter (ts)
ラリー・グレナディア Larry Grenadier (b)
+
マット・マネリ Mat Manieri (viola)
菊地雅章 Masabumi Kikuchi (p)

<track 100>
Jugo-ya Moon on 15th Night (Ryosuke Hashizume) / Ryosuke Hashizume Quartet Live at Pit Inn on September 26th, 2010
記念すべき100曲目に偶然入手することができた橋爪亮督グループの9月26日新宿ピットインでのライブ音源の。
橋爪亮督 (ts,ss,loops)
市野元彦 (el-g, electronics)
吉野弘志 (b)
橋本学 (ds,per)
「十五夜」と題されたトラック。
ベースのつまびきに続いてカチャ、カチャと金属音、この打音の空間が支配するしじまの交感に彼らは揺れるトーンで漂い、じきに時間が静止する。
響きの断片だけが置かれる。そこでは梵鐘が鳴っているようだし、遠く山の向こうからの空気が振動してくるようだし。密教寺の儀式とも東大寺の修二会とも地続きだ。
14分38秒。
橋爪亮督のサックスが世界標準化したことは認知していた。トリスターノ学究を経てポスト・マーク・ターナーへ至る歴史的必然をまとった独特なトーンは、おれはそのままニューヨークに行ってターナーとツインでポール・モチアンとヴィレッジヴァンガードに立つものだと思っていたが、この現代ャズ不毛の日本において、これまた市野元彦というポスト・ビル・フリーゼルを世界標準でになう天才、天才は天才は知るのである、さっき荻窪ベルベットサンで市野元彦・渋谷毅・外山明トリオを聴いて激しく納得したが、と、橋爪はすごいグループ表現を拓いていた。
ニューヨークにしかないと思っていた現代ジャズが、日本人の歴史的な感性の現代化とのアダプトを果たせるなどと誰が想像できただろう。そう、まさに「侘び寂び」の世界だ。十数年前、橋爪はガルバレクが好きだと言っていた。おれはもうガルバレクの壮大な歩みは見届けたような気分でいるけど、それにしても橋爪亮督はすごいところまで来てしまったものだ。
前回、中秋の名月を書いたのは、この「十五夜」との遭遇を予言していたのだろうか。
あれはバブルの頃だったか、吉祥寺ロンロンで球体の置き時計を買った。一目見て吸い寄せられるようにして。球体には丸い窓がはめ込まれていて、長針と短針の先は地球と人工衛星になっていたかと思う。時間が立つと、背景が二重の偏光板になっていて、中から白熱球が発光して、黄色、橙色から薄い緑、青色、紺色へと変化するものだった。これが美しかった。
光っているだけの時計だったけど、沈黙の音がしたし、永遠が聴こえたし、世界はその中に収まっているように思えた。
20代で、そんな幸福の絶頂のような時間にとどまっていたのだ。24時間じゅうエアチェックする勢いだったし、駅前の本屋にはスイングジャーナル、ジャズライフ、ジャズ批評、レコード芸術、音楽芸術、MUSIC TODAY、フールズメイト、ロッキングオン、ミュージックマガジン、よいこの歌謡曲、レコードコレクターズ、包、中南米音楽、ブルースマガジン、G-Modern、バーン、FMファン、全部買ってたし、貸しレコード屋「友&愛」で新妻はバイトをしていた。

<track 101>
Tonal Suite / Michael Formanek from『The Rub and Spare Change』 (ECM 2167) 2010
Tim Berne alto saxophone
Craig Taborn piano
Michael Formanek double-bass
Gerald Cleaver drums
最初聴いたとき、「なんでい、これじゃあティム・バーンたちにECMワールドを演奏させてるだけじゃねーか!」とがっかりした。大村幸則さんが雑誌でさすがにやんわり書いていらっしゃった。
だってよ。ティム・バーンといえばニューヨークのダウンタウンシーンで最も凶暴なサックス奏者として少なくとも90年代以降は君臨しつづけてきた王者だぜ。ステファン・ウインターの当時JMTレーベルの諸作、自ら立ち上げたレーベル”screwgun”スクリューガンでの怒涛の作品群、これらに耳を沸騰させて渋谷のディスクユニオン前を風切って闊歩するのが30代現代ジャズ・リスナーの正当だったわけだし。ティム・バーン、スティーブ・コールマン、グレッグ・オズビーがピカイチだったんだよな。マーク・ターナー、クリス・ポッターが台頭してくるまでは。そしてトニー・マラビー、クリス・スピードと、シーンのトップは次々と脅かされている。老いたライオンの追い出しのように苛酷だ。
先入観で評価をしないでいたんだが、何気にカーステでCDが再生されたときに「お!おれ、こんないい演奏(のCD)持っていたっけ?」と耳をそばだてたもので、ベースとタイコの推進に耳をまかせると、これがいいんだな、1・2曲目、ECMミュージシャンよりも上手くてECMっぽい、なんて思ったことは、良い作品だってことじゃない?
17分を超えるトラック「Tonal Suite」、トーンの組曲って言うほどの大袈裟なものじゃないが、この演奏、ベースとタイコが主導して複雑なメロディの土台を整えるなか、ティム・バーンが先導できていなくて追いてけぼりをされたままアドリブを歩んでいるようで、おやまあ、よくまあこのまま録音が進行したものだよなあ、バーンのリーダーもしくはプロデュース作ならこの華のなさは却下だったろう、と、聴き進めてゆくうちに、7分すぎから演奏が宙に浮いたままノー・コンポジション状態に彼らは漂うことになっているようで、12分すぎあたりから戻ってくる演奏感覚のやりとりにノッているうちにコンポジションにきちんと戻っておしまい!と、なかなか聴かせるものである。
きくところによるとティム・バーンのガールフレンドがECMのニューヨーク担当だとか3箇所から耳にしたからたぶんそうなんだろうけど、ECMは信頼のブランドになっている現在では世界的な知名度を上げるにはいい機会なんだろう。おれみたいにECMなら何でも耳にして確認したいというファンは多いのだろうし。ECMとしてはアイヒャー制作らしい良い作品だと思いつつも、ニューヨークの猛獣のようなお前らが・・・、と、ついスクリューガン盤に手を伸ばしているリスナーもいる、てことだ。

<track 102>
Beautiful Dreamer / Bill Frisell from 『Beautiful Dreamer』 (Savoy Label Group) 2010
フリゼール少年の新しいお友だちとの新作『Beautiful Dreamer』。エイヴィン・カンEivind Kangのヴァイオリン、ルディ・ロイストンRudy Roystonのタイコ、この二人のセンス、演奏能力がやたら気持ちいい。だけど、音楽はつまらない。よく聴いてみ?この二人のポテンシャルがフリゼールの設定した檻の中で活かされきっていない。フリゼールはサイドで活きるひとなので、この3にんのライブなら成功したかも。
えー?ここ数作のフリゼール作品のだめだめさに比すれば抜群にいいという。あそう、おれ、聴いてなかったんだよなー。
名盤『アンスピーカブル』でグラミー賞取って、やりたい放題なのだろう、フリゼール。余勢をかっての『East/West』はタイコのケニー・ウォルセンKenny Wollesenが光るカラフルなライブ盤だった。そこまでは良かったということか。
ディスコグラフィーを見て、フリゼールはデビュー以来ずいぶん聴いてきたなあ、と、思う。フリゼールがバラライカという楽器を奏でてエバーハルト・ウェーバーの浮遊幻想世界を彩っていた『Fluid Rustle』なんか今でも寝入りばなによく聴くし。
ジャズ耳にかけては世界を二分しているいとしのリボンちゃん。
3日に京都の上賀茂神社境内でアブドゥーラ・イブラヒム(ダラー・ブラント)を聴いて50分に及ぶ渾身の演奏(1曲!)に風景が一変するような感動をしてきて、8日・9日に新宿ピットインでバティスト・トロティニョンをトリオとソロで聴いてCDとはまた違った指先のマジックを感じてきたという10月、が過ぎて、ね、今週に入ってもトロティニョンのピアノの耳鳴りがするのよ、あのアブドゥーラがあんなに凄かったのに!それを超えてでも鳴っているトロティニョンなのー!あたし、今週は仕事してないんだ、休んでいるほんとの理由はそこなの、わかる?
ねえ、カーク・ウェイラムをメロー、スムース・サックスだなんてのはだれなのよ!ホイットニー「I Will Always Love You」のサックスは彼だけど、ホイットニーも彼しかいないと。あんな懐の深いサックスをこんなつまらないカテゴリーにくくられるなんて。
今日はチャーリー・ヘイデンといきものがかりの新譜を買ったー。
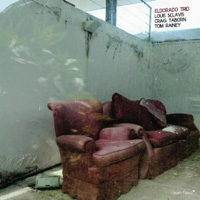
<track 103>
To Steve Lacy / Louis Sclavis, Craig Taborn, Tom Rainey from 『Eldorado Trio』 (Clean Feed) 2010
Louis Sclavis (ss,b-cl)
Craig Taborn (p,fender rhodes)
Tom Rainey (ds)
おー。現代ジャズをリードするレーベル「クリーン・フィード」から。フランスのもはや巨匠であるルイ・スクラヴィスが、ニューヨークの先鋭沸騰職人ふたりとの演奏を問うてきた。ほとんどがスクラヴィスのコンポジションではあるけれど、さすがにコンポジション負けしてない演奏の強度が、ときに不穏な殺気だっているもの。ジャケも良し。
スクラヴィス、いい感じだ。コンポジション・コンプレックスと演奏本能の獰猛さの超克という、そこらへんから放たれてゆくネクスト・ステージが楽しみになる展望を得る。スクラヴィスのインプロはオールド・スタイルに止まるもので、ジャズのラインに乗って強制起動されるときに身体の深部から噴出するような数珠つなぎ旋律、制御不能、に、立つ覚悟があれば大丈夫だ。うー、トリオのネーミングのおやじ臭さは何とかしてくれ。
ブルーノ・シュビヨンはトニー・マラビー、ダニエル・ユメールとのトリオ、ブノワ・デルベックはジャン・ジャック・アブネルとのピアノ・トリオ、ミシェル・ポルタルはボヤン・ズルフィカルパシチ、リオーネル・ルエケ、スコット・コーリィ、ジャック・デジョネットらとの新作、と、フランス・シーンの大物たちは動き出している。
大井町のイトーヨーカドーにある本屋で立ち読みしたら、村上春樹が自分でジャズ喫茶をやる以前によく水道橋の「スイング」に通っていたとあった。平岡正明がよくひとりで「スイング」に行って物思いにふけっていたと知ったのは、晩年のエッセイで、亡くなったあとに出版された本でだったと思う。
水道橋の「スイング」は、ディキシーランドやニューオリンズばかりかかるジャズ喫茶で、駅から後楽園球場へ向かう橋を渡って、お堀を降りてゆくようなコンクリートの階段を降りていった右側にあった。穴倉にもぐるような、お堀の湿気の匂い、打ち消す風、外国の太陽のような日差し、コンクリートのひびの奥から沁み出す敗戦とか死者の無念。
18さいだった。
Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
