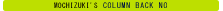吉野弘志は数少ない正統派のベーシストである。いつの頃からかアンプの力を借りて早いパッセージをいとも軽々と弾くベース奏法が一般的になってしまった。しかし吉野弘志のベースからはウッド本来の木の温もりが感じられ、折り目正しいコントラバスの音がじわっと伝わってくる。だから吉野弘志のベースはノンPA、純粋なアコースティックで聴く時、その微妙な音の濃淡、グラデーションがひときわ映える。
ステージで見る吉野弘志はいつも淡々とさり気ない風情で弦を弾いている。一見、柔らかでなめらかで押し付けがましさがまったくない。そしてたたずまいはクールだが心根はとても熱く燃えている。その奥には音に向き合うひたむきさが溢れてその艶やかな音色はライヴ・ハウスを居心地の良い空間にしてしまう。
吉野弘志は自らをフリーだという。しかし吉野弘志の音楽はフリーという言葉でくくれない真の自由がある。
吉野弘志の云うフリーというのは一般的にフリー・フォームと云われているジャズのフォーマットとは異り、すでに確立された音楽のフォームを全てとりはらって自らを開放し、自由に即興することをさしている。
これまで明田川荘之(p)トリオ、坂田明(sax)トリオ&オーケストラ、山下洋輔(p)グループなどジャズの先鋭的な革新者と共演を重ねてきているが、現在は自己のグループ「彼岸の此岸」と「吉野弘志モンゴロイダーズ・ネオ」の2グループを軸足として活動するほかベース・ソロ活動にも力を入れている。同時に吉野は多くのミュージシャンから共演を求められ、自己のグループ以外でもマイク・レズニコフ(ds)「Mike’s Jazz Quartet」や廣木光一(g)「クール・グレード」、石井彰(p)「幽玄郷」、板橋文夫(p)3、渋谷毅(p)とのデュオ、張林(揚琴)とのデュオなど幅広い活動をしているが、とりわけ一噌幸弘(能管)との共演ではジャズと邦楽を基本としながらもあらゆるワールド・ミュージックも視野に入れた即興の世界を展開、今年の10月には一噌幸弘グループでマレーシアに楽旅をしている。
吉野弘志の魅力は何といってもその美しい音色にある。吉野のコントラバスの魅力はやはりソロのときが一段と光彩を放つ。8年ほど前に発表したベース・ソロ・アルバム『on Bass』(rinsen0001)はコントラバスのショーケースのような作品である。自己のオリジナルのほかタッド・ダメロンや坂田明、佐藤允彦、モンゴル民謡など吉野のワールド・ワイドな着想が実を結んだ作品だが、この中の<アルフォンシーナと海>は吉野ファンにとってライヴに行ったらこれを聴かなくては帰れないという隠れたヒット曲になっている。しかしこのソロ・アルバムでもっとも心を魅かれるのは<Poucha Dass>で、フランソア・ラバスの難曲を超絶技巧で弾ききっていて、コントラバスの深い余韻に浸ることが出来る。
1990年にAECのジョセフ・ジャーマン(reeds)を日本に招き、日本ツアーとアルバム制作を行ったとき私は真っ先に吉野さんとの共演を頭に描いた。ほかに、お筝の沢井一恵さん、栗林秀明さん、斉藤徹(b)さん、トロンボーンの故 板谷博さんが加わった。そのときのアルバム『ポエム・ソング』(Yumi’s Alley/Videoarts)ではジョセフと吉野さんはデュオでジョン・コルトレーンの<スピリチュアル>を演奏した。ジョセフのバス・フルートと吉野さんのベース、低音楽器同士が共鳴し合い、まさにスピリチュアルな世界が広がった。本誌JazzTokyoのオーディオ・マイスター及川公生さんにダイレクト録音をしていただいたので吉野さんの艶やかな音色がそっくりそのまま収録されている。
吉野弘志は1955年広島市に生まれる。お姉さん二人も音大に進むという恵まれた音楽環境で育っている。小中学時代は学級委員や生徒会長をつとめる優等生だったという。小さい頃からヴァイオリンを習い、中学時代はブラス・バンドでトランペットを吹いていた。高校は広島一の名門校、広島大学付属高校に進む。高校に入って初めて自分のお金で買ったレコードがマイルスの『カインド・オブ・ブルー』(COLUMBIA)だったとのこと。広島のヤマハで見つけ、何の予備知識もなく買って毎晩くり返し聴いたのがジャズとの本格的な向き合いの始めであった。
吉野さんはポール・チェンバースこそ天才的な革命児だという。<So What>のポール・チェンバースなど相当聴いたのではないかと想像すると吉野さんのベースが一段と快く耳に響く。<今でも力説したいのはポール・チェンバースですね。ポールは古いベースでスコット・ラファロがベースの新しい流れ、みたいによく言われますが、それは大間違いでポールこそベースの革命児でソロでも伴奏でも素晴らしいし、なにが素晴らしいかといったらなかなか理解不能のような、どうしてそんな動きになるのか分からないような不思議な動きをしていて、それが割りと論理的に説明が出来ないようなところがあって、それがとっても素晴らしいんですよ>と語ってくれた。ベースをきわめた人の言葉は重い。
ベースは高校2年のときから弾き始める。
本人曰く、高校時代はドロップ・アウトしていたそうな。学校のロッカーで私服に着替えるとパチンコ屋に向かい、打ち止めにしては得たお金でレコードを買ったという。打ち止めにすると丁度レコード一枚分位のお金になったという。パチンコとジャズと、サルトルとカミユ、実存主義に接したのがひねくれ始めだと笑う。自分は受験のためにこの高校に入ったんじゃないんだ、自由度が高いから入ったんだと思い、大学受験などは念頭になく、ただただ自分探しに没頭していたようである。この頃、友人の誘いでバンドに加わって演奏するようになり、高校の終わりごろには漠然とジャズ・ベーシストになろうかな、と思い始める。そのためベースのレッスンを受け本格的にベースと向き合う。そして広島在住のベーシストからN饗のコントラバスの先生を紹介してもらい指導を受けるが、どっちみちクラシックの練習をするのだったら芸大にでも行こうかと思いたち、N饗の先生に芸大の先生を紹介してもらって勉強し、東京藝術大学、器学科・コントラバス専攻科に進む。この間自分の道を決めるまでに高校を卒業してから2年かかっているという。東京芸大在学中に明田川荘之(p)トリオで「アケタの店」に出演、以来アケタさんとは親友つきあいをしている。やがて坂田明トリオに加わると学業よりも演奏の方が忙しくなりそのままプロのベーシストに専念する。
いま愛用しているベースは1988年加藤登紀子(vo)のカーネギーホール・コンサートに出演した際、ニューヨークの楽器店で見つけたイタリー製の由緒ある名器でCエクステンションをつけてあるという。ベースという低音楽器の低域の限界を広げて自己の音楽の幅を広げようという熱意がこの楽器との出会いにつながったのだと思う。愛器を手に入れて20数年、ベースを弾いている姿も格好いいが演奏会場にベースを運ぶ姿も決まっている。
<ベースという楽器はいわゆるフレットのない弦楽器ですよね、音程の枠がない、アラブ音楽のウードのように半音の半音とか1/3音であるとか、そういう微妙な音程が出せる楽器なんです>
<実は5〜6年前から「アラブ音楽アンサンブル」にも加わって演奏しているんですよ。やろうと思えばそういう世界も出来るかなと思っています>
そしてジャズとアラブ音楽との係わり合いについても持論を話してくれた。
<実は僕はパーカーの時代からハードバップもジャズは相当アラブ音楽から触発されていたんじゃないかと強く感じますね>
<たとえばガレスピーのチュニジアの夜なんかもまずイントロからにしてアラブ音楽的な雰囲気があるし、タイトルからもうかがい知れるものがありますね。モンクなんかも半音と半音の出し方で不協和音を出しているし、もしかしたらモンクもアラブ音楽の音程感覚に魅力を感じていたのではないかとも思うんですよ>
<僕はアラブ音楽に接することによって逆にジャズがより近くなる、そういう感覚を持っているんです>
因みにはじめて買ったベースは高校2年のとき、当時音大に通っていた姉の馴染みの楽器店で安く手に入れたのだと伺っているが、このベースは阪神淡路大震災のあと、被災地でベース奏者を志す子供の役に立てればと無償で提供したという。吉野さんの音楽を愛する気持ちがあらわれた微笑ましいエピソードである。
いま吉野弘志が結成しているユニットの楽器編成は「彼岸の此岸」が太田恵資(violin)、鬼怒無月(guitar)、吉見征樹(tabla)}、「吉野弘志モンゴロイダーズ・ネオ」が小森慶子(clarinet ,sax)、田中信正(piano)、和田啓(req)と2グループともジャズのドラムが入っていない、その理由を伺った。
<ドラムというのはシステマティックに出来ているからどうしても欧米音楽的な小節の枠組みががっちり出来ちゃうんですね>
<で、ドラムが入るとやりやすいんですけど、もっと、こう、欧米音楽的でない音楽やエスニックなものをやるときには枠がないほうが自由になれるんです>
勿論、吉野弘志は富樫雅彦、森山威男、小山彰太といった歴代の名ドラマーともコンビを組んで名演奏を残している。
ユニット「彼岸の此岸」は今年、横浜「ドルフィー」と西荻窪「音や金時」でライヴ・レコーディングを行った。「アケタの店」のオーナー、明田川さん(p、オカリナ)が吉野の「彼岸の此岸」をアケタズ・ディスクでぜひ出したいと云うことからアケタズ・ディスクの島田正明さんを出張させて録音したもので、目下テイク選びをしているのだという。アジア的なテイストを持つ吉野弘志のオリジナルやアラブ民謡、トルコ民謡、ジャズ・スタンダード<マイ・オールド・フレーム>、武満徹の<他人の顔のワルツ>などバラエティーにとんだものになりそうで発売が待たれる。
また、オーソドックスなジャズ・ベース・プレイヤーとしては近々マイク・レズニコフ(ds)の「Mike’s Jazz Quartet」で「アケタの店」でのライヴ・レコーディングが予定されているという。
明田川荘之トリオに始まり、坂田明、山下洋輔、森山威男、富樫雅彦といった日本を代表するミュージシャンと共演を重ねジャズ・フィールドで活躍する一方、加藤登紀子や大貫妙子などのヴォーカリスト、ヴァイオリンの金子飛鳥、高橋悠治や三宅榛名などの現代音楽、武満徹作品、フォルクローレ、ワールド・ミュージックにいたるまであらゆるジャンルに活躍の場を広げ、着々と自己の音楽を築きあげてきた吉野弘志は、いま最も充実した時を迎えている。


 1.31 '16
1.31 '16![]() :
:![]() :
:![]() :
:![]() :
: