
カチューシャー、はずしながらー。いけね、つい鼻歌してしまった。夏が近づく、見たことのない夏がくる。
益子博之さん(音楽批評)が例年のニューヨーク、ダウンタウンのジャズ・シーンの定点観測に6月18日、出発された。期待のライブが目白押しでスケジュールを組むのが大変だったとか。
4月に行なった「益子多田四谷音盤茶会@喫茶茶会記」の第2回目を7月24日(日)に予定しております。現場感覚に裏打ちされた選りすぐりのトラックを聴きながら、今年のNY詣での収穫をお聞きできると思います。当日のゲストはギタリストの市野元彦さん。・・・あ、まだ公式発表されていませんでしたが、喫茶茶会記(http://gekkasha.modalbeats.com/)と益子さんのブログ「うたかたの日々」(http://gekkasha.modalbeats.com/?cid=43768)をチェックしておいてください。
昨日6月17日から、吉祥寺のサウンドカフェズミ(http://www.dzumi.jp/info/2011/0617.html)で、開店5年目突入記念「よいどれ黒海ジャズツアー」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/)隔週金曜日開催がスタートした。セゾングループの文化事業の、ジャズ批評誌の、黄金時代を担ったわたしたちあこがれの不良老人デュオ、15にんの満席状態で質疑応答感想がまったり飛び交うすてきな夜だった。かかる音源ははなはだ濃い。若者が多いのもすごい。将来のサウンドクリエーターにカフェズミ世代なんてのができるのだろう。
益子さんのブログ「うたかたの日々」で紹介されていた「The 25 essential New York City jazz icons」、ニューヨークジャズのアイコン、ベスト25!、これはジャズの専門誌ではなくタウン情報誌のような一般誌に掲載されたものだという。モチアンとウイリアムパーカーをコンプリート街道している日本人はおれだけだぜくらいの自負はあるが、それが1・2位なんだぜ!
1. Paul Motian 2. William Parker 3. Wynton Marsalis 4. Henry Threadgill 5. Roy Haynes
6. Cecil Taylor 7. Tim Berne 8. Ethan Iverson 9. Ornette Coleman 10. Maria Schneider
11. Matthew Shipp 12. Randy Weston 13. Jason Moran 14. Fieldwork 15. Lee Konitz
16. Fred Hersch 17. Jon Irabagon 18. Gretchen Parlato 19. Matana Roberts 20. Tony Malaby
21. Mary Halvorson 22. Muhal Richard Abrams 23. Arturo O’Farrill 24. Ari Hoenig 25. Bill Charlap
モチアン、ウイリアムパーカー、マルサリス、スレッギル。ベスト4なんておれがセレクトしたような不動の4にんではないか。はしたないけど鬼の首を取ったような態度にならせてくれよ、こんなに不遇にジャズを聴いてきて、単なる偶然でもいい、一瞬だけ、一瞬だけ、世界の耳はおれの耳だと、今月から入院状態になった末期ガンの老いた母親にきかせてやりてえ、おっかさん、やったよ、ニューヨークがおれを認めたんだぜ、錦を飾らせてほしい、うっく、うっく。
このリストの秀逸は、一時代を築いたメセニーもメルドーもジャレットも音楽は自己中で入ってないんだし、ハーシュやマラビー、ハルヴァーソンが堂々と入っている点だ。おろ?ローゼンウィンケルとターナーは???クリススピードとクレイグテイボーンは?ジョンホーレンベックに気付いてないのかえ?ううむ、ちょっとわたしがこのベスト25を手直ししておこう。
ジャズには動植物のように系譜や系統があり、おのおの言語である特質もある、が、まずは演奏力、表現力、さらに影響力や伝播の柔軟性を総合的に勘案したジャズ世界ランキングの暫定版として掲げておこう。
1. Paul Motian 2. William Parker 3. Wynton Marsalis 4. Henry Threadgill 5. Kurt Rosenwinkel
6. Kikuchi Masabumi 7. Mark Turner 8. Bruno Chevillon 9. Eric Harland 10. Chris Speed
11. Gerald Cleaver 12. Mary Halvorson 13. Tony Malaby 14. Chris Lightcap 15. Thomas Mogan
16. Tyshawn Sorey 17. Fred Hersch 18. Craig Taborn 19. Stomu Takeishi 20. John Herbert
21. Mat Maneri 22. Charles Lloyd 23. Ben Monder 24. Chris Potter 25. Jacob Anderskov
ふふふ。益子さんの居ないすきに大風呂敷ひろげちったい。「たださん、フランスのシュビヨンやオランダのアンデルシュコフを入れているのでしたら日本の橋爪亮督や市野元彦は入れなくていいのですか?マケンリーは?ダンワイスは?たださんの好きなノアプレミンガーやブノワデルベックは???」とか言われそう・・・。そうだよなー、コニッツ、ジムブラック、アンドレアパーキンス、ジョーモリス、ティムバーン・・・ぞろぞろとベスト30や50、書き出せそうだ。48にんにスポットをあてて、現代ジャズアイコン48として総選挙投票権つけてCD売るか。


<track 118>
ずっとウソだった / 斉藤和義(http://yutori2ch.blog67.fc2.com/blog-entry-2507.html)
さすがエクスワイフだ、斉藤和義をコンプリートしているし、斉藤和義が削除されても何度もYouTubeに投稿し続けた自身の「ずっと好きだった」の替え歌「ずっとウソだった」を、ごていねいにも動画から音声を編集CDRに焼いておみやげに持たせてくれた。
片山杜秀がCDジャーナル6月号(左写真)特集「3.11が音楽にもたらすもの」で、現代的表現、ことにアヴァンギャルド、は、変容を余儀なくされると書いている。地下で地盤を叩かれるのに対抗すべく太鼓が独自の進化を遂げた地震国・日本である、という事実指摘はさすがだ。
2番以降は「ずっとクソだったんだぜ」と歌われる。東電も、北電も、中電も、九電も。
6月6日。FaceBook で見たコメント。
「東北道で福島市を通過中です。西藤君が放射線計測器を持っていて、窓を閉めた車内でも高速道路上で0.5〜0.8マイクロシーベルト毎時が出てます。年間にすると4〜7ミリシーベルトです。子供の年間許容量をはるかに越えてます。困ったのレベルではないですね。」
そういえば、こんな予言地図も見たぞ。
(http://www.qetic.jp/blog/pbr/?p=3654)

<track 119>
Casablanca Moon / Slapp Happy from 『Slapp Happy』 1974
「事故のあとの言説が戦争のあとの一億総懺悔のようで、「東電だけが悪いわけじゃない」と、懺悔と悔恨、鎮魂のオンパレードです。」宮台真司(『原発社会からの離脱-自然エネルギーと共同体自治に向けて』宮台真司×飯田哲也:講談社現代新書 2011)、ぎくー!「いずれにしても、東京電力をバッシングしてても的を外している気がする、と、おれは言いたいのだ」(前号)と書いてしまったおいら、それでは社会は変わらないのだ、さすが宮台、長女のはびるちゃんに胎内にいるときからスラップ・ハッピーを聴かせているだけある。
聴かせていたのは「カサブランカ・ムーン」でしょうか・・・
昨日出た原発本は駅前の本屋には2軒とも売り切れていて、新宿駅構内のブックエクスプレスで棚にあったさいごの1冊をようやく入手した。これは救国の書だ。
はびるちゃんとのはなはだ感動的なエピソードは2年前に幻冬舎新書で出た『日本の難点』で知った。これも救国の書だ。
おいら世界状勢については田中宇さんの国際ニュース解説(http://tanakanews.com/)を読んでいるのですが、宮台さんと田中宇さんの対談がいまいちばん読んでみたいです。

<track 120>
Filters / Bertrand Denzler from 『Tenor』 (Potlatch) 2011
さて歌ものが2曲続いたので、現代即興のCDを。さすが聴くと血の味のする存在感を維持しているフランスのポトラッチ・レーベル(http://www.potlatch.fr/)。
テナー・サックス・ソロ、ということになるんだが、従来のインプロ然とした演奏はしていない。執拗に、息を吹き込み、楽器を共鳴させて倍音だけが楽器から自鳴する事態を操作しようとしている。いけね、答え言っちまった。この営為の射程に耳が気付き始める時間の推移がこの作品のキモであるからだ。演奏者の、自分の響きに耳をすましている態度の密度、審判の精度が上がっているのは時代のモードなのかな、と、思う昨今、これは極端な典型例なのだろうか。
いくら技術革新を駆使して未知のサウンドを現出させようとしても、まだまだ素朴な手と耳の、そもそも声の操作にくらべて生楽器は制約があるがゆえに、可能性が拓けている、という、この満ち足りた胸のすくような冒険心、実験精神、静謐さが、ひときわ輝いているように思えた。
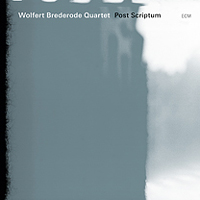
<track 121>
Post Scriptum / Wolfert Brederode Quartet from 『Post Scriptum』 (ECM 2184) 2011
Wolfert Brederode piano Claudio Puntin clarinets Mats Eilertsen double-bass Samuel Rohrer drums
伝統のECMが響いている。このカルテット、ECMでは2作目で、ピアニストは他に2枚参加作がある。ごめん、聴いてなかった。このトラックの耳をそばだてる倍音演出の効果は出色であるが、このカルテットの佇まいはECMの70年代からの伝統をつなげているようだ。
この流麗かつ輪郭が明確なクラリネットにも耳がそばだつ。クラリネットと言えば福島恵一さんの記述「NYダウンタウン・シーンにおけるクラリネットの復権も、決してノスタルジアの産物ではなく、私が「2010年ベスト30」のThe Internationale Nothingの項で指摘したクラリネットの音響的特徴によるものではないだろうか」(http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-105.html)のことも連想する。
このクラリネット奏者クラウディオ・プンティンは、2000年ごろのECM特選名盤『Ylir』(ECM 1749)で知った。何年に一枚かの静謐な盤だ!と、おれは聴いて騒ぐだけであった。刹那快楽主義で怠惰なだけのわたしは気に入るとそれだけ聴くばかりで掘り下げない、掘り下げられない。僚友の堀内宏公がmusicircusで、このプンティンの周辺を掘り下げている(「NEMU RECORDS and Works of Klaus Kugel」http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/review/kugel.htm)。
終盤に収録された「Silver Cloud」は時の回廊に迷い込むような美しさだ。そして、最終トラックはこの曲の変奏の表示で、その音処理の尋常ではない響きこそはECMの現在性を垣間見せているのではないか、『Re:ECM』との対比において。
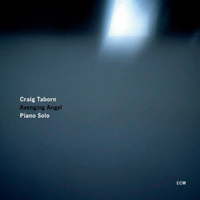
<track 122>
The Broad Day King / Craig Taborn from 『Avenging Angel』 (ECM 2207) 2011
これは歴史的な盤だろう。ピアノ・ソロの革命を、またECMが、というのに近い。
アイヒャープロデュースだが、お馴染みのスタジオではないクレジットから音源はテイボーンの持ち込みに近いのではないか。そして、この閃光のような一撃を露払いにしてECMでリリースが控えているのが菊地雅章のピアノソロではないか(これも菊地のスタジオで録った持ち込みであろう)、と、なかば確信に近い予感にひさびさにどぎまぎしてる。これを歴史的な盤だと世界で最初にぶちあげたのはおれだぜ。しかして、その作品の良さを記述できなければ何にもならないのだが。
『Avenging Angel』というタイトル「復讐の天使」は、固有名詞的であり(http://urashimamaeda.wordpress.com/2009/07/08/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E9%9D%A2%E7%99%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E-120/)、また、テイボーンは何らかを込めているものだろう。
おれはいままでテイボーンのピアノにはまったく注意を払っていなかった。現代ジャズの雄、クリス・ポッターが率いるアンダーグラウンド、これさえ評価をしている日本のジャーナリズムは少ない、で、のりのりに盛り上げているフェンダーローズがテイボーンであることはふまえているが、益子博之さんといろいろ聴いた過程で、テイボーンはフェンダーローズの鬼だと、その尖った変態性に耳が立ちはじめていたここ数年にすぎない。完全ピアノソロが可能だったとは。
菊地雅章にテイボーンをきくとあまり肯定的ではない反応だったし、いくつかのYouTubeでテイボーンの演奏をチェックしてもどこかアクロバティックなショウを顕わにしているように聴こえる。この盤に横溢する、おのれの響きに耳をそばだてて同時に音楽のロジックを見失わないままに鍵盤に対峙している孤独な厳しさは感じない。そしてまた、この演奏はクラシックなりジャズなり聴き手の引き出しによって聴き手が道を見失うような仕掛けに横溢しているのも事実だ。テイボーンは”その音”を弾いていない。空間の、聴こえないところに音を鳴らしている、その響きのラインがわたしには視えるような気がしている、と、言えば多少は手がかりになるだろうか。

<track 123>
Sequence HCM 1 / Daniel Humair, Tony Malaby, Bruno Chvillon from 『pas de dense』 (Zig Zag) 2010
フランス・ジャズ界の帝王ミシェル・ポルタル(おお、そいえばポルタルの新譜も好評だが未聴だー)がライナーを寄せていたり、ディスクユニオン界隈でも高評価な、本盤。ちゃんと聴きあってて、クリシェをある程度避けてて、おのおのの技も駆使している、という点で一定の評価ができる好盤だ。CD制作者もピンときているようで1曲目に据えた、ベース鬼才シュビヨンの撥ね叩く感覚の妙技!が実に美味しいー。
まあ、大御所ユメールじいさんの共演者の選択眼はやはりたいしたものだし、このじいさんのオファーする叩きのオールドファッション度を責めてはいけないんだが、ダウンタウンの暴れん坊マラビーのフットワークの良さもほめていい、とにかくとにかく、シュビヨン、このカッコいい不良中年を世界はまだ十分に認識していないわけだし、シュビヨンはこないだとんでもノイズ盤で大いに楽しませてくれた「シュビヨンの夜」(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20090613)、まずは健在ぶりを楽しもう。
AKBをAKBたらしめているのは、篠田麻里子なんだが、おれはエレベーターに一緒に乗って彼女をエスコートしたことくらいあるさね、初週売上133.4万枚でミスチルの「名もなき詩」を抜いて歴代シングル売上1位になった、って、ひとりで5500枚とか2200枚も買った総選挙投票権目当てがあったともきくAKB48のシングル「Everyday、カチューシャ」、B面扱いの「これからwonderland」で見せる規格外の四肢で堂々とした女王様ぶりをみせる彼女に一票。

<track 124>
青春は恥ずかしい / SKE48 from single「1!2!3!4!ヨロシク!」type B (Nippon Crown) 2010
アイドルのCDを買うのはBuono!の「ホントのじぶん」(2007)以来かもしれない。カップリングの「こころのたまご」も見ないでトチらずに歌えるぞ。ちなみにクッキンアイドル「アイ!マイ!まいん!」の柊まいんちゃんについては、TV音声をDATにつないでいろいろ集めているのはないしょだ。Buono!の鈴木愛理と柊まいんの声の、どちらが上位か、これの判定はテン年代の未解決課題だろう。
さて、このSKE48の4thシングルは楽曲ではなくミュージック・ビデオの破壊力である。踊り、コスチューム、振り付け、かわいさ、四肢の関節のクッション・・・。実際楽曲はパクリとは言わないまでも映像無しでは聴くには耐えない代物。「1!2!3!4!ヨロシク!」の16人選抜メンバーとバックの大勢の女子校生たちの大迫力は早くも現象だろうが、おいらは「青春は恥ずかしい」の赤いスチュワーデス制服の松井玲奈の身動きに、おいでおいでをする笑顔にかまけている。
店員は「ジャケ違いが3つあるんですよー」としか言わなかった!「青春は恥ずかしい」が目当てなのに、Type Aをジャケ買いした。この曲はType Bにしか収録されていないではないか!よく見ると Type A と Type B と劇場盤と、同じタイトルのシングルにB面が違う3種が存在するのである。3つ買うと4800円。全部で5曲の新曲で4800円。22年産こしひかり新米が15キロ買える大金だ。おれの世代には許容できないまったくもってあこぎな商売だ。
AKBやSKEを見ていてつくづく思うのは、彼女たちがいるおかげでNHK児童合唱団のユースシンガーズが低能なガキどもの餌食にならずにすんでいることだ。NHKの文化防衛の視野はさすがに深い。近年の子ども番組における日本語や伝統芸能の取り扱いにも、NHKの凄みがある。このあたり、・・・あまり深く記述しないでおこう。
ミュージックビデオ自体は、踊りの全貌が巧妙に隠されており、さらなる欲望、やっぱりナマで観ないとな、あのコの踊りをカンペキに観たいぞ、をいざなう。「うまく言えないけれどおしりがむずむずしてくるよ!」ほんとなのか?どんななのか?それが青春の恥ずかしさなのか?その振り付けはなんだ!

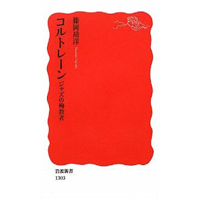
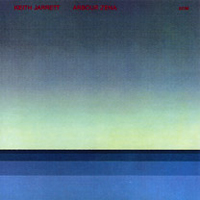
<track 034>
Peace on Earth / John Coltrane from 『Infinity』 (Impulse) 1972
タガララジオ5(http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-05.html)で書いたコルトレーンの『インフィニティ』は93年に国内盤CD化されたまま、アメリカのアマゾンで100ドル!で売られていた。たまたま日本のアマゾンで2800円で出ていたのでようやく入手。もう「48階だての空中寺院のような場所で生まれる順番を待つ列にお経を唱えながら走り回る夢」を見てしまうほど感動しなかったが、吉祥寺カフェズミのオーディオでアナログで聴いたらやはり凄かった。
店主いずみさんが「藤岡さんがちゃんとインフィニティは傑作であると書いているよ」となにげなく言う。藤岡靖洋『コルトレーン ジャズの殉教者』(岩波新書)に書いてあるという。ここでまたおいらは鬼の首をである。
『インフィニティ』はコルトレーンの死後、夫人のアリスがカルテットの音源にオーケストレーションをほどこして、この作業だって相当なモンだと思うよ、自身のハープ演奏、そしてチャーリー・ヘイデンのベース演奏を加えて(!)仕上げた作品である。ジャズファンがジャズファンであるがゆえにこのサウンドを受信しなかった可能性はある。
おれはね、アイヒャーは聴いてすぐに、ジャレットと『Arbour Zena』(ECM 1070)1975を作ったんだと読んでいる。ムラデン・グテシャ指揮のオーケストラの響きに、若きヤン・ガルバレクが朗々と歌い上げ、まさにチャーリー・ヘイデンのベースを不可欠なものとして配置している、もちろん才気煥発にのびやかなキース・ジャレットが作曲しピアノを弾いている。


<track 125>
RENSENADA / Richard Villalobos, Max Loderbauer from 『Re: ECM』 (ECM 2211/12) 2011
これについてはすでに日記で触れた(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20110613)が、さきほど本家ECMサイトにもジャケが掲示された。デジタルなにじみ具合がサウンドとリンクしているジャケだと思う。
2枚組で17トラックのリミックスが聴ける中で、1曲だけ廃盤のままのECM初期作品が素材に使用されている。その作品はベニー・モウピン『ロータスの宝石』(ECM 1043)で、これはハービー・ハンコックが親鸞上人への帰依後、創価学会への入信後の制作であり、ジャケには蓮の華がデザインされているもの、ハンコックがピアノをぐぐっと弾いている唯一のECM参加作でもある。もともとアナログはDJたちの間で高く取り引きされていたものでもあり、作品としてもレベルは高い。

<track 126>
Birth Of Liquid Plejades / Tangerine Dream from 『Zeit』 1972
プログレ界の長距離ランナー、タンジェリン・ドリームのサード。表参道は月光茶房店主の原田さんはおれの顔を見るなり、それまでおしゃれなピアノトリオがかかっていたのを止めてまで、これをかけてくれました。こ、この持続音、金属音、思い詰めのまごうことなきドイツ・ロマン主義のガイストがそのままサウンドになったような・・・、知らなかった、この作品は未聴だった、ECM初期との同時代性も聴こえる・・・、それにしてもお店にいたそれぞれ別々の3にんの若い女性客がジャケを一瞥するなりお会計なされたのはただの偶然なのでしょうか。

<track 127>
Let 'Em In / Paul McCartney & Wings from 『Wings at the Speed of Sound』 1976
当時の邦題「幸せのノック」・・・、横山ノックがこそこそエロいことをしているようなタイトルである、書かなければよかった。
おれはこの曲、勉強熱心なポールがスティーブ・ライヒを聴いて作った曲だと思っている。シンプルな繰り返しのリフで淡々とグルーブさせてしまう、ポールはまだ音楽の最前線を走っていたような気がする。遠くから軍楽隊が行進して近づいてきて、また、遠ざかってゆくアレンジのイメージも鮮やかだ。
おれはこのLPを高校生のころに初めて徹夜をしたときに聴いていたもので、筒井康隆の短編集「にぎやかな未来」の文庫を読みふけっていて、その文庫カバーのたくさんの顔が極彩色にざわめいているイラストにウキウキして眠れなくなったのであった。ちょっとぐぐってみてもその画像は見つからない。LPでは「きみのいないノート」「シーズ・マイ・ベイビー」あたりのつながりを聴くと、今でもその時に戻れてしまう。
6月18日、69さいの誕生日おめでとう。
大相撲に関心のあるひとは、高橋秀実(たかはしひでみね)の『おすもうさん』(草思社)を読んでおかないとだめー。現代思想誌2010年10月号の特集「大相撲」(http://www.seidosha.co.jp/index.php?%C2%E7%C1%EA%CB%D0)では、かなり踏み込んだ議論や論考、この執筆陣を見よ、なんだけれども、どこか踏み込めていないのは、やはり現代思想ではだめというか、すべてコトバに寄り切りをくらっているのである。
ガチンコと八百長、スポーツと神事、国技、それらの議論なんて通用しないおすもうさんの真実。この、呑気な、まあまあな、そこそこな、まったりなカンジ?まったり、って、外国語にはどう訳されるのかいな。まったり、待った。テレビで大相撲中継を観ているとうっとりとしてきて眠くなってしまう謎まで、高橋さんは迫っている。すもう、すまふ、って、住まう、でもあったか!
はっけよい、はっけよい、ひがーし、坂本真綾、ふぃーるまいせるふー、にいしー、小沢健二、てんしたちのしーんー、のこった、のこった、と、そんなふうに音楽を、でも全力で聴いているんだよ、自分でも何書いているんだかわからなくなってしまいましたので、では、次回。
Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
