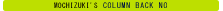アケタこと明田川荘之は見事なまでの反骨の人、そして信念の人というのが定説となっている。
一見、無愛想に見えるその内面からは生真面目といっては怒られるかもしれないほどに素直で自分に正直な人柄がにじみ出ている。なにごとにも誠実で自分の心に忠実な方である。
どんなときでも演奏中は精神を集中しエモーションのかたまりとなる。しかし、ひとたびステージを降りると、時には饒舌なギャグを連発し、時には顔中を満面の笑みにしてその場を和ませる。まわりの人への気配りも人一倍強く、繊細な感覚を持っている。
アケタ・トリオのライヴではアケタは晩年のエヴァンスのように曲の導入部に長いピアノ・ソロを弾くことが多いが、このソロが一段とすばらしい。
ピアノと向き合うときのアケタは身体を前後左右にゆすり、パウエルの100倍もの唸り声をあげる。
その演奏スタイルはピアノとの格闘のようでもあり、またピアノと愛を交わしているようでもある。
全身全霊を注ぎこむピアノからは激しい魂の鼓動と何とも云えない哀感がにじみ出る。
最近はビリー・ホリデイの『レディ・イン・サテン』(CBS SONY)、バド・パウエルの『バド・パウエル・イン・パリス』(reprise)、ブラームスの<交響曲4番>、モーツァルトの<交響曲40番>や<クラリネット協奏曲>などを、こだわりをもって聴いているという。これらの演奏とか曲には死と直面した強いストレスがないと表現できない、ということがわかってきたという。これは(破滅型の)天才は大変だということでもあり、自分がそういう音楽が好きなのでつらいところだとも云う。
アケタの書く曲は童謡のようにメルヘンティックで可愛らしい。しかし演奏そのものはドラマティックで奇想天外、眼を離せない。その一方でアケタの弾くバラードがまた絶品、こんなにも優しい人なのかと我を忘れる。アルバム『ニアネス・オブ・ユー』(アケタズ・ディスク)などはその代表作であるが大体どのアルバムにも一曲はバラードが入っていて如何にアケタがバラードに心を注いでいるかが分かる。巨匠とか、名人と呼ばれる人は大体においてバラードで人を泣かせる術を持っている。個人的にはアケタの<アイル・クローズ・マイ・アイズ><アイ・フォール・イン・ラブ・トゥ・イージリー>などがフェイヴァリット曲であるが、もうひとつ、アケタのブルースもそのものずばり<アケタズ・ブルース>、アケタの人生が聴こえてくるのである。
アケタさんとは10年ほどスイングジャーナル誌で同じコラムを分けあって担当していたし、新聞「ジャズワールド」でもご一緒だったこともあって特別な親しみを感じているせいか、ときどき無性に聴きたくなることがある。これは私にかぎった話ではないらしく全国各地にアケタ症候群におちいった人がいるらしい。その範囲は北海道から東北、九州、沖縄におよび、アケタさんは時々かの地の友人から招かれてひとり旅をする吟遊詩人でもある。また、1996年にはアフリカ・ツアーも行っている。
アケタはピアニスト、オカリーナ奏者、作曲家そして株式会社アケタの社長としてライヴハウス「アケタの店」の運営、「アケタズ・ディスク」のプロデュース、さらに「アケタオカリーナ」の開発と製作そして女子美術大学アート・デザイン表現学科の講師、エッセイストなどいくつもの顔を持ち、その一方で「中央線ジャズ」(CDジャーナル・ムック)なる語原の震源地として「アケタの店」からさまざまなメッセージを発信している。
明田川荘之、通称アケタは1950年10月23日、東京荻窪に生まれる。あるアルバムのライナーノーツには自分の生まれた産院の名前まで自ら記述している。生まれながらにピュアで全てオープンな人なのだ。
小学校の2年のときから当時、父、孝のお弟子さんだった火山久からオルガンと作曲の手ほどきを受ける。意外にも小、中学校の頃はボーイソプラノを担当し学校の催し物などで歌っていたという。高校1年の頃から4年半エレクトーンを習うがピアノは独学と云う。
立教大学の経済学部に入学、大学の軽音楽部に入ってジャズを知る。はじめ、ピーターソン、マイルス、MJQなどを聴いているうちにマルやドルフィー、パウエルを知り、ジャズは現代のクラシックだとの思いに至ったのだそうである。ジャズを知る前はずっとクラシックを聴いていたそうでブラームス、カール・シューリヒトが好きで、今はシューマンにも興味があるという。
19歳のとき、大学在学中に「新宿ピットイン」朝の部や渋谷「オスカー」などで演奏するようになり、大学を卒業して1年後の1974年2月24日、23歳にして西荻窪「アケタの店」をオープンする。アルバイトで蓄えた資金と母カヅさんから借りたお金を元手に店を構えた。自分の目指す理想に向かっての船出である。自分の店を持つにいたった経緯は当時の日本のジャズをとりまく状況に不満があったとか、いろいろな方が書かれているが、あらためてご本人に語っていただいた。
「不満は日本ジャズ全部に、という思いで、自分は天才だと見込んでもいました。だから自分の理想とするスケジュールで店を運営したかった。しかし今考えるとかなり無理もありましたね。天才と思い込んでも技術や理論などがついてきてないとか」また、当初は希望する高名なミュージシャンが全く出てくれなかったという。しかし、アケタの熱意が徐々に伝わり状況は好転する。「山下さんがホームグランドにさせてくれと、毎月出始めたように記憶します。坂田さんや香津美氏や向井、そして店の真骨頂としては古澤、板橋が中心に」70年代に日本のジャズを牽引したトップ・ミュージシャン達が次々に賛同「アケタの店」をホームグラウンドのように愛し、楽しみ、また修練の場としたのだ。渋谷毅もそうしたアケタの店を愛する1人で「渋谷毅オーケストラ」や深夜の「ピアノ・ソロ」、「渋谷さんといっしょ」「月の鳥」などいろいろな組み合わせでアケタの店の歴史を刻み続けている。渋谷毅オーケストラの作品ではずばり『ホームグランド・アケタLive』(アケタズ・ディスク)と名づけられているほどである。ベースの吉野弘志も店の近くに住んでいることもあってアケタの常連、多くのセッションでしなやかなリズムを提供している。「アケタの店」の毎月のプログラムに肉筆の添え書きを足した「実写版!月刊アケタがわ賞」はアケタさんのジョークがコミカルでエロティカル、面白くて毎月これを楽しみにしている人も多いようだが、吉野さんはおそらくこの欄の最多登場記録を誇っていて、アケタさんと吉野さんとの深い友好関係を垣間見ることが出来る。
アケタの店をホームグランドにしていたが惜しくも急逝してしまった古澤良治郎(ds)さんについて伺った。
「とても尊敬していました。古澤さんの曲、特に<エミ>大好き。ドラムのどうなるかわからないスリルと放ちまくる人間臭さ、好きでした。プロデュース能力も抜群。ユニット「ね」を現出させたのは天才!」
また、武田和命(ts)さんについても「僕は晩年よく一緒にやりました、出来不出来がありましたが、彼の硬質音がツボに決まった時は誰もかないませんでしたね」と話してくれた。
こうした多くのミュージシャン達に支えられて早やくも39年、今では中央線ジャズの総本山とまで云われ、ジャズの拠点となっている。アケタの店にはさまざまな人が訪れそれぞれの流儀で音楽を楽しんでいるが芥川賞作家の奥泉光さんもそうしたひとりで、よく店を訪れるという。あるとき石井彰「幽玄郷」を聴きに行った時に偶然ご一緒したことがある。奥泉さんは吉野弘志と親しく、ときには吉野とのセッションでドルフィーなみのフルートを吹くこともあると云う。自由人アケタのところには自由人が多く集まるようである。
1975年に自己のレーベル、アケタズ・ディスクを立ち上げる。その記念すべき第1作は『エロチカル・ピアノ・ソロ&グロテスク・ピアノ・トリオ』(アケタズ・ディスク)で、このスタート地点ですでに自己を確立していたのである。以降「アケタの店」のライヴ録音を中心に精力的にアルバムを製作、TBMとならんで日本を代表するジャズ・レーベルに育て上げた。リリース枚数は優に3桁を超えている。ご自分のリーダー・アルバムも50〜60枚をこえるほどだそうで、あまりに多く自分でも数えてみないと正確にはわからないとのことである。
アケタは自分のアルバムの大半は自分でライナーノーツを書いているが、そのどれもがユーモアたっぷりの自伝的エッセイになっていてライナーを読みながらアルバムを聴くとアケタの人となりが浮かび上がって一層深くアケタズ・ミュージックにひたることができる。アケタズ・ディスクのライナーノーツを一冊の本にまとめていまはやりのアケタズ・ディスク・ガイドブックに仕立てたら相当面白いエッセイ集になりそうである。
そしてさらにオカリーナの演奏ではピアノ以上に天才ぶりを発揮する。
『シチリアーノ』(アケタズ・ディスク)というアルバムがある。6年ほど前の作品であるがこれほど面白いアルバムも世のなか滅多にない。なんでも、このアルバムの<シチリア・マフィア・ブルース>という曲の演奏の途中でチェロの翠川敬基とリードの藤川義明が喧嘩をはじめ、ついには殴りあいの音までも忠実に録音してあるということで知られているらしいが、その冒頭で演奏されるアケタさんのオカリーナが格別に素晴らしい。オカリーナはジャズを演奏する楽器としてはまだ少数派であるが、どうして、アケタのオカリーナのブルースは泣ける。話題の喧嘩についてはスピーカーの音量を上げて聴いてみると確かに二人の絡み合う様子が浮かんでくる。しかし、そうした俗っぽい興味よりもこのアルバムのアケタのピアノとオカリーナのプレイは神がかって素晴らしいし、藤川のアルトもフルートもドルフィーが舞い降りたように乗っている。アルトとソプラノの2管同時演奏まで入っている。アケタさんはこのように演奏途中でアクシデントが起きようとも演奏がよければそのまま正直に世に出すという信念をお持ちのようだ。また、この演奏を中断することなく音を録り続けたアケタの専属エンジニア、島田さんもまさに筋金入りのアケタ・ファミリーである。
アケタのもうひとつの顔が「アケタオカリーナ」の開発と製作。株式会社アケタの社長としてオカリーナの製作と普及に力を注いでいる。アケタさんの父、孝さんはオカリーナの音色に魅かれ発祥の地イタリアから日本に持ち込んだ先駆者。それまで10個が標準だった指穴を12個に広げ、半音を正確に出せるように独自に「オカリーナ」を開発しオカリーナの可能性を広げた「アケタオカリーナ」の創設者で、孝さんのアトリエからは火山久など多くのオカリーナ奏者が巣立っている。アケタは父、孝さんを深く尊敬していて、音楽研究家であり、彫刻家であり、画家でもあった孝さんの作品をご自分のアルバムのジャケットで数多く発表している。また、その後を継いでオカリーナの工房を守った母カヅさんを敬愛し、オカリーナの工房の発展に心血を注いでいる。だからアケタさんの吹くオカリーナのブルースは魂のブルースなのである。アケタさんは折に触れて、「アケタオカリーナ祭り」を実施し早世した父、孝さんの功績を讃え、オカリーナの普及に努めている。アケタを語るとき父、孝さん抜きではアケタの真実は伝えられない。アケタの音楽、そして生き方には父、孝さんの姿が投影されているのである。「父は僕の心の支えです。父のやろうとしていたことは手に取るようにわかるような気がします」そして「芸術的感性では同じものと思っています。少なくとも郷愁と哀感は同じ血を分けていることを痛感します」。父とご両親の故郷である北魚沼に思いをはせた<孝と北魚沼の旅情>はセンチメンタルな思いがつのる名曲で何度か録音している。「僕に映る北魚沼は父の作品とも重なってすごく日本的郷愁を感じるのです」と語る。
今年も11月23日から27日迄の5日間、アケタの店で「アケタオカリーナ祭り2013」八十年の伝統とともに、現在を生きる、を実施する。http://www.aketa.org/matsuri13.html
ここに来るまでには大変な苦難もあったと思うがアケタはアイデアと行動の人、笑って乗り越えてこられたように思う。
「店をなくしたら自分の存在はなくなってしまうという思いから、店はつぶれないと思い込んでいますね。だからつぶれないための動きは自然におきます。例えば店の空間、ジャズだけでは大変なので、オカリーナ作りにも使う。ジャズで厳しい時、良いジャズマンを良い客の入る他ジャンルのユニットにゲストとして入れ、そういう特集で利益を上げる」その根っこには質の良い音楽を提供することが大前提となっていて、「常に客集めに質を落としたジャズはやらないように」心がけているという。
そして昨今のきびしい環境のもとでこれからの方向、道筋についても伺った。
「ビルの立て直しがいつあってもおかしくないです。その時、一時移転する気力をもたなければならないとは思っていますが、どうなるかわかりません。オカリーナと父の美術を展示できる記念館のようなスペースも夢です」
もし、あなたがまだアケタの生の演奏にふれていないのだとしたら、一度「アケタの店」を訪れてアケタ・トリオ、アケタの長いカデンツアを聴けばピアノ越しに揺れるアケタの背中に真摯な求道者の姿を感じとることができるかもしれない。自称「天才アケタ」はあながち自称だけではない。


 1.31 '16
1.31 '16![]() :
:![]() :
:![]() :
:![]() :
: