
長いトンネルを抜けるときには、それがそうだとわかるものだし、何に囚われていたかも次第にわかってくるものだ。

<track 140>
三月の水Aguas de Marco (Waters of March) / Antonio Carlos Jobim from 『Jobim』
ジョビン自身が苦悩の果ての再生を果たした曲であったらしいけど、自伝とか読むのはまたあとでね、歌詞は・・・ええとここにあります→ http://blog.goo.ne.jp/bozzo173/e/a83780df6e945173520e3d565a2fe96f
絶望の淵にあったことがあったとかなかったとか、だれかはだれかの昔話をきくこともあるかもしれない。菊地成孔の粋な夜電波でこの曲流れて、即座に泣けた。このトラックがぼくを触発し、何か次の場所まで行けるような気持ちにさせた。
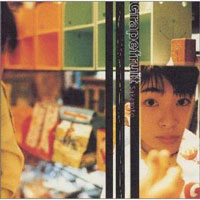
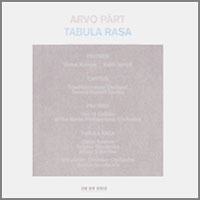
<track 141>
Feel Myself / 坂本真綾 Maaya Sakamoto from 『グレープフルーツ』 (Victor Entertainment) 1997
アニメ『荒川アンダーザブリッジ』(傑作だよん)のDVDを観ていて、金星人を自称する電波系美少女ニノ159cm43kgの声をやっているのが坂本真綾かあ、と言っている、今ごろ!わはは。おいらの遺伝子史上最高傑作は第一子の長女かなみん24さいなんだが、アニメ好きだとか腐女子だとかいろいろ言うが、いつもアニメの世界にいるような毛糸の帽子をかぶって夕暮れお魚屋さんのOL仕事を終えて帰ってくるのを、かわいくてこないだは抱きついてきた(!)、2さいの頃府中競馬場に肩車をしてダービーの馬券を買いに連れていった小さな公園、「おぼえてるよ!おとうちゃんのおでこがあぶらでべたべたしてやだなーって思ってた!」。ニノにそっくりになってるし。
坂本真綾を聴いたのは、ミシェル・ドネダ〜斎藤徹『春の旅 Spring Road 01』をrovamimi Jazz/Improv AWARD 2002年間ベストに挙げた(http://homepage3.nifty.com/musicircus/rova_n/2002.htm)翌年に『少年アリス』(これぞ最高傑作!)からかな。
デビューアルバムの1曲目、坂本真綾と菅野よう子の第一子(おいおい)がこのフィールマイセルフである。
「あの日 突然に 離ればなれになった瞬間でさえも思ってた 君のこと 好きになったことも 忘れないことも 大丈夫だって」、失恋とか離婚とか大震災とか、人生にはこれでもか!というくらい辛いこともあらあな。
ギターのストロークから始まって、鐘の音が鳴る。サウンドの背景に鐘の音が鳴り続け、5:00からいきなり空中に投げ出されるような浮遊感、これは驚くべき音響効果である、この謎は解けていない、そして、楽曲がギターの最後の一音を響かせたあと、その残響の中に、鳴り止んだはずの鐘の音がまざまざと立ち現れてくる。
こ、これは!ECMニューシリーズの第1作『アルヴォ・ペルト:タブラ・ラサ』ECM1275(「現代音楽の風景を一変させた」と評される歴史的な作品)の「ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌」での鐘の響き、・・・オーケストラが沈み込んだ轟音を響かせて終わってゆくのに、オーケストラが響き終わって静寂が現れるところ、鐘の残響がふぁーんと立ち現われてくるあの身動きできない音楽的体験ではないか。
これがペルトの「鈴鳴り(ティンティナブリ)形式」だと昨日まで思っていたよ。チガウのね(ティンティナブリ形式http://akihikomatsumoto.com/maxmsp/arvo.html)。堀内さんご指摘ありがとうございます。
え!このフィールマイセルフの残響を検証された福島さんから、ギターの最期の一音の残響が鐘の音の残響音程と一致しており、実際には鐘の音は聴こえないにしても、明らかにそれを狙っている菅野よう子の天才性を指摘された。・・・え?鳴ってない?おれのグランディスで大音量でかけるとたしかに鳴っていた気がするのだが・・・ほんとだ、鳴ってないや。
というわけで、凶悪なふたりの耳のアニキとこの曲を共有できたことだ。深謝。
この坂本真綾のファーストは捨て曲なしの名盤なんだが、「約束はいらない」でもこの鐘鳴りアレンジは実に効果的に施されており、加速はパットメセニーを思わせるし、2:00に突如バグパイプが大地から響き渡るさまは・・・

<track 142>
ラブリー / 小沢健二 from 『ライフ』 1994
「ライフ・イズ・カミン・バック!」、おざけん26さいの声を書きたいのだ。
この音楽に出会ってしまうような出来事が、いま悲しみの淵にいるようなぼくや誰かにもきっと訪れますように。それで、この音楽の純度が、そのまま現在までの小沢健二の歩みに続いているということ。
東京タワーをバックに背伸びをする内ジャケ。
「あれ?こないだフリッパーズ・ギター、再結成したよねえ?」と昨日きいたぞ。ほんとかよ、「恋とマシンガン」のスイング感でジャズなんて一発さ。ジャズ喫茶で「ECM全部聴いてきたよ、でも小沢健二のライフ一枚あればみんな要らない」と言って誰かさんを困らせたりしたっけ。
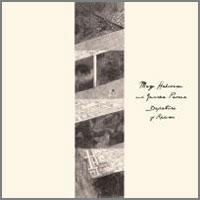

<track 143>
That Other Thing / Mary Halvorson and Jessica Pavone from 『Departure of Reason』 (Thirsty Ear) 2011
さあ、これまでの流れから、現代ジャズのめがね女子メアリー・ハルヴァーソンのギターに耳をすますのがタガララジオの流儀だ。この経路でやって来なければきっと迷うと思うんだ。ジャズだと思うから、インプロと思うから、新しいと思うから、Thirsty Earだと思うから、アンソニー・ブラクストンとこの学生だと思うから、あれ?あれ?となる。・・・ならないか。
準拠するモンが無い自由というのかなあ、フリージャズでもアヴァンギャルドでもないよこれ、不思議な道なき道を行く童貞力のチャーミングさだ。こら!メアリーに童貞力言うか!
ハルヴァーソンに注目したのは、コンポストを熟読したいた頃に八田真行さんのレビュー(http://com-post.jp/index.php?itemid=386)で即購入したんです。
彼らの頭ん中にあるのは、フリッパーズ・ギターみたいな全音楽引用を無邪気に編むような楽しくて楽しくて仕方ないという創造のかたちだ。分析するのは困難かもしれない、だけど、中に入ってしまうことだ。そりゃどんな音楽でもそうだろ!
・・・でも、なんでこのかわいいポートレイトがジャケじゃなかったのお!2枚買ったんだぜ、がっかりだぜ、ポスターにしてくれよ。


<track 144>
Ballad 1 / Masabumi Kikuchi Trio from 『Sunrise』 (ECM2096) 2012
プーさん(菊地雅章きくちまさぶみ)のインタビューがニューヨークタイムスに掲載された(http://www.nytimes.com/2012/03/25/arts/music/masabumi-kikuchi-finds-new-direction-with-sunrise.html?_r=1&pagewanted=all)。
「Floating in Time, Hiding in Sight」
浮遊するサウンド、音の背後でそれは見えない
・・・ぜんぜん意訳になってねえ!が、本質を見据えたいいタイトルじゃねえかNYタイムスよお。
深夜にEXILEのDVDで岡村隆志が警備員姿で闖入するRising Sun聴いてカンドー(岡村ちゃんのダンスうまいよ!おお日本が復興するための歌なんだなあ!)してたんだが、SunriseのプーさんがNYタイムスにという・・・、ポリドール時代にBambooレーベルを立ち上げてコアなJAZZシーンを牽引した五野洋さんがFaceBookでシェアしたのをかわきりに、トリオレコードにいた原田和男さん、現代JAZZ批評家益子博之さん、カッティングエッジなレーベルSongXJazzを駆動する宮野川真さん、そして我々現代JAZZリスナーを育ててくれたマーク・ラパポートさんが次々と祝砲のようにシェアしている。ラパポートさんは、40年かかったがラブユー!プー!と短かくも万感伝わる投稿だ。
プーさんは演奏にまったく満足していなかったところ、モチアンが心配して、その録音に介入し、2曲カットしてアイヒャーと仕上げてしまったんだようだ、それを聴いてプーさんは耳をチェンジしたってんだから、凄まじいものだ。ジャズの現代史だ。
ニューヨークタイムス、ちゃんとプーさんの、あえて書くけど現代性を、認識してる。欧米のクリティークは、テイボーンの新しさにもキチンと反応していたし。能も、石庭も、怪談も、欧米に見出されて自分に気付いている日本だったりしているのと同型なのかい。
プーさんはシンプルに「自分のランゲージを深めているだけだ」「アヴァンギャルドを演ってるんじゃないよ」とだけ、読者向けに基本的ななヒントを与えている。ぼくにはメアリー・ハルヴァーソンのうなじにも「Play Your Own Thing」にも、「Stay Hungry, Stay Foolish」(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20110713)にも聞こえる。
プーさんからメイルがきた!「ちぇきら!check it out」と、このサイトを教えてくれた。「Legends Is Here」 http://dothemath.typepad.com/dtm/2012/03/the-legends-are-here.html
プーさんに教えてくれたのは モチアン好きの写真家John Rogersだそうで、おお、プーさんのこの表情!がすべてを伝えてくれますね。あー、なみだ出てきた。

<track 145>
序 Jo / 紫絃会 from 『舞楽 春鶯囀一具(しゅんのうでんいちぐ)』(日本伝統文化振興財団) 2012
ヴェサラの『ナン・マドル』(ECM1077)、(http://homepage3.nifty.com/musicircus/ecm/e_hl/004tx_01.htm)参照、
に雅楽の響きを聴き。
『ジャパニーズ・トラディショナル・ミュージック 雅楽・声明 1941年』に、雅楽の古層を耳にしていた(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20090814)。
しかしながら、この録音・・・、聴き始めて身動きができなかった。
深夜の八百万の山河がわきたつようだった。圧倒された。この圧力、この力量、この漲り。聴きながら必死だ。
「楽師の名前をみただけで、雅楽に関心の深い方には目も眩(くら)むような思いではないでしょうか。サッカー・ファンであれば、ペレ、ベッケンバウアー、プラティニ、マラドーナ、ロベルト・バッジョ、ストイコビッチ、ジダン、メッシの名前が並んでいるのを目にするようなものでしょう。」(じゃぽ音っとブログ「雅楽 新しき古き響き/木戸敏郎・武満徹」http://d.hatena.ne.jp/japojp/20120222/1329906981)
そこまで書きますか堀内さん、と、アマゾンして・・・CDプレイヤーのスイッチを止められない、動かし難く、引力が・・・スピリチュアル・ユニティみたいな出会いだぜ・・・不用意に聴くと頚椎がやられるぜマジで。そ、それにしても何なんだこれは。ああ、雅楽ね、なんて絶対一蹴できないって。お正月にテレビから流れる雅楽は全部ウエハースだ。これぞまさしく原液。漆黒の闇の中、四方八方から矢が飛んで来て、足元には撒きビシ、身動きはできない。笙の響きのゆらぎ具合、笛の空間描出、鳴り物の絶妙、・・・あらゆる耳の聴取の必殺技が完封されている体で必死なのだ、顔はひきつり、・・・このサウンドの畏怖は。
全国で(つまり全世界で)18枚しか初回予約が入らなかったというコアなブツになってしまってはいけないだろ。全国の自治体および教育機関の図書館仕入れ担当者の皆さま、民衆のリクエストに応じてAKBや五木博之やジブリのサントラの同一作品を6点も揃えることだけが責務ではないと思います。

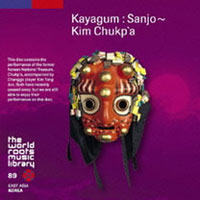
<track 146>
西村朗:覡(かむなぎ) / 沢井一恵・齋藤徹 from 『THE SAWAI KAZUE』 (邦楽ジャーナル) 2011
これまた凄いものを聴いてしまった。わたしと堀内さんが主宰する音楽サイト「musicircus」で、「2011年に聴いた10枚」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/)という企画を、多田雅範、堀内宏公、若林恵、長井明日香、岡島豊樹、福島恵一、益子博之、原田正夫(敬称略)、ONE PIECEの面々が音楽の海原を海賊するイメージで、わたしは読んだわけですが(すいません)、日本の伝統音楽の深淵を探求する堀内さんと、インプロから音響からディストピアアンビエントまで論ずる耳の熊楠たる福島さんがともに沢井一恵の本作をピシッと棋盤に金将を指すような、選出。
イントロから、到来するような気配・・・。楽譜の根底にある韓国リズム「クッコリ」の原形に近いところで演奏したくて、楽譜に指示された打楽器ではなくコントラバスの齋藤徹との協演となったという。・・・西村朗も、沢井一恵も、齋藤徹も聴いてきた、し、7手先までは余裕で読めるゾ、なんて構えで聴こうとする自分がいて、しかしね、薪で炊いたごはんの味わちがうううんですよお、というオバハンみたいで、どこがどう美味しいとかグルメンなこと言えんのですが、演奏にトランスしていたとか憑依していたとか所在がわからなくなる時間にこちらもチューンインしてしまう演奏だし、現代音楽のコンポジションにも十七絃にもコントラバスにも還元できないもんが、そこには西村も沢井も齋藤もいないふうにただただこちらは漂って聴いて、いみじくもライナーで齋藤が「録った音を聴くと生き物のようにうねっている」と書いたところに到着する。
ラジオは桜前線が長崎に岡山に、今年は遅いですねと話している。ぼくは「2011年に聴いた10枚」で『韓国の伽耶琴(カヤグム)/金竹坡』を耳にして、おそらく共時的にここに来ていたのだろうかと思う。韓国も日本も音楽のつながりは太古から綿々とあることが感じられるし、西村・沢井・齋藤は今ここでという現代性でリレーしている。この圧倒的な贈与された感覚、途方もなく届かない思い、といったものは、個人的にはECMを聴き始めた頃の価値と地続きである。おいおいマンフレート、このCDはアマゾンでも売ってないゾ、邦楽ジャーナルでしか購入できないぞ、なんなら送ってあげようか?そっちでは桜前線を待ってうきうきしているアジアの片隅のわたしにはなれないって?

<track 147>
Current / 橋爪亮督グループ from 『アコースティック・フルード ACOUSTIC FLUID』 (tactilesounds records) 2012
そうそう、マンフレート、あなたが拓いた音楽の地平から新しい才能が!・・・という書き出しになってしまうが。
オリジナルなヴォイス。これを獲得したサックス奏者橋爪。天性のメロディー・メイカーの橋爪。そして、市野、橋本のプレイに耳をすますと、橋爪がニューヨークに行かなかった理由が判然とする。>単独のCDレビューを掲げました


<track 148>
E.E.Tension and Circumstance / Keith Rowe - John Tilbury (Potlatch P311) 2011
04年にキース・ロウはAMMを脱退しているんだって?・・・AMMはプレヴォーとティルベリーのふたり組になってしまったのか。ふうううん、て、あんまり関心無さげ、M.I.M.E.OとPhosphorまでは追いかけたこのシーンではありましたが最近聴けてません。キース・ロウは好きでねー、『AMM III / It Had Been an Ordinary Enough Day In Pueblo, Colorado』(Japo/ECM)を最初に聴いて今でも「Radio Activity」を脳内再生させてうっとりとしている。
キース・ロウはあれだ、グルジェフ信奉であるし、禅とかが基盤にあって奏でているだろ。AMMが即興シーンで孤高の存在だった理由のいくばくかもそこか。弱音系だか音響系とかの新しい世代は、彼から出てきた系譜ではないだろうか。アーストワイル(レーベル)の良さも、そうだね。デヴィッド・シルヴィアンがアーストワイルのスタジオに来たりしていたのも、つながる。
血の味がする即興レーベル“ポトラッチ”から、ロウとティルベリーのデュオ、仏アンスタン・シャビレでのライブ、がリリースされた。
ちょっと驚くような穏やかさで、おれは深夜の京都の寺の中でじっとしているようなイメージに包まれていた。ピアノは鍵盤で祈るような打音を、ギターというかAMラジオのようなノイズを・・・。稚拙なんだか素朴なんだかというイラストのジャケになぜだかぐっとくる。
なんとキース・ロウの亡くなった兄弟の手によるもので、ロウは母親の筆跡に似せてクレジットを筆記しているという。03年のデュオ作はティルベリーの母親に捧げられた演奏でアーストワイルからリリースされており、本作は10年のデュオ作品。
ああ、そういう録音なのです、感じます・・・。即興とかAMMがそういう演奏を許すのか!と原理主義者みたいな意見もあるかもしれませんが、え?ナシなの?そんな偏狭な制約は無いでしょう?とわたしは思うわけです。

<track 149>
Mirror Balls / DCPRG from 『Alter War In Tokyo』 (Impusle!) 2011
この2枚組のラストトラック。「ニセコロッシJAPAN2011http://homepage3.nifty.com/musicircus/rova_n/rova_r32.htm」で書いた、耳の飢餓感を煽るブラコンのバックトラックみたいな快楽は、その演奏の最後にキーボードは余滴のようにビーチボーイズのグッドヴァイブレーションを仄めかすキーを置いているところでブレイクする。それはもう熱病のウイルスのように、予感を暗示する。アメリカンミュージックが視た夢の果実のひとつである。アップル・コンピュータだよ。Stay Hungy, Stay Foolish が向こう側に見えるんじゃないかと思うような。
二月堂のお水取り、3月12日深夜、奈良へ向かう東名高速でこの曲になみだが出てきた。3月のお水取り、ジョビンの「三月の水」じゃねえか!・・・なんて子どものような言葉遊びは本気だい。
菊地成孔の公式サイト第3インターネットで、ミュージックマガジンを撤退します、という記事!(http://www.kikuchinaruyoshi.net/2012/03/23/ミュージックマガジンから撤退します/)松尾、寺島、後藤、中山みんな出てきて、つい平岡正明著『毒血と薔薇』の解説で書いた寺島×平岡論争読み解きまで思い出す。そこには「清水先生亡きあと」と文字が並び、思えば菊地も大友も清水俊彦チルドレンであるはずだ。帝王油井正一は清水俊彦に阿部薫へ連れて行かれて「こういうのはわからない」と言ったという。すごい逸話だな。こないだ後藤雅洋が菊地雅章を「わからない」と書いたのもえらい。・・・この、菊地が後藤をディスった直後にコンポストで村井康司が素晴らしい菊地成孔特集を始めた。ちょっと政治のにおいでうまく読めない。菊地成孔、日本ジャズ村を完全制覇の観が。アウンサンスーチーか。みんな出てくるオペラみたいだ。
わかった音楽は次々と生彩を失ってゆく。わかるようなわからないような謎が音楽を聴かせる。衝撃は謎だ。あなたのことがもっと知りたい、だから音楽は女神。
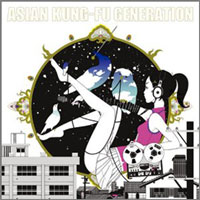
<track 150>
RE:RE: / Asian Kang-Fu Generation from『ソルファ』 2004
中学生になった次男が「アジアン・カンフー・ジェネレーションていいんだよ!」と言い、おれは「なにい?エイジアン・ダブ・ファウンデーションのほうがすごいぞ!」と返答していたあの日。次男と日本武道館へアジカンを聴きに行って、アリーナで立ちっぱなしのライブは気持ちは乗っても体力が続かないのでそれ以来引退している。アジカンとバンプでおれの中のミスチル時代が終わり、アジカンバンプ時代はラドウィンプスで終わりを告げ、そのあとは相対性理論、世界の終わりが一枚だけ熱病になって、去年はHIATUS(ハイエータス)だったかな。少女時代か。
これが阿波踊りのリズムだなんて、ほんとうだー!
長井明日香「2011年に聴いた10枚」http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/tx_3.htm

<track 151>
Salvatore Sciarrino : Variazioni for violincello and orchestra (1974) from 『Orchestral Works』 (KAIROS) 2008
昨年は震災の影響で延期された「コンポージアム2011(http://www.operacity.jp/concert/compo/2011/110525/)」が1月に行われた。悠さんのレビュー(http://www.jazztokyo.com/live_report/report402.html)「音響についてのとらえ方の変更を迫られる思いを強くした」という、わたしもこのCD3枚組を聴いてのけぞっています。サルヴァトーレ・シャリーノ。こんなに耳に鮮やかなのはペルト、シュニトケ、グバイドゥーリナに遭遇した以来のことだ。現代音楽のCDでこんなに没頭できるのは『射干玉(ぬばたま) ── 小山薫の世界[作品選集]』以来だ。
叙々苑の焼肉を食ったら牛角では食えなくなるだろましてや安楽亭では。
ふふふ。サルヴァトーレ・シャリーノ、それから、ジル・オーブリー、この視野とレベルの音楽は確実に到来するだろう。耳の臨界点はがーっと上昇して、もう昨日までの音楽はバスの最後部で見送る景色のようだ。
現代音楽を現代音楽たらしめいてるのは、オーケストラの表現だろう。おお、すごい誤った断定。オーケストラの維持とか音楽学生の作曲家育成費用とかのインフラにどれだけの税金が投入されているのか明らかにするような現代音楽評論はどこかにないのだろうか。

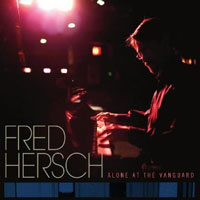
<track 152>
Old Devil Moon / Fred Hersch and Nico Gori from 『Da Vinci』 (bee jazz) 2012
2010年の年末、ジャズの殿堂、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードで75年の歴史の中で初めてピアノ・ソロでの一週間公演(6日間12セット)を果たしたフレッド・ハーシュ。このライブはCD『アローン・アット・ザ・ヴァンガード』(Palmetto)となり、即座にハーシュはグラミー賞にノミネートされた。
フレッド・ハーシュ。1955年オハイオ生まれ、子供の頃からピアノを弾き始め12才のときにはシンフォニーを書いている神童。ボストンのニューイングランド音楽大学で教鞭をとる。あのブラッド・メルドーが教え子だときいてメルドーの謎はいくばくか解けた(メルドーはレディオヘッドとハーシュでできている!)。バッド・プラスのイーサン・アイヴァーソンも教え子である。いわゆるミュージシャンズ・ミュージシャンの存在ではあるが、ハーシュはビル・エヴァンスを研究しつつ、その後のジャレット、メルドーの数十年にわたる王権を、ジャズ語法的に空中に跳躍させるのではなく、執拗に一音一音正攻法で音のロジックを追い詰めてゆく手法で覆そうとしているようだ。
この「エヴァンス〜ジャレット〜メルドー」を根こそぎ更新してしまうピアノの技術や質感は、むしろクラシック界のシフやピリス、岡田博美との参照で捉えるべきものかもしれない。それはいわゆるジャズやクラシックの越境といった事態ではなく、自然に音楽が進み出た視界なのではないだろうか。その意味で「ハーシュは21世紀の革新者である」(ニューヨーク・タイムス)という指摘は正しい。
ハーシュは08年に持病のエイズが悪化、昏睡状態から、気管を切開してチューブで摂る状態が8ヶ月も続いていたとのこと、そして、奇跡の復活。死の淵から帰還したハーシュの演奏について、天使の指を持つとはただの形容句ではない。おれはね、音楽の神さまが「ちょいとフレッド、まだ弾くべきトラックがあんじゃねーの?」と、
それはこの冒頭の躍動に現れていると思うんだけど・・・。
<track 153> ( 01 track ) / TPT Trio : Thomas Morgan (b), Masabumi “Poo” Kikuchi (p), Todd Neufeld (g)
ハーシュもプーさんも、音楽の神さまから地上に返されてきたってわけか!
NPR(National Public Radio)が「プーさんと呼ばれるピアニスト(A Pianist Named ‘Poo’)」という動画付き記事を掲げた(https://www.npr.org/blogs/ablogsupreme/2012/03/26/149407481/a-pianist-named-poo)。これをFacebookでシェアしてくれたのは益子博之で、昨年の名盤『Motian Sickness モチアン症候群』(オレのベスト10>http://homepage3.nifty.com/musicircus/rova_n/rova_r32.htm)のジェフ・コスグルーヴがシェアしたものだそう。・・・うー、世界が正義と信頼に満ちてきたみてえだ...
昨年のグランプリ覇者(益子博之=多田雅範音盤茶話会アワード2011)である建築鍵クレイグ・テイボーンが、トーマス・モーガンとのトリオをぶち上げてきた!これもNPRによるもので音が聴ける>「Craig Taborn Trio: Live At The Village Vanguard」(http://www.npr.org/event/music/149499552/craig-taborn-trio-live-at-the-village-vanguard)
NYのプーさんに、ほらほらテイボーンがモーガンとのトリオを演ってるよ!と言いつけたら、すかさずムッとしたのか「先週のおれたちの録音は凄まじかったぜ!3年はこのTPTを演っているが、相当のもんだと思う。聴かせてやりたいがな。」なんて返ってくる。ううう、ここはケニー稲岡に頼むしかない!おれの前では吼えるマラドーナ稲岡なんだが、CD日本盤化に際しヘンリー・スレッギルに堂々と交渉できたり世界的に最も信頼されているケニーだけあって...TPTのプライヴェート音源を一緒に聴くことができたっ!
TPTはピアノ、ベース、ギターというドラムレスの編成。おれは彼方にジョー・マネリ尊父の『三人歩き(ECM)』(ダウンタウンの伝説盤)や嚆矢であるジミー・ジェフリー3までを耳に招聘する。
ベースのモーガン、ギターのネウフェルド、同じ81年8月生まれの30さい、ともにプーさんやモチアンに負けない耳の良さがわかる。プーさんというと、ピーコック、モチアンとのテザード・ムーンの黄金のトリオが挙がるが、もうピーコックはいらないだろう、この二人モーガン、ネウフェルドの若き畏れを知らない才能にプーさんのピアノはさらに先に出ている。プーさんはこの演奏に“ensemble improvisation”という語を用いている。おれは...、名人の舞う能を感じさえしている。
間違いなくモーガンのベースは世界最高峰に到達している。
モーガンが化けたと世界で最初にぶち上げたのは、お、おれだぜよ。07年の『日野=菊地クインテット/カウンターカレント』(SONY)に愛情を込めて「足を引っ張っているのが世界のヒノテル」と記したレビュー(http://www.jazztokyo.com/newdisc/558/hino_kikuchi.html)、「じじいのせんずり見せつけあいショウにおれたちはついてゆけない」という名セリフを刻んだ『ポール・モチアン Trio2000+Two/オン・ブロードウェイ vol.5』のレビュー(http://www.jazztokyo.com/newdisc/571/motian.html)がその証拠だ。
益子博之が『Sunrise』について、モーガンのベース音へのフォーカスを指摘しており(http://com-post.jp/index.php?itemid=581)、堀内宏公(http://www.jazztokyo.com/five/five885.html)も「モチアンの関与の核心はそこでしょう」と分析していた。おれは「モーガンがすげー!」(http://www.jazztokyo.com/five/five879.html)としか言えてなかったな。
ギターのネウフェルドは、タイショウウン・ソーレイやジェラルド・クリーヴァー、ダン・ワイス、トニー・マラビー、武石務らとの活動をしており、自己のグループでのビリー・ミンツBilly Mintzというドラマーについてはわたしはちょっとときめいたりしているのだが、と、まあ、ミュージシャンつながりを言うのも何だが、見逃せない存在だ。
TPTの演奏がひとたび始まれば、身動きできない漆黒の無重量状態になってしまう。今はそうとしか書けない。
日本はTPPではなく、TPTに襲われるべきだ!(あちゃー)
¿ギターのTodd Neufeldは、ドイツ系。Neufeldは、英語ではNewFeild、発音はノイフェルトだけど、そちらではどう発音してるんですか、と菊地さんに尋ねたところ(これからの人なんで最初の導入が肝腎)、ヌーフェルトだ、っていわれました。Toddはタッドと読ませる人もいますが(MAレーベルのタッド・ガーフィンクル)、彼の場合はトッドとのこと? TPTは6月来襲のウワサもあるので、トッド・ヌーフェルトで行きませう。?(稲岡)
Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
