
1. �����Ƃ��悤�@����
�{���F�������m
1932�N7��17�����s���܂�B2011�N7��21�������ɂĎ���
���s��w�o�ϊw�����ƌ�A1956�N���{�M����s�ɓ��s�B1960�N�A�ސE��A���y�]�_�ƂƂ��ēƗ��B�w�X�C���O�E�W���[�i���x���̃��R�[�h�]�S�������o�āA
1969�N�@���y�G���w�j���[�E�~���[�W�b�N�}�K�W���x�i1980�N�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�Ɏ����ύX�j�n���A89�N�܂ŕҏW���߂�
1982�N�@���y�A�[�J�C���ɏœ_�����Ă������w���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�x�n���B
1989�N�@���[���h�E�~���[�W�b�N��厏�G���w�m�C�Y�x�n���A92�N3���܂�13�����s
1990�N�@���g�̃��[�x���u�I�[�f�B�u�b�N�v�n�݁ASP�����Ȃǂ𒆐S�ɐ��E�̖��O�̉��y���Љ�B�I�ȁA����A�f�U�C���Ȃǂ��ׂĂ����g�Ŏ肪����B
2006�N�@�W���Y�A�|�s�����[�A�������y���܂ސ��E�e����SP�ALP�ACD�A�����A�����y����܂ގ��g�̃R���N�V����������p��w�Ɋ�
2008�N�@��������p��q�����������C
2009�N�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�����������[��ޔC
2010�N�@������Ѓ~���[�W�b�N�E�}�K�W���Ў������E�ޔC
2011�N7��4���@���g�̓��ʊďC�ɂĕ����������p�قŁu�����Ƃ��悤�R���N�V�����W�`�y��ƃ��R�[�h�𒆐S�Ɂv�J�ÁA�������ʂ����J
��Ȓ����F
�w��O���y�̐^���x�i�~���[�W�b�N�E�}�K�W��1986�j
�w��O���y�Ƃ��ẴW���Y�x�i�~���[�W�b�N�E�}�K�W�� 1999�j
�w�|�s�����[���y�̐��I�x�i��g�V�� 1999�j
�w�����Ƃ��悤�̎��W�S���x�i�~���[�W�b�N�E�}�K�W�� 2005�j
2. �����Ƃ��悤�R���N�V�����W����������p��w �b Nobucco ���c�L�q / �B�e�@�c���Y��Y
���̏f�����A�Ƃ��悤���Ɨc�ȓ���ŁA�����{��k�Ќ�A���т��сA�d�b�Řb�����Ă����B
�Ƃ��ɕς�����l�q�͂Ȃ��������A���N�O����A�����̎�����l���A��������p��w�ɉ��y�W�̎��������ׂĊ��A����̏������}���V�����Ɉ����z���A����̏����Ȃǂ��A�������Ɛi�߂Ă����Ƃ����B
�Q�O�P�P�N�V���S������X���Q�S���܂ŁA��������p��w�ŁA�u�����Ƃ��悤�R���N�V�����W�v���J������Ă��܂��B�����y��A���R�[�h�A���ЂȂǂ��W������A�Ƃ��悤�����ǂ̂悤�ɉ��y�Ɗւ���Ă����̂���H�邱�Ƃ��ł��܂��B
�Q�O�O�U�N�ɁA�R���N�V����������p��w�Ɋ��邱�Ƃ����܂�A���̓W����Ɍ����āA�����ԁA������i�߂��Ă����悤�ł��B�Ƃ��悤���ɂƂ��āA���̓W����́A���̏�Ȃ���тł���A�����ɍŌ�̊���ƂȂ�܂����B
���U�O�N��̃t�H�[�N�ƃ��b�N�̓����B���e�����y����A�t���J�ցB�u���[�X�̉��ɂ��鍕�l���y�̒T���B�C���h�l�V�A�ł̃N���`�������y�Ƃ̏o��B�A�W�A�̈�ށA�e���T�E�e���A�k�X���b�h�B�ӔN�̃��[���b�p���s�A�M���V�����y�Ƃ̏o����Ȃǂ��W������A���R�[�h�́A��ʂɂ͗��ʂ��Ă��Ȃ��A���łɎp�������Ă��܂���LP�𒆐S�ɓW���B���̑��A�Ƃ��悤���̃R���N�V�����ł���A�W�A�A�A���u�A�A�t���J�̂ǂ���������`�����������y�큃���ہA�J�A�ՁA�E�[�h�A�|���ՁA�R���A�e�w�s�A�m�A�S�ՁA�؋ՁA�_�}�������W������Ă��܂����B
�V���S���ɂ��̓W������I�[�v���A�V���P�V���ɂV�X�̒a�������}���A�V���Q�P�������B�܂�ŁA���ׂĂ��A�v�Z���ꂽ���̂悤�ł����B
�Ō�ɁA����CD�wPagina de viaje���̕���x(Jazz Tokyo)�̉���A�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�ł̏Љ�ȂǁA�����b�ɂȂ�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�莆�����o������ƁA�x���Ȃ�Ȃ�����A�������J�Ȃ��Ԏ������������A�{���Ɋ������v���܂����B
����CD�wPagina de viaje���̕���x�́A���̈�Ԃ̕�ł��B�i�^���S�E�s�A�j�X�^�j


3. �Ǔ��F�����Ƃ��悤���� �b �{���@��
�V���Q�Q���t�������e���ŕ�ꂽ�A�����Ƃ��悤������]��ɋ������l�͏��Ȃ��Ȃ��͂����B�����g�̊y��E���R�[�h�E�R���N�V�����W������Ɏ����Ȃ������Ƃ̂��ƁA���ڂ̗F�l�A�m�l�Ȃ炸�Ƃ��Ռ��̓x�����͂܂��܂��傫���B
�ނ��]��̓c�C�b�^�[�i�킽�����g�͂���Ă��Ȃ�����ǁj��ʂ��ďu���ԂɍL����A�����̂����ɁA���ړI�A�ԐړI�Ɋւ�����l��������P�Ȃ鉹�y�D���܂ŁA�����̐l���u���O�⎩�g�̂g�o�ŁA�Ƃ��悤����̐l�ƂȂ�⒘�앨�ɂ��āA�߂��߂��Ɏv���̂������f�ڂ��Ă��āA���ꂼ�ꂪ�ނ�����e���͂̑傫�������߂Ēm�炳�ꂽ�̂������B
�킽�����g�͂Ƃ��悤����Ƃ͖ʎ����Ȃ��A�킽�����܂��P�Ȃ鉹�y�D���̂����̂ЂƂ�ɉ߂����A�Ƃ��悤����ȂǂƁA�e�����ɌĂ��Ă��������Ȃǎ��炱�̂����Ȃ��̂�������Ȃ�����ǁA���y�A�Ƃ��ɃA�t���J�嗤�̉��y�̉��[���������Ă��ꂽ�t�Ƃ��Ẵ��X�y�N�g�Ɛe���݂����߂āA�����ł͂Ƃ��悤����ƌĂ��Ă����������Ǝv���B
�P�Ȃ鉹�y�D���̂����̂ЂƂ�ł���킽�����A�ʎ��̂Ȃ��Ƃ��悤����ɂ��Ă��ꂱ����Ȃǂ������܂����A���̎��i�������̂�����ǁA�Ƃ��悤����̏����ꂽ���܂��܂̕��͂ɏ��Ȃ���ʉe�������҂̂ЂƂ�Ƃ��āA�����Ɗ��ӂ̈ӂ�\���ď����������^���������Ă����������Ƃɂ����B
�܂��́A���������u���Ă������Ƃ��������b�ɂȂ����̂��A���N�Ƃ��悤���ҏW���߂�ꂽ�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x���B�h�������ɓƒf�I�ȃA���o���E���r���[�ɂ͔������o���邱�Ƃ�����������ǁi�\���ɑ����̈Ⴂ�͂����Ă��A���l�̎�|�̂��Ƃ��q�ׂĂ���u���O���������������j�A���[���h�E�~���[�W�b�N�S��ɂ킽���Ẵ��A�ȏ��A�A�[�e�B�X�g�E�C���^�r���[�����ځA�C���^�[�l�b�g�����y���Ă��Ȃ���������̋M�d�ȏ�ŁA�u�}�K�W���v�Ŏd���ꂽ�������ƂɁA���͂Ȃ��Z�{��WAVE�ŃA���o���̎����`�F�b�N�Ƃ����̂���ԃR�[�X�������BJ-pop�̈����̔䗦�������Ȃ��Ă���������A�i�X��Ɏ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���ł͖{���ŗ����ǂ݂��炵�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�D��S�����ŁA�����炭����芴���������ƌ������܂���Ă��������ȂQ�O��A�킽���ɂƂ��ĉ��y�̋��ȏ��̂悤�ȑ��݂������̂��w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�������B
�����Ă�������A�S�҂Ƃ��悤����̏������낵�A�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�̑������Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�A�A�t���J�嗤�̉��y�Ɋւ���ǂ��w�쏑�w�A�t���J�̉����������Ă���x�́A�P�X�W�S�N���s�Ȃ��獡���܂������Â������������Ȃ������ŁA�A�t���J�̉��y�ɂ��ĉ����m�肽�����Ƃ�����A�킽���͍����܂��ŏ��ɂ��̖{�̃y�[�W���߂���B���ʁA�����ʂ̉��y��y��̏Љ�A����ɂ��ω���X���A�A�W�A�A���[���b�p�e���̉��y��y��Ƃ̔�r�A�z�ꐧ�ɂ���Ď����o����A�s���������ō��t���p�`��ς������y�̂��̌�ɂ��ĂȂǑ��p�I�Ȏ��_�ł̖L�x�ł킩��₷���L���ɉ����A�i�C�W�F���A�̃L���O�E�T�j�[�E�A�f�A�K�[�i�̃J�N���o�E���r���A�t���J�̌̃~���A���E�}�P�o�̏������C���^�r���[�i�~���A���E�}�P�o�̏������͂Ȃ�ƂP�X�U�X�N�j�Ȃǂ��f�ځA�Ƃ��悤����̃A�t���J�嗤�ւ̐[�����������������B�킽�����l�I�ɂ悭�����}���A�Z�l�K���A�M�j�A������̉��y�̗�������o���A�܂��\���Ńf�r���[����O�́A�T���t�E�P�C�^��b�X�[�E���h�D�[�������ꂼ�ꏊ�����Ă����O���[�v�̂����{�[�J���X�g�Ƃ��ďЉ�Ă��āA���̂Ƃ����łɔނ�ɒ��ڂ��Ă������Ƃ��M�i�������j�킹��B���łɁA�T���t�̏������Ă������E�U���o�T�h�D�[����C���E�o���h�A���b�X�[�̏������Ă����G�g���[���E�h�D�E�_�J�[���Ƃ������o���h�����Ă�������́A���ꂼ��̓`�����y�Ƀ��e���̗v�f�������A���A�t���J�����̉��y�̐V��������̖��J���ƂȂ��������ŁA���́w�A�t���J�̉����������Ă���x�ł́A���̃o���h�̏Љ�������Ă��̎���̉��y�����������ƋP���Ă���l�q��`���Ă���Ă���B
�Ƃɂ����A�ǂނ��тɉ�������V�������������邵�A���ۂ̉��y���O�ɂ��łɂ킭�킭�������邱�ƊԈႢ�Ȃ��̈���Ȃ̂ŁA�����炭������łɂȂ��Ă���Ǝv������ǁA�����ǂ����ŋ��R�Ɍ������琥�����������߂������B
�Ƃ͂����A�p�������Ȃ���A�킽���͂Ƃ��悤����̑��̒��앨��ǂ��Ƃ��Ȃ��A���ʓI�ɔނ̎������������ɂȂ��Ă��܂����̂͒x���Ɏ����Ă��܂����̂�������Ȃ����A����ɔނ̏Љ�邳�܂��܂ȉ��y��m�肽���Ȃ艽�����I�[�_�[�����Ƃ��낾�B
��w�𑲋ƌサ�炭��s�ɂ��߂̂������A�T�O�N��㔼���特�y�Љ�L���𓊍e���Ă��������B�t���[�ɂȂ��Ă��炨�S���Ȃ�ɂȂ�܂ł̂�����́A�킽�����Љ��܂ł��Ȃ��A�����̉��y�t�@���̒m��Ƃ��낾�B�S���Ȃ鐔���O�ɂV�X�˂̂��a�������}����ꂽ�����ŁA����Ȃ��N�ɂȂ��Ă����Ƃ͂܂������m�炸�A�ł��ł��邱�ƂȂ�Ȃ����̂˂�������m�ŁA�J�^�J�i�\�L�ƃA�O���b�V�u�Ȍ��t�����̑����A�Ƃ��悤����Ɠ��̌����̕��͂ɂ����������ڂɂ����肽�������B
�v���C�x�[�g�Ȏ���͉����m��Ȃ����A�F�������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��邪�A���炩�ɂ����艺�����ƋF��݂̂ł���B�S��育���������F��\���グ�܂��B�i�����}����g�ًΖ��j

4. �����Ƃ��悤�搶�@�Ǔ� �b G2us�@���J�G�i
�ނ�ł�����ݐ\���グ�܂��B
���܂�̋����ɖ��������Ƃ��Ď~�߂������Ƃ����̂��{���ł��B
�Ƃ��悤�搶�́A���Љ�I�ȃ��b�N�����[���ɁA�^�����ȑ��ݗ��R��^�����l�B
�X�g�[���Y�̏����\�͂ɁA�����ȎЉ��^�����l�B
�q&�a�̐��_�����y�W���[�i���Y���ɁA���Ƃ��č��ݍ��l�B
���̋Ɛт͂��܂�ɂ��̑傷���Č��t�ł͌�肫��Ȃ��B
�����n�߂Đ搶�ɂ��ڂɂ��������͍̂��Z��N�̂Ƃ��i�������40�N�O�D�D�D�j�B
�����̐V�������y������T��V���|�W���E���������ăX�g�[���Y�̉�������Ă���ꂽ�B
NMM�i�w�j���[�E�~���[�W�b�N�}�K�W���x�j���ŕ����͌��Ă�������ǂ��A����ۂ́A�h�炬�̂Ȃ��C���e���W�F���X�̒��ɐl���ݍ���ł��܂��₳�����̂���l�B
�������A���ɋ����A���Ɋ����������A����͉���̓r���Ń��R�[�h����������̂�����ǂ��A�搶�̒����������܂�ɂ������B
�X�g�[���Y�́w�X�e�B�b�L�E�t�B���K�[�Y�x���㗤����������Ł@���̒��́��u���E���E�V���K�[�����Ă���Ƃ��̐搶�̐g�̂̓����i�����đ傫�������ł͂Ȃ��j�B
���́A���̂Ƃ������A�����I�A�{�\�I�Ȃ��Ƃ��������B
�����܂Ō����ɉ��y�������Ă���w�������x������̂��D�D�D
�����܂Ō����ɉ��y�̊�����\��������������̂��D�D�D
�e������蕥���Ă܂������ɉ��y�ƌ��������S�ӋC���w�B
����ȗ����͊��S�ɂƂ��悤�搶�̃~�[�n�[�ł������B
���̓��A�V���|�W���E�����I��������ƁA���Q�����m�l�l�ɃT�C�������Ă��炢�A��������Ă�������B
���ɕς�������Z���ł������B
�����������y�����ɋ���ł������́A���Ƃ��閈�ɁA�搶�����������ĕ����Ă�������B�ܘ_�A�߂����ɗ��Ă͂��炦�Ȃ��������D�D�D������Â������B
�u���O�̂�鉹�y�͂܂���Âł�����v�ƌ���ꂽ���t���Y����Ȃ��B
���ł����̗�݁B
12�N�O�Ɏ����A�G�b�Z�C�W�i���M�j���o���Ƃ��ɁA���ꂵ���Ȃ��Ƃ����ă^�C�g���������������B
�w�s���i�t���`�j�x
�L���Ղ����B
���́A�����搶�̂ق����s�����B�s�����D�D�D�B
���ɂ́A�搶�̎v�z���A���_��������ɓ`����g���ƐӔC������B
�[���߂��݂Ǝ����݂������ĂƂ��悤�搶�̎��𓉂݂܂��B�i�M�^���X�g�j

5. �Ǔ��@�����Ƃ��悤 �b ���c����
�u�t�H�[�N���S���̎�͑吨���邪�A�g�t�H�[�N�E�V���K�[�h�ƌĂׂ�l�͂ق�̈ꕔ�ɂ��������Ȃ��v
1969�N�āA���߂ăj���[���[�N�̃��B���b�W��f�r�����Ƃ��A���t�H�[�N�E�V�e�B���������āA�労���B���@�`�H!!�@�������A���āA�s�[�g�E�V�[�K�[��A�{�u�E�f�B������A�W���[���E�o�G�Y��APPM�������n���z�[���Ƃ��Ă����Ƃ���ȂB
�X���ɓ������Ƃ���ɁA��������Ƒz���N�����ꂽ�t���[�Y���A�{�e�̃C���g���ł���B�ڂ��ɂƂ��āA�����Ƃ��悤����w���Ƃ́A���̃t���[�Y�ɏW��Ă���B
���E60�N�t�A�a�J�E�����u�́w�j���[�E�~���[�W�b�N�}�K�W���x�̕ҏW���������˂�B�ړI�́A�ڂ�����ɂ���w�W���Y�x���Ƃ́u�����L���v�̌��ł���B�܂��������ꂽ�̂́A�����́A���y�������Ƃ������A���y�n���H�[�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��̂ł���B�ׂ�̕����ɂ́A�͂�Ȃ�Ƃ�����������̌��ɕ��シ��`�F�������肰�Ȃ��u���Ă���B�ڂ��ɂƂ��ẮA���т��������Ƃ������A�n���p�ȗʂ̎����ł͂Ȃ��B������A���ЁA���ʁA���R�[�h�A�����A�����ɐ�������Ă���̂ł���B
���̓������A�������y�ł���Ȃ�A�N�����[���������̂�����ǂ��A�l�̂��Ȃ�����͂ł́A�ÓT�`���㉹�y�Ɋւ�����̂��قƂ�ǂȂ̂ł���B����A�������ь��i���㉹�y�Ɓj�̕������ƒm��B
�ɂ��₩�ɉ����Ă��ꂽ�̂��A�c�엥�ł���B���̃X�[�c���܂�����������Ȃ����āA���̂����J���g���̕����L���̂悤�ȃC���[�W���I�[�o�[���b�v����B���ꂩ��A���k�i�H�j��A�����Ƃ��悤�ҏW�����Љ���B
���쓙�ŁA�l�������Ă����C���[�W�́A�T�^�I�ȃr�[�g�j�N�Ƃ������A�q�vs�^�[�Ƃ����C���[�W�ł������̂�����ǂ��A�������ďo��������Ƃ̂Ȃ��A�Â��ɔR������I�[������������Ƌ���A�N�[���ȃq�b�v�Ƃ������A�A�J�f�~�b�N�ȃq�b�v�Ƃł������̂��낤���H�@�d���Ă̂����A�z�[���X�p���̃O���[�����������W���P�b�g����ۂɎc��B
�u���s�̋�s�������i�L������������H�j���C���ɂȂ�܂��āB�撣���ĉ������v�Ƃ������x�̃n�i�V�������Ă͂��܂����Q�Q�B
�T���t�����V�X�R�`�j���[�|�[�g�`�V�J�S�`�j���[���[�N�A����f�r���A�A���Ă����̂͏��H�ł���B�z�e���͂��ׂ�YMCA�B�j���[�|�[�g�ł͉Ƌ�̑q�ɂ̈�p�ŐQ���܂肵�B�t�F�X�e�B�o���E�t�B�[���h�ւ̍s���A��́A�q�b�`�n�C�N�B�v���X�E�p�X�����炦���A���O�Ń`�P�b�g���A�B�e�́A�܂������̃Q������B��70�N�̃j���[�|�[�g�Ȃ�āA�h���悪�����炸�A�I��F�ɃX�[�c�P�[�X��a���āA�B�e����������肵���Q�Q�B�����b�ɂȂ�܂����B
�T���E���A�}�C���X�A�r���E�G���@���X with �W�F���~�[�E�X�^�C�O�A�T�j�[�E�}���C�A���[�����h�E�J�[�N���ڂ̓�����ɂ����̂�����ǂ��A�������������̂́A�u���[�X�`�j���[���b�N�̏o�����������ƁB
B.B.�L���O�A�W�F�X���E�^���A�X���C�A�T�x�[�W�E���[�Y�A�W�F�[���X�E�u���E���A�W�����E���C�I�[���A�W���j�[�E�E�B���^�[�A�t�����N�E�U�b�p�A�u���b�h�E�X�F�b�g�E�A���h�E�e�B�A�[�Y�A���b�h�E�c�F�b�y�����A���X�������X�e�[�W�Ɏ��X�Ɠo�ꂷ����̂ł���B
�A������A�c�엥��茴�e�˗�����B400���l�ߌ��e�p��30���قǂ̌��e����C�ɂ܂݂�ĕԋp����Ă����̂́A��������~�̂��Ƃł������B
���܁A���Â��v���ɁA�{�c�ɂȂ��������́A������j���[�E���b�N�v�����u��v�Ƃ��ĂƂ炦���ɁA�ЂƂ́u�����v�Ƃ��ĂƂ炦������ɈႢ�Ȃ��B
���������A���N�A�����X�e�[�W�ŁA�}�C���X�E�f�C���B�X�E���j�b�g�i�`�b�N�E�R���A�A�f�C���E�z�����h�A�W���b�N�E�f�B�W���l�b�g�j�́A�w�r�b�`�F�Y�E�u�����[�x�������Ă���B���̃j���[�E�W���Y�v������������Ɓu��v�Ƃ��ĂƂ炦��̂ɁA���N�̌�����K�v�Ƃ����B
�j���[�E���b�N�v���́A�����Ɂu���ہv�Ƃ��ĂƂ炦�Ă���B��Ȃ���J�^�N�i�ł��Ȃ��Q�Q�B
�����A�u�W���Y������~���[�W�V�����͑吨���邪�A�g�W���Y�E�~���[�W�V�����h�ƌĂׂ�l�́A���̂ق�̈ꕔ�ɂ��������Ȃ��v�B
����A�u���y�Ƃ������l�Ԃ́A�吨���邪�A�g�z�����m�h�ƌĂׂ�l�́A���̂ق�̈ꕔ�ɂ��������Ȃ��v�B
�����Ƃ��悤�́A�^�́g�z�����m�h�ł���B
�����B�i�W���Y�o�[�wBitches Brew for hipsters only�x�I�[�i�[�j
���F�u�����L���v�Ƃ́A�G���ƎG���̊ԂŁA�����ő��݂ɍL�����ڂ��邱�Ƃ������B�Q�l�܂łɁA�w�W���Y�x��1970�N1�����́w�j���[�~���[�W�b�N�}�K�W���x�̍L���́A�u���W�F�h���b�O�ƃ��b�N�E���{�����[�V�����v�A�u�Βk�F�ь��E�����M�v�ł���B


6. �����Ƃ��悤����̎��𓉂� �b ��M��
�Ƃ��悤������]���m�����̂�7��22���t���̓����V�������������B�ڂ��͑�z�̐V���͐e�����p���Łu�����v�����A�O�o���ɎԒ��œǂނ̂͌��܂��āu�����V���v�ł���B���������낢��ǂݔ�ׂĂ݂����A�u�����V���v���s�Εs�}�ɓO���Ă��ĂقƂ�ǎ���ɋ߂����u�Љ�̖ؑ��i�ڂ������j�v�ƂȂ蓾�Ă���B�����炳�܂Ȏ狌�h�̐V���͐��_�q�����낵���Ȃ��B�C���^�[�l�b�g�̕��y�ŐV����ǂ܂Ȃ���҂������Ă���悤�����A�ڂ��Ȃǂ͍ŋ߂܂��܂��V����ǂݍ��ގ��Ԃ������Ă���B�l�b�g�Ƃ̍��ʉ���}���āA�V�����ЊO����̓��e�̔Z����e��ϋɓI�Ɍf�ڂ���悤�ɂȂ�������ł���B
����͂��Ă����B�Ƃ��悤������]���ڂɂ����Ƃ��A��u�A���O�𗬂��i�F���~�܂����悤�Ɏv�����B�������A�u�g�����v�ɂ��u�\���ς݂̎����v�̉\�����Z���Ƃ���B�������Ɍf�ڂ���Ă���Ƃ��悤����̋߉e�����ĂЂƂ荇�_���������B���������ŊJ�Â���Ă���u�����Ƃ��悤�R���N�V�����W�v�ɎQ�������Ƃ��悤����͏�ɐg��a���ǂ�����X�����ł���B�ڂ��̋L���͏����Ȃ���G�l���M�b�V���Ől���˂�悤�ȋ����፷���̑s�N�̂Ƃ��悤����̃C���[�W���Œ肳�ꂽ�܂܂��B��i��킢�j79�Ƃ���B�����ł����ΎP���i����j���B�����̘V���ɂ͕q���ł����Ă����l�̘V���ɂ͓݊��ł��邱�Ƃ������B�v���Ԃ�ɏo������������̕ς��悤�ɋ������A�������V���Ă����Ă���悤�ɁA���l���������x�ŘV���Ă���̂��B�����̓��̒��̃C���[�W���Œ肳�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���ɉ߂��Ȃ��B
�Ƃ��悤����ɍŌ�ɐڐG�����̂́A2005�N�B�������āA�u�G�m�X�A�C���X����A�������^���S�E�s�A�j�X�^Nobucco�i���c�L�q�j��CD�w���̕���`�p�q�i�E�f�E���B�A�w�x��JazzTokyo���烊���[�X���邱�ƂɂȂ�A�ޏ��̏f���̗c�Ȃ��݂ł������Ƃ��悤����ɉ�����˗����邱�ƂɂȂ����B�Ƃ��悤����Ƃ̂��Ƃ�́w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�̕ҏW�����o�R���čs��ꂽ���A�����[�X��ɂR�l�ŐH���ł��A�Ƃ����̓X�P�W���[���̓s���ʼnʂ�����Ȃ��܂I������B���̎��Ƃ��悤�����M�������C�i�[�m�[�c�ŁA�Ƃ��悤����́A�ޏ����e���������l���̉��y�Ƃ̒��ŃA�X�g���E�s�A�\���ƃG�O�x���g�E�W�X�����`�ɑ���]����ۗ������B�u�ԓx��ۗ�����v�Ƃ������Ƃ͎�����A�ے肷�邱�Ƃ��Ӗ�����B���c��͂�JazzTokyo��CD�Љ�ihttp://www.jazztokyo.com/newdisc/komado/nobucco.html�j�ŐG��Ă���悤�Ɂg�s�A�\�����W�X�����`�����m���y������āA�����n�ɉ��y�̖쐶���f�t�H������������h������ł���B�R���e���|�����[�E�^���S�ƃR���e���|�����[�E�u���W���A���̗��Y���o�b�T���邠����A�Ƃ��悤����̖ʖږ��@�Ƃ������Ƃ��낾�B
�ڂ�����������A�w�~���[�W�b�N�}�K�W���x�̕ҏW���������Ƃ��悤����̓����[�X����ECM�̃A���o���ɂ��Ƃ��Ƃ�1�_��2�_�̕]�����������iMM���̕]����10�_���_���j�B�����ĕ]���̑����Ɂu�C�����������v�Ƃ����l���Ɂu�C�F�i�����傭�j�������v�Ȃǂ��g��ꂽ�B��O���E�̉��y��������Ƃ��悤����ɂƂ��āA�C���v���ɐV�����W�J�𑣂����Y���̃I�[�v������V�������y�̂���悤�ł���^���|�p�ȂǁA���y�ɃC���e���W�F���X����������ECM�̍앗�͎��������̂ł���B�Z�V���E�e�C���[�E���j�b�g�́w�A�L�T�L���x���g�����ȊO�̉����̂ł��Ȃ��h�ƕ]�����́E���������Ăяo������A�o�_�[���E���C�́w�A�V���o�b�h�x���g�W���Y�Ƃ͂����Ȃ��h�ƒf�肵���]�����f�ڂ����w�X�C���O�E�W���[�i���x���̎��R�I�F�ҏW���Ɍ��܂��ӂ��������肵���ӋC���V�̂ڂ����������A�Ƃ��悤����̍̓_�ɂ͕�����������Ƃ��Ȃ������B�Ƃ��悤����̔�]�̍��W���������s�ςł��邱�Ƃ��q�ϓI�ɒm���Ă�������ł���B�i�l�K�e�B���ȕ]�����f�ڂ��ꂽ���[�J�[�ɂ���ẮA�L���f�ڂ������~�߂����Ƃ��������ƕ����j�B
����ǂ��납�A�Ƃ��悤����ɓ��������ɕҏW����K�ꂽ���Ƃ�����B���e���̃A���o�����������A������˗������Ƃ��悤����̏��������ɂ���āu�����悤�悤�v�ƌ�A�����Ƃ��ł���B��A�ɂ͌������Ƃ��悤���A�ے��̎��Ɨm�y�S���Ɂu����A�C������悤�Ɂv�ƒ��ӂ𑣂��������������B�����̃g���I���R�[�h�̓W���Y�̑��ɁA�u���[�X�A���Q�G�A���e���A�u���[�O���X�A�n���C�A���E�~���[�W�b�N�ȂǁA�����郋�[�c�E�~���[�W�b�N�L�������[�X���A�Ƃ��悤����̕]���������������Ƃ�����̂��낤�B���̌�A�Ƃ��悤����̓A���o���E�����[�X����]����A�W�A�̃~���[�W�V�����̏Љ������������B
���S���m�F���ꂽ7��21���̗��X���A�����V���̗[���͂Ƃ��悤����̈�e���f�ڂ����B���������ŊJ�Â���Ă���u�����Ƃ��悤�R���N�V�����W�v�i���傪����SP��5,000�_�ALP 3���_�ACD�E�J�Z�b�g5,000�_�A�y��350�_�̂Ȃ�����ꕔ��̌n�I�ɓW���j�Ɋւ�����̂ŁA�������A�M�̗���͈�_���݂��Ȃ������B�v���Ԃ�Ɏ�ɂ���MM���̍ŐV���i�\����K-POP�̃A�C�h���E�O���[�vKARA�j�ɂ͐�M�ƂȂ����u�Ƃ��悤�Y�E�g�[�N�v�̍ŏI�т��f�ڂ���Ă���A�������ł́u�N����v�̋����I�ď��̐����ɐG��A�g���y�Ƃ��Ắu�N����v����ɂ���Ȃ�ڂ���������A����ȂɋC�����̈����͓̂�ƂȂ��A�Ƃ͂����蓚����h�ƒf���Č����B�u�Ƃ��悤�Y�E�g�[�N�v�́A�Ƃ��悤����̓ƒf�ƕΌ��̘A�ڃG�b�Z�C�ŁA�ڂ��Ȃǂ�MM������Ɏ��Ɛ^����ɖڂ�ʂ������̂��B�T���ĂƂ��悤����̐h���ɋ��̂����v�����������Ƃ����������ƋL������B
�Ƃ��悤����́g�g�����h�ɂ��āu�F�m�ǁv���]�X���鐺���������Ă������A�Ƃ��悤����̎�����`��������̂��B����͂Ƃ��悤����Ȃ�̐l���̃P�W���̕t�����������Ƃڂ��͊m�M����B�g�V���Ƃ͎c���Ȃ��̂ł���h���Ƃ�F�߂ł͂��邪�B�i�{���ҏW���j
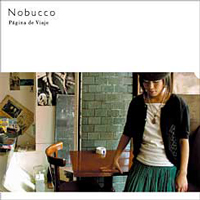
7. ���悤�Ȃ璆���Ƃ��悤�搶 �b �H�R����q
7��21�������Ƃ��悤�搶���A����79�̐��U������B�u�Ȃ��H�ǂ����āI�v�ƌ��������u����ׂ����������A�I������B�v�ƌ����̂������ȋC�����ł���B
�Ƃ��悤�搶�Ƃ̈�Ԃ̎v���o�́A��͂�1991�N�� WOMAD YOKOHAMA���낤�B�p���� WOMAD���c�Ƌ��ɐݗ������A�������WOMAD JAPAN�̃f�B���N�^�[������������A�Ƃ��悤�搶��WOMAD ���{�ψ���̌ږ���˗������B����́A�䂪���ɂ����āA���e������j���[�E���b�N�A�����Ă₪�Ă̓��[���h�E�~���[�W�b�N�܂ŁA�F�m�ƕ��y�ɐs�͂����Ƃ��悤�搶�ւ́A���߂Ă��̉��Ԃ��̈Ӗ����������B
�\�z�ʂ�Ƃ��悤�搶�͉������Ă��ꂽ���A���ꂩ��WOMAD YOKOHAMA�J�Â܂ł̓����͌����ĕ��R�ł͂Ȃ������BWOMAD�͖{�Ƃ̉p���ƊO���ł̃t�F�X�e�B�o�����A���ʂ��������o�[�Ńc�A�[���A�J�Í����ƂɌ䓖�n�A�[�e�B�X�g�����������C���i�b�v�Ő�����}���ė����B�Ƃ��낪�Ƃ��悤�搶�͓��{����WOMAD�ŁA���܂łōō���WOMAD���������邱�Ƃ������ɂȂ��B���[���h�E�c�A�[�Ƃ͕ʂ́A���{�Ǝ��̃��C���i�b�v��������]�����B�Ƃ��悤�搶��WOMAD�̎�|�Ƃ��̌��тɂ͑傢�Ɍh�ӂ����A���ƃA�W�A�A���e���̃��C���i�b�v�ɂ́A���˂Ă���^���悵�Ă�������ł���B
WOMAD���c�̒��S�l���A�g�[�}�X�E�u���[�}���ƁA�Ƃ��悤�搶�A���݂��Ƀ��[���b�p�ƃA�W�A���\���郏�[���h�E�~���[�W�b�N�̑��l�҂Ƃ��ẮA�Ӓn�ƃv���C�h���^������Ԃ��荇���A�����Ƃ��x�X�������B���܂�̌������ɒʖu��������ȏ���Ȃ��I�v�Ƌ����o���قǂ������B�Ƃ��悤�搶�H���u���̍ۂ�����WOMAD�̈����������A�����c�锒�l�D�ʂ̐A���n�x�z�ғI�����^���e�B�����߂����Ă�낤����Ȃ����I�����A�[�e�B�X�g�͂���Ȃ��A�����ɕς���ׂ��I�������ǂ����Ă��o��������Ȃ�A���͓��{�ψ���̌ږ���~���I�v�g�[�}�X�H���u�i�J������WOMAD��������C���H�ނ�����ȏ㋭�����s�g����Ȃ�A���{�ł�WOMAD�J�Â͎��~�߂�I�v���̓x�ɗ��҂��Ȃ��߂Ē�������̂����̖�ڂ������B
�ŏI�I�ɂ�WOMAD���c�����A���̓����̂Ƃ��悤�搶�́A���f�B�A�A�X�|���T�[�A�����ē��{�l�A�[�e�B�X�g�ɑ���e���͂̑傫���͔F�߂�����A�啝�ɏ������ē��{�ψ���̗v�]�ɏ]���Ă��ꂽ�B�����ăp�V�t�B�R���l�̃I�[�v�j���O�E�C�x���g�Ƃ��āA�\�Z�ɂ͔�r�I�b�܂�Ă������Ƃ�����A91�N�̑�1��i�n���h�A�|�[�O�X�A���b�X�[�E���h�D�[���A��{����A�X�U���k�E���F�K�A�s�͂�ݑ��j92�N�̑�2��i���}�E�C���}�A�k�X���b�g�E�t�@�e�E�A���E�n�[���A�p�p�E�E�F���o�A�͓��Ƌe���ہA�s�͂�ݑ��j�́A���ɂ��Ďv���ƌ��\���Ȗʎq�������B�I�n���x�����ŁA�T�ڂɂ͐��͓I�ɂ��ׂĂ̏o���҂̃X�e�[�W������Ă����悤�����A�Ƃ��悤�搶�͂��̍����łɑ̗͂ƋC�͂̐������n�b�L���Ǝ��o���Ă����B
��1��WOMAD YOKOHAMA��3���Ԃ̊��Ԓ��A���͂Ƃ��悤�搶�ƃR���T�[�g�̍��ԂɁA�܂��H�������Ȃ���F�X�ƎG�k�������B�����ĂP�̋^��ɂ��Ď��₵���B�Ƃ��悤�搶�̉��y�ɑ������Ȃ�����A�ٕ����ɑ��鑸�h�̔O�A�s���ᔻ�͂ɑ��āA�ɒ[�ɊC�O��ނ̉����Ȃ����Ƃ��A���˂Ă���C�ɂȂ��Ă����B�u�s���Ȃ�A�ό����s�ɖт̐������悤�ȋ삯���c�A�[�͂��߂B3�T�Ԉȏ�͑؍݂��āA�t�B�[���h�E���[�N����肽���B�����Ȃ�Ǝ��O�̏�������p�̖�������A�Z�����ɂ��܂��ĂȂ��Ȃ������ł��Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă���B����ɁA��������ő̒�������āA�N���̐��b�ɂȂ����葼�l�ɖ��f�͐�ɂ��������Ȃ��B�v�Ƃ̓����������B�����āu�i�����͔��ڂ������Ă����j���b�X�[�E���h�D�[���ƃT���t�E�P�C�^���A�����A�t���J�̑�n�ŋ������邱�Ƃ�����Ȃ�A����͊ςĂ݂����Ȃ��B�~���R���̎��͂������Ă���邩�ȁH�v�Ǝ��ɐu�����B�����u���{���{�ɂȂ��Ă��A���Ǝ����m���Ȃ�Ԉ֎q�ɂ�����t���Ăł��������܂��B���̂����A���n�ŖŒ��ꒃ�Ș_���������ʂ����Ƃ���Ȃ�A�Ԉ֎q���ƕ���o���܂�����ˁI�v�Ɠ�����Ɓu�Ԉ֎q�ŏ�ɑ��l�̉���K�v�ȏ�ԂŁA�����𑱂��čs�����Ƃ́A�ƂĂ��䖝�ł��Ȃ��B�ł��~���R����Ȃ�A������������N�������Ĉ���āA��Ŗ�̈����Ɋ���Ă���̂ŁA�C���˂����Ɉ�x�Ȃ痊��ł��������ȁB�v�Əq�ׂ�\��́A���y�ƊE�ł͈،h�̔O�������Č����Ă���A���i�ɂ܂�Ȃ������Ƃ��悤�Ƃ͕ʂ́A�D�������ꂳ��̂��̂������B
�Ƃ���Ŏ������y�]�_�ƁA�����Ƃ��悤�̑��݂�m�����̂́A�j���[�~���[�W�b�N�}�K�W���̑n���ł������B���S����������m�y�ɐe���݁ABillboard�Ȃǂ̗m���ɂ��s���R���Ȃ��ƒ�����������A���P�̎��ɂ͂��ł�NME�i�p���̉��y�V���j���[�~���[�W�J���E�G�L�X�v���X�j���q��ւŒ���w�ǂ��Ă����̂ŁA�t�@���G���̗v�f�����������̓��{�̉��y���͑S��������Ȃ������B����Ȓ��A�j���[�~���[�W�b�N�}�K�W���̏o���͉���I�������B�|�s�����[���y��^��������]�_�ł���ŏ��̎G���Ƃ��āA���Ƃ͑S��������悷���݂������B���̑n���҂ŕҏW���������Ƃ��悤�搶�̎p���A���߂Ėڂɂ����̂́A�j���[�~���[�W�b�N�}�K�W�����㉇�����A���Ẵ��b�N�E�A�[�e�B�X�g�̃t�B�����E�R���T�[�g�������B
���ۂɂƂ��悤�搶�Ƃ̕t���������n�܂����̂͂���10���N��ɂȂ�B���̗F�l���b�X�[�E���h�D�[�����A���߂ăC���^�[�i�V���i���E�}�[�P�b�g�Ɍ����Ĕ��\�����ANelson Mandela�̓��{�Ճ����[�X�̍��������B�Ƃ��悤�搶�Ƃ��e�����A���b�X�[�̃t�@����Nelson Mandela�̃����[�X�ɂ�����ȋ��͂����Ă��ꂽ�A���e�����y�]�_�Ɓ^DJ�̒|���~�搶�̏Љ�����B�����A�t���J���y�̃}�j�A�ƁA�G�X�j�b�N���y�D���̃��b�N�E�t�@���̊ԂŁA���b�X�[���b��ɂȂ肾���A�Ƃ��悤�搶�̑E�߂Ń~���[�W�b�N�}�K�W���Ƀ��b�X�[�ɂ��ď��߂Ċ�e�����B���炩��Ԃ��Ȃ��Ƃ��悤�搶���ďC����ANHK�|BS�̃V���[�Y���ԁu�ԓ����y�v�̈ꕔ����`�����ƂɂȂ�A�v���f���[�T�[�̌̑�]��v����Ƃ̕t���������n�܂����B
���҂Ƃ̏o����A���WOMAD YOKOHAMA�ւƂȂ�����A���x���ł����킹�����˂ė[�H�����ɂ������Ƃ�����B�[�H�̐ȂƁA����1�x�͒����Ƃ��悤��������K�ꂽ���A���͂Ƃ��悤�搶�ɒ����B�u���镪��œ��{�ɉ����錠�ЂƋ��ꂽ�l�ł��A���S�̂Ȃ��҂��炷��w���ꂿ���A�����ɂ��Ȃ�Ȃ��K���N�^���R�̂悤�Ɏc���Ď��x�Ɩ��f������B���C�ȓ��Ɏd���̌�p�҂ƁA�^��Ȏ����̐����ɂ��Ă̏�����i�߂Ă��������B�v�ƁB��p�҂ɂ��ẮA���Ƃ��ĉ��l���̖��������������A����̒N���Ɉς˂�l�q�ł͂Ȃ������B�����ɂ��ẮAWOMAD����݂ŁA���l�ɒ����Ƃ��悤�����ق��J�݂���b��i�߂Ă���ƌ������Ƃ������B�����ĉ��l���̉��y�W�҂Ǝ��҂������A�����Ɍ������������Ă������A���̌�n�������c�͕̂������A�����̗\�Z��D�悷�鎞��ɂȂ�A���̊Ԃɂ������ق̘b�����������ɂȂ��Ă��܂����B
�Ƃ��悤�搶�����S�͂������čs�����̂́A89�N�~���[�W�b�N�}�K�W���̕ҏW������ނ��Ɠ����ɐV�����肪�����A���[���h�E�~���[�W�b�N����̂ɂ����G���A�G���m�C�Y���x������92�N�����Ǝv���B���N�̑�2��WOMAD YOKOHAMA�ł́A�Ƃ��悤�搶�̓k�X���b�g�E�t�@�e�E�A���E�n�[�����A���������̃A�[�e�B�X�g�������āA�R���T�[�g���Ɏp�������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����đ��̃R���T�[�g�ł��Ƃ��悤�搶�̎p���������邱�Ƃ͂߂����茸�������B���̎��_�ŁA���̒��ł́u�A�N�e�B���ȉ��y�]�_�ƒ����Ƃ��悤�͊��������B�v�Ɗ������B�Ƃ��悤�搶�Ɖ���Ƃ��A�b�����Ƃ��Ȃ��Ȃ����B���̖������������Ȃ��������A�����Ƃ��悤�����ق����͉��Ƃ��`�ɂ��Ďc���ė~�����Ɗ�����B
���͂Ƃ��悤�搶�̕]�_�ɉe�����āA�N�����b�N�E�~���[�W�V�����̃t�@���ɂȂ�����A���[���h�E�~���[�W�b�N�ɂ��Ċw�Ƃ����ӎ��͑S���Ȃ��B�Ƃ��悤�搶���牽���w�Ƃ���A����́u�v���ӎ��������Ɓv�ł���B���͈ꎞ�����b�N�E�~���[�W�V�����̎ʐ^���B���Ă������Ƃ����邪�i���������Ď~�߂���ł͂Ȃ��j�Ƃ��悤�搶�̏����ɏ]���A�ʐ^���B���Ă��鎞�́i�B�e�]�����]�Ă��t���܂ň�т��āj��ɖ{�Ƃ̂���Ŗv�����ė����B���͕����̎��Ƃ��c�ނ悤�ɂȂ������A�Ƃ�����Ƃ�]�Z�łȂ��A�{�C�Ŏ��g��ł������ł���B
���炭����w�ǂ��Ă����~���[�W�b�N�}�K�W�����A���̊Ԃɂ��ǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă������A�Ƃ��悤�Y�g�[�N�����͗����ǂ݁A�������͒m�l�̎������Ŗ����ǂݑ����Ă����B����Ȓ��ŕ�������p��w�ɉ��y�W�̂��ׂĂ̎��������邱�ƁA�����̎���̂��Ƃ��l���āA�ɗ͉Ƒ�����͂̊W�҂̎�����킹�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�����ɐg�Ӑ��������Ă��邱�Ƃ�m�����B�����Ă��ׂĂ��I���āA�܂����������̔��p�قŁu �����Ƃ��悤�R���N�V�����W�v���J�Â���ĊԂ��Ȃ��A�Ƃ��悤�搶�͎������g�Ŏ����̐l�������������B���悤�Ȃ�A�{���ɂ��悤�Ȃ璆���Ƃ��悤�搶�E�E�E�E�B�i8��7���@�O���I�C���^�[�i�V���i���j

8. ���悤�Ȃ�A�Ƃ��悤���� �b �I ��F
�����G�b�Z�C(http://www.jazztokyo.com/column/editrial01/v43_index.html)
 12.27 '15
12.27 '15
�N�����W
���Ƃ��́@����CD�@�Q�O�P�T�i�����ҁj
���J����b���c���b
�דc���k�b��M��b
�_��G�Y�b�����[��b
�]���R���b�y������b
�֓����b�ʈ�V��
���Ƃ��́@����CD�@�Q�O�P�T�i�C�O�ҁj
���J����b���c���b
�דc���k�b��M��b
�_��G�Y�b�����[��b
�]���R���b�y������b
�֓����b��Օ��F
���̃��C���^���̃R���T�[�g�@�Q�O�P�T�i�����ҁj
���J����b���c���b
�דc���k�b��M��b
�_��G�Y�b�֓����b
�]���R���b�I��F
���̃��C���^���̃R���T�[�g�@�Q�O�P�T�i�C�O�ҁj
���J����b���c���b
�דc���k�b��M��b
�_��G�Y�b�֓����b
�]���R���b��Օ��F�b
�I��F
�i*�A���t�@�x�b�g���j
![]() �F
�F
#1267�wMike Nock ~Roger Manins / Two -Out�x�wMike Nock~Laurence Pike / Beginning and end of knowing�x(FWM) �I��F
#1268�w�����vFIT! / �݂邭��x(MIX DYNAMITE) ꎓ� ��
#1269�wRomain Collin / Press Enter�x(ACT Music) ��Օ��F
#1270�wMike Moreno / Lotus�x(World Culture Music) ��Օ��F
#1271�wShoko Nagai / Taken Shadows�x(Animul) ���c��
#1272�w�͖�q���^�����N�X�x(Sony Music Direct) ���i�L��Y
#1273�wThe Creative Music Studio (CMS) -Archive Selections Vol.2�x(Planet Arts) �u���[�X�E���[�E�M�������^�[
#1274�wMette Henriette�x(ECM) �}���N�X�E�V���e�O�}�C���[
#1275�w���̂P�� 2015�i�����ҁj�x
#1276�w���̂P�� 2015�i�C�O�ҁj�x
![]() �F
�F
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
�������ɂ��郊�A���E�W���Y�@�|�@�j���[���[�N����̃��|�[�g
by �V�X�R�E�u���b�h���[ Cisco Bradley�C���c�� Takeshi Goda, ꎓ��� Akira Saito, �g�c��T�q Nonoko Yoshida & �@���ߖ� Rema Hasumi
#09 Contents
�E���y��i��������ٖM�l ���c��
�E�A�ڑ�X��F�j���[���[�N�E�V�[���ŐV���C���E���|�[�g�������[�X��� �i�V�X�R�E�u���b�h���[�j
�E�悵���̂̂���NY���� ��V��i�ŏI��j �g�c��T�q
�E���C���E���|�[�g�F�g�c��T�q@Stone �@���ߖ�
�E�C���^�r���[�F�W���V���E�G���@���X ꎓ���
�A�ڃt�H�g�E�G�b�Z�C
Reflection of Music 43�u�}�b�c�E�O�X�^�t�\���v�����]
�J���T�X�E�V�e�B�̐l�Ɖ��y
#46. �`���b�N�E�փf�B�b�N�X���Ƃ́g�I�[�j�\���W�[�h: �`���[���[�E�p�[�J�[�E�q�X�g���J���E�c�A�[ �|���m�q
�y������̒����ǂ���`�F�b�N
#255�wWolfgang Muthspiel / Driftwood�x(ECM)
#256�wBoys featuring SHUN�x(Studio TLive)
#257�wMette Henriette�x(ECM)
#258�w�c���ϖ��^�I���V�I���x(�X�^�W�I�E�p���C�\)
#259�w���엲��&T-SLIDING T-SLIDING �U�`Just Bacharach�x(What's New)
#260�w�J�E���g�E�x�C�V�[�E�I�[�P�X�g���E�C���E�A���X�e���_���P�X�T�U�x(55 Records)
#261�wNautilus / Nautiloid Matter�x(Palette Sound)
#262�wcode�hM�h�^���F���̋����x(Wisteria)
![]() �F
�F
#144�uJosh Evans�W���V���E�G���@���X �vꎓ���
![]() �F
�F
#82�w���{�̃W���Y�͉��l����n�܂����x��M��
![]() �F
�F
#860�u�I�J�^�I�E���c���Ɓ@���J���C�����R�[�f�B���O�v������
#861�u�R�����E���@�����E�g���I�v����N�k
#862�u��6��@��y�ƍ��ە����𗬁v��M��
#863�u�g�c��T�q��The Stone, NY�v�@���ߖ�
#864�u�c��x�q�w�O���ȉƂ̈⌾�x�ŏI��v���J����
#865�u�G���\�E���B���T���[�[�@�s�A�m�E���T�C�^���v���J����
#866�u���E���{�̃W���Y�͕X��ۂ���n�܂����v��M��
#867�uJazz Treffen 2015�����A�L�@���f�B�E�}�n�[���@�j���X�E���H�O�����v��M��
#868�u�J�}�V�E���V���g���v�_��G�Y
#869�u���̃��C���^�R���T�[�g 2015�i�����ҁj�v
#870�u���̃��C���^�R���T�[�g 2015�i�C�O�ҁj�v
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.
