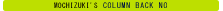最近、ジャズ・グレイトと言われるピアニストの作品では評価の定まった名盤とされるものよりもごく初期の作品、特にファースト・アルバムに耳を傾けることが多い。
キース・ジャレットが『Facing You』(ECM)でECMデビューしたのが26歳、チック・コリアが『Now He Sings、Now He Sobs』(Solid State)で世を驚かしたのが27歳の時であり、バド・パウエルの『The Amazing Bud Powell』(Blue Note)が25歳、ビル・エヴァンスの『New Jazz Conceptions』(Riverside)が27歳、フィニアス・ニューボーンJrの『Here is Phineas』(Atlantic)も27歳、アンドレ・プレヴィンの『My Fair Lady』(Contemporary)も27歳の時の録音である。
これらの作品からは熟成した香しさよりもひたむきに音と向き合う姿勢の方がつよく伝わってきてジャズが本来持っていた一瞬のゆるみもない緊張感と勢いをいまだに力強く発しているのに驚かされる。
石田幹雄が『TURKISH MAMBO』(Five Stars Records)を録音したのは2007年、こうした若き日のジャズ・グレイト達と同じ年代の26歳の時であった。
当時、札幌で活動していた石田幹雄が札幌時代に培ったジャズの全てを注いだ作品で、トリスターノの黒い横顔のジャケット『LENNIE TRISTANO』(Atlantic)で多重録音した変拍子の難曲<TURKISH MAMBO>を重ね録りなしでいともやすやすとその複雑な曲想を再現したり、マイルスやミンガス、ガレスピー、パウエルといった巨人たちの名曲を軽々と弾きこなし先達へのリスペクトをしながらも、もてる才気のすべてをピアノに注いでいる。石田は、無意識のうちにこの年代の持つ一途さが何物にもかえがたい力をもっているということを実証してくれている。
そしてジャズ、とりわけ即興という甘い果実を知った喜びが石田の人生を大きく変えることになる。
石田幹雄はこのレコーディングを機に東京に居を構え、東京と札幌を往き来しながら音楽の活動の場を広げはじめる。
石田幹雄は1981年の生まれ、滋賀県草津で育ち、今年の11月で34歳という最も光り輝く目映い時期を迎えようとしている。
家にピアノがあって姉が弾いていたことから3歳からピアノを弾き始め、ヤマハの音楽院に通っていたが小学5年位から中学5年までは田所政人についてピアノを学ぶ。先生の田所政人は京都大学出身のピアニストで、草津で田所ピアノ教室を開きピアノや発声等を教えている方である。
<けっこう変わった先生でしたけど、同時に凄くいい先生でした。ヤマハで教則本を使った習い方をしていたんですけど、そういう教え方は良くないんだよね、と小学生の僕に言う先生だったんです。で、機能的に弾くやり方とかを解りやすく説明してくれるんです。多分、コルトーという人の教則本やいろんなところから自分で組み立てた練習方法を教えてくれたように思います。とりあえずブラックユーモアを交えて面白く教えてくれるので自分には合っていたみたいです。ほとんど褒めないで今のはまぁまぁだったかな、と言ってくれるのが印象的でした>
石田は最も多感な10代の前半にピアノの機能的なテクニック全般を身につけている。一般にこの年代に身につけたものはその後の生き方に大きく作用すると言われているが石田の場合はこの時期にピアノと自分とを一体化することに成功してしまったようで、いつ、どこで、どんなピアノを弾いても石田の音が鳴り響いてくるのである。
共演しているミュージシャンからは石田のピアノは上手いという声をよく聞くが石田は決してテクニックをひけらかすとか粗雑になるということはなく、共演する相手の音を真正面からしっかりと聴き真摯にその音に反応するから評価が高いのである。
高校は大津の名門校、膳所高校に進む。
高校では山岳部に所属するかたわら軽音楽部でキーボードを弾いていたそうだが特に音楽にのめり込んでゆくようなことはなかったという。
大学の進路を決める際、石田はまずは理学部を目指し、その上で学校は、北か南かのどこか遠いところに行って学びたいと考え思案の結果、北を選択する。
2000年、北海道大学理学部に進み、学生生活を始める。専攻は地球惑星物質学科(現 地球惑星科学科)を専攻する。
<卒業論文がない分だけピアノがいっぱい弾けるなって思って>
理学部に入って専攻を決める際に卒論のない学科だから選んだのだと謙遜するが案外石田の音楽との相関もあるのかもしれない。
大学ではジャズ研究会に入部しここで本格的にジャズと向き合う。
<まず、ピアノが弾きたいなっていうのがあったんで…クラシックのサークルもあったんですけど何となくジャズを選んでジャズ研に入ったんです>
以来なんとなく選んだ筈のジャズが石田のピアノの中で大きなウエイトを占めるようになってゆく。
<ジャズというよりはアドリブをとるという行為が自分にとって楽しくてしようがなかったという感じでした>
<ジャズというものを知れば知るほど思うことの一つに、国の成り立ちから、いろんな人や文化が混じりゆく過程、それを表出する力、一番効果的な方法、かつダイナミックなパワーがアメリカという国にあったのではと思います>
クラシックではパブロ・カザルスが弾いているバッハのチェロ組曲が好きで時折り自分でも弾いているようだ。
<作曲家+演奏家で素晴らしい音楽になると思うのですが、これまで聴いた中でも良かったのはパブロ・カザルスが弾いているバッハのチェロ組曲が素晴らしいなと思います。作曲された当時のリズムもあると思うのですが、カザルスの場合はその作曲家のリズム+自分の個人的なリズムが見事に融合しているような気がします>
最初に買って聴いたピアニストはチャールズ・ミンガス『CROWN』(Atlantic)のウエイド・レグ(p)であったというからかなり渋い入り方である。前述の『TURKISH MAMBO』の選曲をみても石田は1枚のアルバムをじっくりと聴き込んでそのアーティストの核となる部分を吸収し自分の糧としてゆくタイプのように思われる。
セシル・テイラーからセロニアス・モンクのはざまを往き来しながら自在に展開する石田のピアノからは勿論、セシルの、モンクのフレーズはそのまま出てこない。むしろ、鍵盤上を駆け巡る左右の手のバランスがファッツ・ウォーラーやアート・テイタムのストライドを連想する。
<いやあ、テイタムみたいに明確にはなかなか…テイタムは聴きましたけど、まだまだ相当聴かないとだめだって気がしますね>
<セシルはほとんど聴いていないです。モンクは相当レコードも聴いていますね。大学時代から直接コピーしたり、プロになってまた何か聴こうかなって思ったときもモンクは多かったように思いますし、面白いなぁって思って…モンク好きですよ>
<フィニアス・ニューボーンJr.も昔そうとう真面目に聴きましたよ>
そして特に好きなミュージシャンを聴くと、しばらく沈黙ののちビル・エヴァンスの名前をあげてくれた。
<結局、ビル・エヴァンスをずっと聴いている気がしますね>
北大のジャズ研では初代トリオのメンバー瀬尾高志(b)とも出会い演奏活動を始める。
2005年大学を卒業するが、そのまま札幌の『ジェリコ』や『くう』などのライヴ・ハウス等で演奏活動を続けプロの道への歩みを始める。他の職業に就くことは大学に入る前から一切考えていなかったという。
2006年、横浜ジャズプロムナードのコンペティションでグランプリと市民賞を受賞し東京進出の足掛かりとする。この時のメンバーが瀬尾高志(b)、竹村一哲(ds)とのトリオであった。
2007年このメンバーでファースト・アルバム『張碓(はりうす)』をリリースする。張碓は札幌と小樽の間にある駅の名前で、電車に乗って小山彰太(ds)を聴きにゆくときに通った時に目の奥に刻んだ駅名なのだそうである。
横浜ジャズプロムナードの出演の前後からしばしば横浜には足を運び、前述のリーダー・アルバム『TURKISH MAMBO』のレコーディングのチャンスを得、その翌年の2008年、東京に移り住む。
<やっぱり仲間に囲まれていた学生時代よりも上京して一人で考え直す時間が出来たのと、今までやってきたことの整理も出来たというか自分を見つめられるようになりましたね、違った見え方も出来るようになったし、自分に対してね>
東京に居を構えてからは東京と北海道を往き来して演奏活動を続けている。
2011年に早川徹(b)、福島紀明(ds)とのトリオで『瞬芸』(Tiger Sounds Records)をリリースする。
現在は安藤昇(b)と藤井信夫(ds)との「石田幹雄3」の活動を軸にさまざまなセッションに名を連ねているがその中でもとりわけデュオが面白い。
石田はデュオの相手の音を実によく聴いて、そのすべてを自分の中に吸収した上で自分の音を重ね、反応してゆく。本稿執筆のために1時間ほど話をさせて頂いたがその対話の中でも石田は相手の話を、耳を澄ましてよく聞きその核心について丁寧にしかも整然と答えてくれた。こうした普段の生活のなかでの真摯で誠実な人柄はそのまま音楽の中にも投影されているように思われる。
最近のデュオの相手は林栄一(as)、蜂谷真紀(vo)、寺田町(vo,g)、小山彰太(ds)、吉田隆一(bs)、山本育美(vo)等々みな一家言をもつアーティストばかりでありそのどのセッションでも石田の対話ははずみ、ときにフリー・インプロヴィゼーションへと突き進む。こう云うシーンを見た人は石田をフリー・ミュージシャンと認識するが、その目まぐるしく展開する音のその奥には音楽への深い慈しみと、ピアノと石田とが一つに溶け合って生じた結晶が燦然と輝いている。
このほか、石田幹雄は「松風紘一4+1」と吉野弘志「MOPTIセッション」、「太田朱美(fl)4」にもレギュラーで参加している。
リーダーであり、共演者であり、また良き理解者でもある松風紘一(reeds)はその風貌を評してすでに風格があるというか、ベテランみたいな顔をしているからね、と語る。
<演奏もそうですよ。でもとにかく演奏はちゃんとしているしね。音楽に対しても真摯だし、まだ発展途上と云うか、同時に底知れないところがあるよねえ、とにかく自分の音楽をつくるのに音楽と真正面に向かっているね>
もうひとりのリーダーである吉野弘志(b)は石田の音楽への取り組み方、姿勢を高く評価する。
<おそらくフリー系でガンガン弾くみたいな印象を持っている方がかなり多いかと思うんですけど、そういう部分もあるんですけど、実はデリケートな小っちゃな音を大切にしていくような、そういう技術もあるんですよ。というのも彼から聞いた話によると子供のころに、いわゆるお稽古ごととしてピアノを習っていたそうです>
<で、その先生がとても厳しくて、しかも優れた先生だったみたいでピアノという楽器の機能的な技術をそうとう学んだそうですね。しかも機能面だけでなくバッハのインベンションとか、そういうような音大の入試で弾かされるような曲でもいかに音楽的に弾くかっていうようなことまで勉強させられたみたいです>
<だから根本的にピアノの基礎が凄くしっかりしているんですよ。それは技術っていうことだけでなく音楽に対しての取り組み方っていうかその姿勢がしっかり出来ているって云うことですね>
<それと、彼はまぁ最近のものから古いものまでよく聴いていますし、またジャズにとどまらず現代音楽、それからブラジル音楽まで広範囲に自分で聴いていますね>
ジェラルド・クレイトンや上原ひろみ等いつの間にかハンコック、キース、メルドーと云うジャズ・ピアノの流れとは無縁の若いピアニストたちが増えてきたがそうした新しい流れの中のひとりである石田幹雄にとってジャズって何かをあえて伺った。
<そう、初めてアイデンティティーが確立できたっていうのはジャズを始めたおかげだと思います>
<音楽とは”今”、自分の周りに起こしたことや、起きていることであり生活の糧であり、(生活であり)演奏したり人の音を聴いたり楽器に触れたり、結局音楽を定義する感覚や考えが自分にはないというか、でも、そのような事に日々感じながらやっています>
ピアノをもっともっと弾きたいという気持ちからジャズの世界に入った石田幹雄は今33歳、年代的にも最も創造性が発揮できる年令に差し掛かっていてさまざまなセッションでその才を発散させている。
<家でどれだけ弾いても練習は練習にすぎないんです、現場ですね。結局、本番で身についてゆくというか、そういう気がしますね>
ミントンハウス以来、現場主義で変遷を遂げてきたジャズの王道を、身をもって実践している石田幹雄のステージはいつも、情熱と云うもの凄いエネルギーで発熱している。


 1.31 '16
1.31 '16![]() :
:![]() :
:![]() :
:![]() :
: