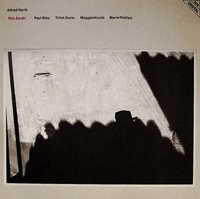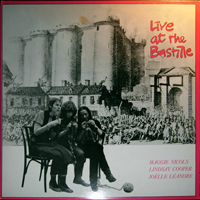|
|
|---|---|
 |
|
|
6月20日木曜日午後2時、新皇帝トーマス・モーガンと月光茶房でお会いしたのでございます。Jazz Tokyo稲岡編集長が、プライベートで来日しているトーマスとコンタクトしていて、「インタビュー、興味ありませんよね?」とこのおれにメールしてくるのんか、興味ないわけないですがな!インタビューはようできへんけど、会わしてえなー。
会うなり、iPhoneで「これがおれが考える現代ジャズ・ミュージシャン・ランキングだ」「1位がトーマス・モーガンだ」「21世紀のスコット・ラファロだ、ゲイリー・ピーコックを超えてるぜ」「TPPトリオは特別だ、レコーデングはしないのか、アイヒャーには無理だと思うぜ」「能は観たことないのか、橋爪亮督グループの十五夜という曲のライブテイクを聴いてもらいたくて持ってきたんだ」「このCDインスピレーション&パワーはこの稲岡さんが当時の日本のフリージャズをドキュメントした2枚組、あげるー」とはしゃぐおれ。
「ECMではどの盤が好きなのですか?」と新皇帝にきかれるおれ。2秒。「エドワード・ヴェサラのナン・マドルという作品かな」、すっとECM資料室ビブリオテカ・ムタツミンダからアナログ盤を手にする原田正夫マスター。

<track 251> Melody Fair / Bee Gees 1971
You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=6r3CcgcXkig
速度について。
ビージーズの「メロディ・フェア」は異様なヒットソングである。
イントロからして演奏のタイミングがズレてるような、そのズレに速度を見る。
ヴォーカルが入ると合っているんだか合っていないんだか、感覚がかく乱されて宙に浮いた感覚に置かれる。
イントロは右側アコギのアルペジオ、左手からベースの弓弾き、そして奏者の呼吸らしき擦過音、オケがかぶさって、の、おのおののテンポは合っているのに呼吸が孤立しているのだ。
これはもうレイヤー構造をなしていると見てよい。
ハンドクラッピングにはっとさせられる。
のは、耳が、レイヤー構造によって形成された空間を聴くからなのだ。
こないだ『Selected Signs III - VII』CDレビュー(http://www.jazztokyo.com/five/five1001.html)の文末にYou Tubeで並べた「ニセコロッシ・セレクテッドサイン」
についての福島恵一さんからの望外の喜びをくれたレビュー。そして続編。
耳の枠はずし:「ムタツミンダにかかる月 − 『ECM Selected Signs III - VIII』を超えて」
http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-234.html
耳の枠はずし:「ムタツミンダにかかる月 − 『ECM Selected Signs III - VIII』を超えて(承前)」
http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-235.html
これくらいのオマケ・リストを付けないとおれがレビューする意味はないだろう、くらいの、若い読者にECMで人生の階段を踏み外させるのはおじさんの責務だと言わんばかりの所業を、ともにECMを聴いてきた恵一兄さんはあの暖かい眼差しで取り上げてくださった。
福島恵一 ECM20×2
http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-38.html
ECM、フリードリヒ、北方を眼差す視線
http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20100711
福島さんの「The Great Pretender」論
http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-60.html
ちょいとタガララジオ35にジャケとともに並べ、おしゃべりでも。
<track 252> Transformate, Transcend Tones & Images / Alfred Harth from 『This Earth!』 (ECM 1264)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=AxCSQwvm6gw
Maggie Nicolsの乾いた粘膜が震えこすれて血が滲み痛々しく傷ついていくヴォーカリゼーションは、Meredith Monkたちの引き締まった声の身体によるモダンな舞踏や、北欧トラッドの歌姫たちによる凍てつく冬の朝のようにぴんと張り詰め澄み切った朗唱とは、明らかに別世界に生息している。多田はいきなり冒頭から、決して再発されず封印されたままのAlfred Harthによる呪われた名盤を取り出してくる。(福島恵一)
Alfred Harth tenor, alto and soprano saxophones, bass clarinet
Paul Bley piano
Trilok Gurtu percussion
Maggie Nicols voice
Barre Phillips bass
輸入盤屋の欧州即興コーナーからLindsay Cooper, Joëlle Léandre, Maggie Nicolsの『Live At The Bastille』を聴いていた、女の子3にんのインプロ・ライブ、すごく楽しい、当時はフェミニンの文脈があったのかな、マギー・ニコルスの声質も超高音もインプロヴァイズも絶品でした、
ポール・ブレイはECMで名品『Open, To Love』を出したあと、それを否定するかの『Alone Again solo piano』を自分で立ち上げたレーベルで出していた(ぼくはそれを圧倒的に支持している)から、このECM作品への復帰にはただならぬ気配を感じた、
そしてアルフレート・ハルトは、当時ハイナー・ゲッベルスと激しいデュオ演奏を斬り付けていた存在だったし、ECMの2番『Just Music』集団即興盤(廃盤)にその名はあったが、アイヒャーとハルトは同じドイツ・シーンでミュージシャン同士として出会っていたはずだ。
なぜ、いま、ここで?この5にんが揃ったのだろう。
コンポジションされた劇中歌を抜群な演奏力を持つマイスターたちと互角にインプロヴァイズさせながら透徹した美意識で結晶化させた作品、廃盤のままに置かれる理由はまったくない。
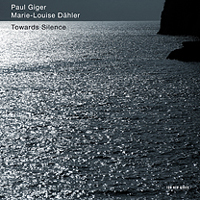
<track 253> Paul Giger "Bombay II" foto de Fernando Figueroa Sanchez y Clara Ivanna Figueroa from 『Towards Silence』 (ECM New Series 2014)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=xKWj51HwCug
ポール・ギーガーについては堀内宏公さんのこの記事を。
「聖なる空間に響きわたる宇宙的郷愁 PAUL GIGER / ALPSTEIN (ECM 1426)」
幼少の頃、カウベルの音、というのは、やはり核心なのだろう。
わたしたちは良くできた音楽を聴くのではない。生命の謎、幼少期に受信した音。コトバや法整備や会話ルールなどで組み上がっている現実界といったものはひとつの過程的な形態に過ぎないとどこかで思い出させるような作用を、
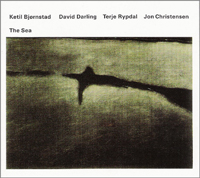
<track 254> Ketil Bjornstad The Sea Part II from 『The Sea』 (ECM 1545)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=D627sFeuBh0
ビョルンスタについては、思い出がたくさん過ぎてうまく書けない。このピアニストの最新作に至るまでのクオリティの高さは、予想していなかったくらいだ、新作を聴くごとに巨人に見えてゆく。
このトラックは、1曲目は船出だとすれば、この2曲目は海原に出ている。イントロのゆらぐ表現から明らかだろう。ヨン・クリステンセンのシンバルワークがやはり素晴らしい土台を築いているが、これでもかと高揚するテリエ・リピダルのギター、終わっていいようなところまで行ってもまだ盛り上がる、おやじ、やり過ぎだろ、ストラトキャスターが肩からズリ下がってへろへろになっているのまでがわかる、恥ずかしさなぞ通り越してしまう堂々とした北欧ロマンに涙だ。
・・・もっと品のいい書き方がなかったものか。
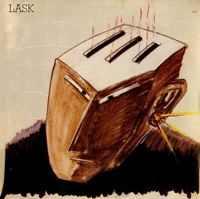
<track 255> Ulrich P. Lask - Unknown Realms (Shirli Sees) from 『Lask』 (ECM 1217)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=-tVTSuoRgr0
この盤はECM番号がパット・メセニー・グループ『オフランプ』(ECM 1216)の次なのですね、
A面1曲目の「Drain Brain」のほうがもちろん破壊度大なのだけどね、
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=muYo3DOpdD0
検索してたらスタジオ・ヴォイス誌でのセレクトに入れていたのが引っかかった
「静謐な世界にのみこまれていく」
http://www.studiovoice.jp/refactored/artspaces/ecm/artspace.php#
原田正夫さんがウォルガング・ダウナーの『Output』(ECM 1006)を選出されている。
Wolfgang Dauner - "Nothing to Declare" (1970)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=eNBo3G--mgY
この盤を今村健一さんがグルーブ・クラシックスでCD化しようとしたのだけど、アイヒャーに断られたんだっけ。
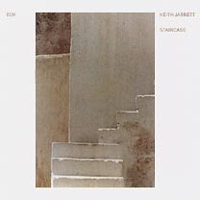
<track 256> Staircase Part 3 / Keith Jarrett from 『Staircase / Hourglass / Sundial / Sand』 (ECM 1090/91)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=ePQ-JJn8r08
この「ステアケース・パート3」は、70年代に稲岡さんが編んだECMスペシャルで聴いたのが最初。はじめてのジャレット体験。
この2枚組の組曲、フランスで映画音楽録って、空いたスタジオでジャレットとアイヒャーが目配せで録ってしまった奇跡的なもの。
ほんとは「アワグラス・パート2」を並べたかった。13分強のトラックなのだが、7分50秒だったかな、ホントウに「時間が止まってしまう感覚」になる。このことだけは、しっかりと後世に伝えるのだ。
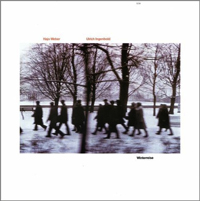
<track 257> Karussell / Hajo Weber & Ulrich Ingenbold from 『Winterreise』 (ECM 1235)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=mT8lb8sy-LQ

<track 258> When Face Gets Pale / Miroslav Vitous Group from 『Miroslav Vitous Group』 (ECM 1185)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=_HoyrxOptEE
Miroslav Vitous - double bass
John Surman - soprano saxophone
Kenny Kirkland - piano
Jon Christensen - drums

<track 259> 7 Anéis / Egberto Gismonti Group from 『Infancia』
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=0k5tTdNzRvU
Egberto Gismonti Trio - 7 Aneis / Infancia / Forro
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=n8B3-ZCsqcE
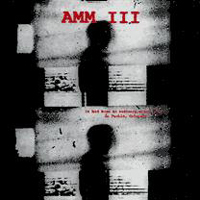
<track 260> Radio Activity / AMM III from 『It Had Been An Ordinary Enough Day in Pueblo, Colorado』
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=2Fh9FYUDCp0
Keith Rowe guitar, prepared guitar, transistor radio
Eddie Prevost drums
AMMのラジオ・アクテヴィティが配置されるとき、ほかのトラックまでがレイヤー構造によって受信する枠組みが与えられ、空間性を聴く構え、たとえばジャレットのピアノ音だけではなく、この録音固有のECMリバーブの存在を意識するというような、
そうなるとAMMのトラックはかつてスティーブ・レイクがJapoで制作したという特異性はこのリストにとっての傷ではなくなる
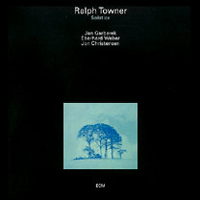
<track 261> Oceanus / Ralph Towner from 『Solstice』 (ECM 1060)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=5DE7ScoLmp8
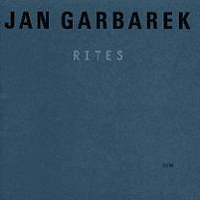
<track 262> Jansug Kakhidze The Moon over Mtatsminda from 『Rites / Jan Garbarek』 (ECM 1685/86)
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=eP-BHfmotwY
「この二枚組は、仰々しいイントロと呼応するフィナーレで壮大なる絵巻物を志向している力作だ。そしてすべてのトラックが、二枚目の半ばに収録されている、唯一ガルバレク自身が参加していない(!)トラックである「ムタツミンダ山の月」にドラマが集約されて配置されている。このトラックはギヤ・カンチェーリの作品を演奏したトビリシ交響楽団の指揮者であるカヒーゼ氏(Jansug Kakhidze)、指揮者でもあり作曲家、シンガーでもあるグルジア出身の62歳のおっさんが古びた映画音楽のようなオーケストラをバックに震えながら歌うものであるが、氏が心臓疾患から奇跡的に快復してから故郷の風景、ムタツミンダ山にかかる月を歌ったものである。このデモ・テープを、総帥マンフレート・アイヒャーがスタジオで何気なくガルバレクに聴かせたところ、ガルバレクは即座に感銘しアルバムへの収録を申し出、この曲に焦点を合わせていくつかの曲を作り始めたのだという。」
(「ガルバレクは二度死んでいた」多田雅範
http://homepage3.nifty.com/musicircus/ecm/rarum/r_02.htm )

竹田賢一さんが初の単著『地表に蠢く音楽ども』を上梓された。
竹田賢一『地表に蠢く音楽ども』刊行記念トーク&ライヴ
「アンダーグラウンド音楽シーンに絶大な影響を与えてきた稀有なイデオローグ/オルガナイザー、竹田賢一待望の初評論集『地表に蠢く音楽ども』(月曜社)を記念したトーク&ライヴ!!!!!!!!」
【出演】竹田賢一、平井玄、中原昌也、チヨズ
8月4日(日) 渋谷Last Waltz 開場 12:30 開演 13:00

<track 263> L.Shankar Caroline & Ustad Allah Rakha - Milano, Teatro Ciak, 30/08/1993
竹田さんがスタジオ・ヴォイス誌でECMの10枚を挙げていた記事があったんだ。トップに大きく『The Epidemics』(ECM1308)1985のジャケが掲載されてて、度肝を抜かれた。こういう記事が青少年には刺さった、
当時、LPで聴き始めて、ターンテーブルに乗せたLPを間違ったか、止めてコースターを確認する、ECMだ、ノオオオ!ついにECMはプレス・ミスしたんだぜ!というくらい俺の度肝を抜いた作品だった。『The Epidemics』
(http://www.ecmrecords.com/Catalogue/ECM/1300/1308.php?cat=%2FArtists%2FShankar%23%23Shankar&we_start=0&lvredir=712)、ギター:スティーブ・ヴァイに、ベース:パーシー・ジョーンズでっせ、ロック者もプログレ隔離室ものけぞる組み合わせ。
竹田さんの記事がなければ、今でもビューティフルなECMばかりを求めるリスナーのままだった可能性がある。コペルニクス的なんとか、だ。竹田さんのリストにはミシャ・アルペリン『Wave Of Sorrow』もあったなあ、ほかのラインナップはどんなだったろう・・・。
You Tube ではこんなのがあります。たまらんです。
L.Shankar Caroline & Ustad Allah Rakha - Milano, Teatro Ciak, 30/08/1993
http://www.youtube.com/watch?v=r48n2dImHoY
L. Shankar & The Epidemics - Sankarabaranam Pancha Nadai Pallavi
http://www.youtube.com/watch?v=6cbimKNih7g
Shankar , Trilok , Garbarek , Hussain = Germany 1984
http://www.youtube.com/watch?v=691yTHowzds

<track 264> Breathless / Ulrich Lask from 『Indean Poa』 (CMP 62) 1995
ECMレーベルが80年代前半に、ニューシリーズを開始する84年ちょっと前に、アヴァンギャルド〜ポスト・パンクに手を伸ばしていた時期があったかな、上記のシャンカール、ルー・リードのバックをつとめたというエブリマン・バンド、そしてファーストでマギー・ニコルスを配置したラスクの2枚、このジャーマン・パンクのカッコ良さは中毒性の高い代物。2枚とも廃盤。
デヴィッド・バーンの劇中音楽盤『ニー・プレイズ』がアメリカのECMから正規番号無しでリリースされたこともあった。これはアイヒャーの右腕だったボブ・ハーウィッツが手がけたもので、ハーウィッツはノンサッチ・レーベルに移ってメセニーやフリゼールを連れて行ってしまった格好になった。
ラスクのよもやの3作目『Indean Poa』がCMPレーベルから出ていたのは、竹田さんに教わった。これがまた95年なりのコンテンポラリーな傑作で、ウォルター・キンテス Walter Quintus という Degitalia 担当の音像表現が素晴らしい。ダンサブルなビートをくぐもらせてラスクのサックスを重奏させる手つき、サウンドのスケープを歪ませる仕上げかたは現在でも通用する尖り具合だ。
ウルリッヒ・ラスクはサックス奏者で、このディスコグラフィー(http://www.discogs.com/artist/Ulrich+Lask)での08年の2枚は、悠然と自然音の中で吹いていますな、なんか浮波雲のようななよなよしてて自然体、それでいてカッコいいという孤高。

<track 265> 子供達を責めないで / 伊武雅刀 1983
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=RiGRbC4n6mc
わたしはECM好きが嫌いです。ECM好きは幼稚で礼儀知らずで気分屋で、前向きな姿勢と無いものねだり、心変わりと出来心で生きている。4ビートだ、スイングだ、新伝承派だと、ハッキリくちに出してひとをはやしたてる無神経さ、わたしははっきり言ってウイントンです、ウイントンです!
努力のそぶりも見せない、忍耐のかけらもない、ジャズの深みも渋みも、なーんにも持っていない、そのくせ下から見上げるようなあの態度!ジャズ雑誌新譜コーナーでは足手まとい、年間ベスト金賞では悩みの種、いつも音楽批評界の問題児、そんなお荷物みたいなそんな宅急便みたいなそんなECM好きが嫌いだ、わたしは思うのです、この世の中からECM好きがひとりもいなくなってくれたらと、ジャズファンだけの世の中ならどんなによいことでしょう、わたしはECM好きに生まれないでよかったと胸をなでおろしています!
わたっ、わたしはECM好きが嫌いだ、うん、わたしはECM好きが嫌いだ!ECM好きがモダンジャズのために何かしてくれたことがあるでしょうか?いいえ!ECM好きはわたしたちジャズファンの足をひっぱるだけです、身勝手で、足が臭い!
ジャレット、タウナー、ガルバレク、ジスモンチ、エバーハルト・ウエーバー、好きなものしか聴きたがらない、モダン・ジャズ史にはフタをする、エコーをかければ済むと思っているところがズルい、
何でも聴くECM好きも嫌いだ!コンテンポラリー・フォークだのフュージョンだの越境だのポストモダンだの、ジョー・マネリだの、ハイナー・ゲッベルスだの、すくすくとCDラックの背ばかり高くなりやがって、逃げ足がはやく、いつも強いものにつく、あの世間体を気にする目がいやだ、目が不愉快だ、なにがポストフリージャズだ、なにがクリスタル・サイレンスだ、なにが沈黙の次に美しいサウンドだ、
そんなECM好きのためにわたしたちジャズファンはなーんにもする必要はありませんよ、第一、
これだけECM盤があるのに、どの一枚だって無いでしょう、だったらいいじゃないですか、それならそれで結構だ、ありがとう、ね、わたしたちモダンジャズファンだけで刹那的に生きましょう、ね、ECM好きは嫌いだ、ECM好きは大嫌いだ、
はなせ、おれはモダン・ジャズ・ファンだぞ!
誰が何と言おうとわたしはECM好きが嫌いだ、わたしはホントウにECM好きが嫌いだー!
これは元歌。
SAMMY DAVIS JR - DON'T BLAME THE CHILDREN
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=DxZseSNZRDc
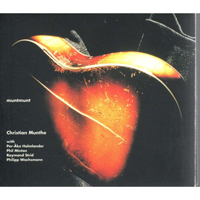
<track 266> muntmunt I / Christian Munthe from 『muntmunt』 (Blue Tower Records) 1994
Christian Munthe acoustic & electriv guitar
Per-Ake Holmlander tuba
Phil Minton voice
Raymond Strid drums
Philipp Wachsmann acoustic & amplified violin
午後3時すぎに起きて、暑くて、なんか涼しいCDないかなーと、大滝詠一「君は天然色」かけたりしてたんだけどダメで、
Christian Munthe スウェーデンの即興ギタリストの94年作『muntmunt』(Blue Tower)を、思い出した、このCDは処分しないで残している愛聴盤、このギタリストは掻きむしるような奏法のようで(傷だらけのギターがジャケ)、TPPトリオのトッド・ニューフェルドを連想する。ニューフェルドは痙攣してジャズの感覚に楔を打つ。
このChristian Muntheのたとえばソロ演奏を、涼しく聴いた、ということではなくて(それじゃあおハナシにならない)、以前のように、抽象図形の美を脳内に描くように聴くこともしていた、んだが、
ひとつのギター、ひとりの奏者であるソロ演奏に、複数のタイムラインといったものを視てみて、
たとえばボールの動きだけ見ればそのジグザグ、速度変化、高低、カーブが抽象図形美に近しいとして、サッカー選手の4・5にんの動き(=複数のタイムライン)が存在するものとして、
「聴こえてしまう」んだなあ・・・
もう20ねん近く前のレコーディングなんだけれど。
これもまた「メロディフェア状態」と言えるのではないだろうかー
独りで深夜に何を書いているのでしょうか
耳の枠はずし「ディスク・レヴュー2013年1月〜5月 その3」
http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-239.html
「エレクトロ・アコースティックなインプロヴィゼーションと器楽的インプロヴィゼーションをレヴューの対象として仕分けるようになった」ことへの説明の中で、「多田雅範がブログでこの謎めいた核心部分を的確に言い当てている」と評価いただいた(わはは、ちょっとドヤ顔モードかも)。
この「仕分け」は、全世界のクリティークの中で自覚的なのは福島さんだけだろう。益子博之さんの選曲にも、この耳の思考は備わっているように感じられる。・・・などと上から目線で書いていられるわたしではないのだ、福島さん、益子さんによって気付かされた視点で手元にある古い録音を耳にして(わはは、新譜が買えないので)は、驚いたとっさの一言に過ぎなかったのだ。
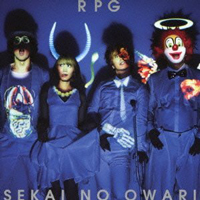
<track 267> RPG / SEKAI NO OWARI 2013
You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
なんとラストではバンドがダンスしている、のが、異様に感動的、たぶんおれだけ。
サウンドが空間的に収録されていないだんご状なのを悲しんでいるのも、たぶんおれだけ。
きゃりーぱみゅぱみゅと深瀬慧くんがラブラブデートの話題ですが、いいなあ。
安室奈美恵が「わたしにはわかっているんだ」と歌う新曲「Contrail」にもマーチングバンドが出てくる。
強い肯定感と全能感がなければ、マーチ、行進曲は機能しない(原田真二にも、パット・メセニーにも)。
世界戦争を予感しているのだったら、やばいよ。
バンド「世界の終わり」のピアノ、Saoriちゃんの才能をわたしは大きいとみているが、深瀬くんにとって先輩なのか、糟糠の妻ではないのか。アコースティック・ピアノのアクセントがすごくいいと思っているんだ。
ぱみゅぱみゅは中田ヤスタカの才気とクールジャパンの追い風でもって、失速していない。
世界の終わりは前シングル「スターライトパレード」の開放感、新曲「RPG」も前向きで、毒気の牙を隠しているように感じられるのが心配だ。
あれれ、トーマス・モーガンと会ったときの話は?
いいの、いいの、肝心なところは書かないの。
先日、京都の紅葉の名所といわれる寺へ行ったのですが、黒山の人だかり。境内を行列で進む人々が、前日テレビで紹介されたというポイントにくると、ここだ、ここだ、といっせいにデジタルカメラや携帯で撮影していました。それは記録映画で見た、草原に生息するプレーリードックの群れにそっくりでした。コミュニケーション・デザインにかかわってきた者として、忸怩たる思いで眺めたものです。この人たちは、最終的にはみずからの生命までも、他者のつくり出す意味や価値で消費することを望んでしまうのではないか。あらぬ思いに、散り落ちた紅葉が人びとの血痕に見え、怖気づいてしまったものです。(菊地信義)
Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。
 1.31 '16
1.31 '16
追悼特集
ポール・ブレイ Paul Bley
![]() :
:
#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美
#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武
#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡
#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武
#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス
#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター
#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣
![]() :
:
JAZZ RIGHT NOW - Report from New York
今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート
by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi
#10 Contents
・トランスワールド・コネクション 剛田武
・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
シスコ・ブラッドリー
・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま
第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻
音の見える風景
「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美
カンサス・シティの人と音楽
#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子
及川公生の聴きどころチェック
#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)
#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)
#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)
#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)
#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)
オスロに学ぶ
Vol.27「Nakama Records」田中鮎美
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説
#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)
![]() :
:
#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義
#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義
![]() :
:
#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣
#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠
#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄
#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄
#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄
Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.
ALL RIGHTS RESERVED.