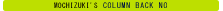かつて詩人の白石かずこは<音には色彩がある。音には匂いがある…>とエッセイ集『Visible Sounds 風景が唄う』(音楽之友社)の中で語っていた。橋爪亮督グループの音には風景がある。最新作『SIDE TWO』(APLS 1410)からはおだやかで幻想的な風景が浮かび上がってくる。新宿ピットインのライヴ録音でありながらサウンドはクールでスタティックにスタートする。ミニマル的なピアノに導かれ橋爪のテナーがメロディーを吹き市野のギターが絡む。そしてメンバー5人がゆるやかにそれぞれの景色を描き始める。グループのサウンドはいつしか白昼夢へといざない、やがてひとつの景色が浮かび上がる。モダンなコンテンポラリー・サウンドにもかかわらず、その奥からは幼いころに見た情景を思い出すような心地よい響きに満たされる。
橋爪亮督はテナー・サックス、ソプラノ・サックス奏者であると同時にコンポーザーであり、自らの世界観を音で表現する探究者でありサウンドのクリエイターである。
息の長いフレーズを滑らかに紡ぎライヴで付きものの火の出るような激しいブローは少しも表に出さず冷静沈着に自分の空間を積み上げてゆく橋爪亮督の姿に新しいクールの誕生を見る。
橋爪亮督は1990年からバークリー音楽大学で学び、ボストンに7年間暮らしていたがその滞在中に自己のグループでのライヴ活動もしている。
あるとき友人から電話がかかってきて、こんどライヴやるから時間の都合がつく?と聞かれたので<空いているけど誰がやるの>と答えたら<ユー>と云われ<誰がリーダーなの?>と聞いたら<ユアーズ>つまり、お前の曲をお前のバンドでやろうと云われてグループのリーダーとなりクラブで週2日、毎週演奏することになったのだという。
橋爪のサックスにギター、ピアノ、ベース、ドラムという5人編成は現在の橋爪亮督グループと同じ楽器構成で現在の橋爪亮督Gの原点といえる。ベース奏者をのぞいて全員がバークリーの友人達でメンバーには当時バークリーに学び現在は日本で活躍している清野拓巳(g)と工藤隆(p)も参加している。
そして「1996年6月29日、ボストンのクラブ「Willow Jazz Club」での橋爪グループのライヴ録音が2枚のアルバムとしてリリースされる。
『AND THEN YOU HEARD TALES RYO HASHIZUME』(1996、HAO RECORDS 428)
『In The Stranger’s Hand RYO HASHIZUME』(1997、HAO RECORDS 429)
この2作が橋爪のファースト・レコーディングとなる。
橋爪は自分のCDがアメリカのレコード店に並んでいるのを見たときは正直うれしかったですね、と語っている。
バークリーでは初め演奏科に入りアルト・サックスを学んでいたが、そこには世界中から学びに来ているミュージシャン志望者がいて、その中に入って自分の立ち位置を探ることになった。
<小さい頃からずっと音楽をやってきて我こそはって云う人がいろいろな国から来ているの、僕はと云えば小さい頃から音楽の英才教育を受けてきた訳でもなくて、ちょっといい気になって若気の至りでバークリーに来てしまったようなもので…>
このような環境のもとで、周りの人から日本人なのになぜ日本の音楽をやらないの、日本の楽器を演奏しないの、と云われて20歳の時に初めて壁にぶつかったと云う。
<やっぱり、お前の音楽って何?って云われたとき、いわゆる真似事しかやってきていないわけですよ、ジャズとかフュージョンとかを聴いてそれなりに吹けて満足していたんですが…やっぱりアメリカに行ったらすぐそばでアメリカが演奏しているわけですよね。そうなったら俺、今まで何やってきたんだろうということになって…周りの人からお前日本人なのに日本の音楽やらないのとかも云われて返す言葉がなくて>
<一時期、楽器を演奏することが怖くなって離れたことがあるんです。自分は何をやったらいいのかよく分からなくなってしまって学校に行くのも嫌になってしまってね>
今で云う引きこもり状態になり半年間バークリーを休学しアルバイトをしながら自問自答をしていた。
<で、その時は全てをやめて日本へ帰ろうとさえ思ったんですが、自分の中でこれではいけないかなって、それでいろいろ考えた結果、今までは自分が何を好きなのかを感じてやってきた訳なんだから小さい頃からジャズをやって、聴いて育ったアメリカの人とかブラックの人と同じことをやってもしようがないなと云う思いに至ってね>
<それなら自分で曲を書いてそれで演奏すればそれは良いと云われようが悪いと云われようが自分自身なので…それをするしかないと思って作曲科に入ったんです>
そして作曲科では自分で曲を書いて自分で集めたメンバーでリサイタルをやることを最初の目標にした。作曲家としての橋爪は自分のグループをスタートした時点で既に50〜60曲は作曲していたという。
作曲科ではテッド・ピースやグレッグ・ホプキンスに師事する。
橋爪はテッド・ピースの著書『ジャズにおける作曲の理論と実践 バークリー/ジャズ・コンポジション』(ATN)の翻訳も行っている。
好きな作曲家は沢山いるということであるが、あえてジャズ・ミュージシャンの中からあげてもらうとポール・モチアン(ds、1929〜2011)とキース・ジャレット(p)そしてウエイン・ショーター(sax)の名前をあげてくれた。
<ポール・モチアンは作曲家としても凄いですし、キースも作曲家として凄く影響を受けたんです、ショーターはプレイヤーとしても作曲家としても影響を受けていますね>
作曲科に入ると同時に楽器もアルト・サックスからテナー・サックスに替えている。
アルト・サックスでは行き詰まっていて自分自身になれなかったのだという。
<アルトではいろんな人をコピーしてそれが身についちゃっていたのと、あともう一つはアルトだと自分のしゃべっている声域よりも高いところの音が出るのでもっと自分の声に近い音域ということと、ゼロからやりたいと思ってテナーに替えたんです>
アルバイトで貯めたお金と母親から支援してもらったお金をもってニューヨークに行ってテナー・サックスを購入したというが現在もこの楽器を使っている。25年間愛用していることになるテナーはステージで渋い光を放っている。橋爪の描くサウンドの中から浮かび上がるテナーの響きは穏やかな中に芯のある力強さがあり、自分の音、自分の語り口を持っている。
橋爪亮督は1970年3月8日大阪の生まれで小、中、高、大学まで岡山で暮らす。
家では妹がピアノを弾き父親がクラシック音楽が好きで聴いていたという。
高校1年の時にブラス・バンドに入りアルト・サックスを始める。
この頃はフュージョン全盛期で、ラジオでよく聴いていたという。
大学は岡山大学の工学部に進み化学を専攻する。
大学2年の夏にバークリーのセミナー「バークリー・イン・ジャパン」に参加し奨学金をもらえることになる。
<たしか19歳の夏休みだったんですけど、まあ若かったですし、そういうのを貰えることに凄く得意気になっちゃって両親に行きたいって云ったら快くかどうかは分かりませんが行ってきなさいって言ってくれて>
1990年、岡山大を休学しバークリーに入学し1997年までの7年間をボストンで暮らす。
1997年の秋に帰国するが1カ月ほどで岡山から東京に移り住み日本での音楽活動を始める。
はじめはいろいろなジャム・セッションに顔出ししてミュージシャンに自分をアピールしたという。
<いちばん最初に声をかけてくれたのが廣木光一(g)さんで、廣木光一Gで「新宿ピットイン」とか西荻「アケタの店」とか今はない市川「リブル」とか色々教えてもらったんです>
<そのあと色々なグループに呼ばれたりしながら、貴方どういう人なの?って云われたらこういうことやってます、って云えるグループをつくってリーダーでやっていかなくてはと思いまして自分のグループをつくりました>
さまざまなセッションに参加しながら「橋爪亮督グループ」を結成し活動を継続している。
セッションで一緒に演奏しているベースの吉野弘志は<もう7〜8年位かな、レギュラー・グループとしてではないんですけどちょくちょくセッションでやったりしています。そうですね、とにかく楽器の技術はしっかりしているし、で、何というか音感が鋭いというか、その音感が鋭いのと理論的なこともしっかりしているし表面的にはクールに見えてもとにかく内容的、内面的には熱いプレイをしていますよ>と語ってくれた。
橋爪自身も吉野弘志とのセッションを大切にしている。
<吉野さんは大きいですね、大きいんです、大地を感じるんです、僕好きなんです>
他のグループのレギュラーになることが殆んどなかった橋爪が唯一レギュラーで参加していたのが「平井庸一グループ」で10数年にわたって徹底してレニー・トリスターノ(p)系のクール・ジャズを演奏している。因みに平井庸一とは偶然1970年3月8日の誕生年月日が同じだったそうである。
<平井さんが僕の演奏を聴きに来てくれたんですよ、で控室に訪ねてきてくれて、初めまして僕 平井庸一です、といってトリスターノの譜面をどんと渡してこういう曲やっているんですけどよかったら一緒にやって下さいって云われて、トリスターノは嫌いじゃなかったから、ハイって返事して参加することになったんです>
橋爪はクール・サウンドが好きでリー・コニッツ(as)やウオーン・マーシュ(ts)がサックス・プレイヤーとしても作曲家としても大好きなのだという。
<トリスターノは今でこそそんなに新しくないかもしれませんけど、当時は斬新で、あのサウンドっていうのはワン・アンド・オンリーで自分のスタイルと個性を持っていることと演奏家として凄くチャレンジングなんですよね、そういう意味で好きですね、難解ですけど>
橋爪は平井庸一Gでアルバム・タイトルもずばり『LENNIE`S PENNIES』(Marshmallow Records 2008)、『MAARIONETTE 』(Marshmallow Records 2009)の2枚のアルバムに加わっている。
そして更に2009年の10月27日、平井Gの一員としてトリスターノ派の重鎮テッド・ブラウン(ts)と「新宿ピットイン」で共演し『LIVE AT PIT INN,TOKYO TED BROWN』(Marshmallow Records、2010)を残している。
<テッド・ブラウンと一緒に演奏することが出来て何というか夢心地でした!>
バークリーからもどった市野元彦(g)が2001年の7月新宿ピットインに橋爪亮督を訪ね、翌8月のステージから市野が橋爪亮督Gに参加することになり現在に至るまで足掛け15年にわたって市野は橋爪Gの中軸として演奏している。
市野元彦が加わってからはギター入りのカルテットやクインテットなどさまざまな編成でグループのサウンドを構築しながら作品を残している。
この頃の作品にはディスコグラフィーによると『WORDLESS』(POLYSTAR JAZZ LIBRARY、2007)、『AS WE BREATHE』(BounDEE JAZZ LIBRARY、2008)、『Needful Things』(Grapes Records、2009)などがある。
そして、2012年、現メンバーでの『ACOUSTIC FLUIDアコーステイック・フルード』(tactilesound records、2012)を発表する。
メンバーは橋爪亮督(Ts、LOOPS)、市野元彦(g)、佐藤浩一(p)、織原良次(fretless-b)、橋本学(ds, per)の5人。
市野元彦(g)は「rabbitoo」や「幽玄郷+1」、渋谷毅(p)とのデュオ等で活躍中だし、佐藤浩一(p)は洗足音大〜バークリー出身で自己のグループや「rabbitoo」、土井徳浩(cl)カルテット等で、織原良次(fretless-b)はフレットレス・ベースの第一人者で「織原良次Mid」や野本晴美トリオ等、橋本学(ds, per)は田中信正(p)トリオや西山瞳(p)トリオ他で活躍しているそれぞれ今もっとも忙しい売れっ子ミュージシャンが揃っている。
<一時期はカルテットでやっていたときもあるんですが、勿論ピアノもギターもハーモニーを出せる楽器なんですけど、そのどちらか一つにしてしまうとどうしても負担が大きくなって、今はこの5人の編成が落ち着いていますね>
このメンバーで2012年の4月20日、新宿ピットインでCD『ACOUSTIC FLUID』の発売記念ライヴを行うが、この時の演奏と11月30日の「橋爪亮督G TOUR 2012“ACOUSTIC FLUID”」のライヴ演奏をまとめてCD『VISIBLE/INVISIBLE』(Apollo Sounds、2013)として発表、そして更にこのときの音源と2013年7月10日の新宿ピットインでのライヴ演奏からセレクトして『SIDE TWO』(Apollo Sounds、2014)をリリースしている。
この『VISIBLE/INVISIBLE』と『SIDE TWO』は2作品とも橋爪が日本でのプロ・デビュー以来ずっと大事にして演奏し続けてきた新宿ピットインでのライヴであり、写真に例えるとポジとネガのような相関関係が感じられ、この2枚のアルバムを通して聴くと現在の橋爪亮督Gの実像がくっきりと浮かび上がってくる。
橋爪Gは原則、橋爪のオリジナル曲を演奏するグループであるがコントロールされたものと自由度がうまく両立していて、どの曲もフィルム写真のような深みのある他の誰にもない橋爪亮督の世界を形作っている。
橋爪は写真が好きで、今時、古いフィルム・カメラで主に風景を撮っているというからかなりの凝り性のようでこの辺にも音楽との接点がありそうである。
橋爪亮督にとってのジャズってなにかを最後に伺った。
<難しい質問で答えに至るまでにはもっと時が必要なのだと思いますが…簡単に言ってしまえば、やっぱり自分がもっとも解放される表現の場だと思います>


 1.31 '16
1.31 '16![]() :
:![]() :
:![]() :
:![]() :
: